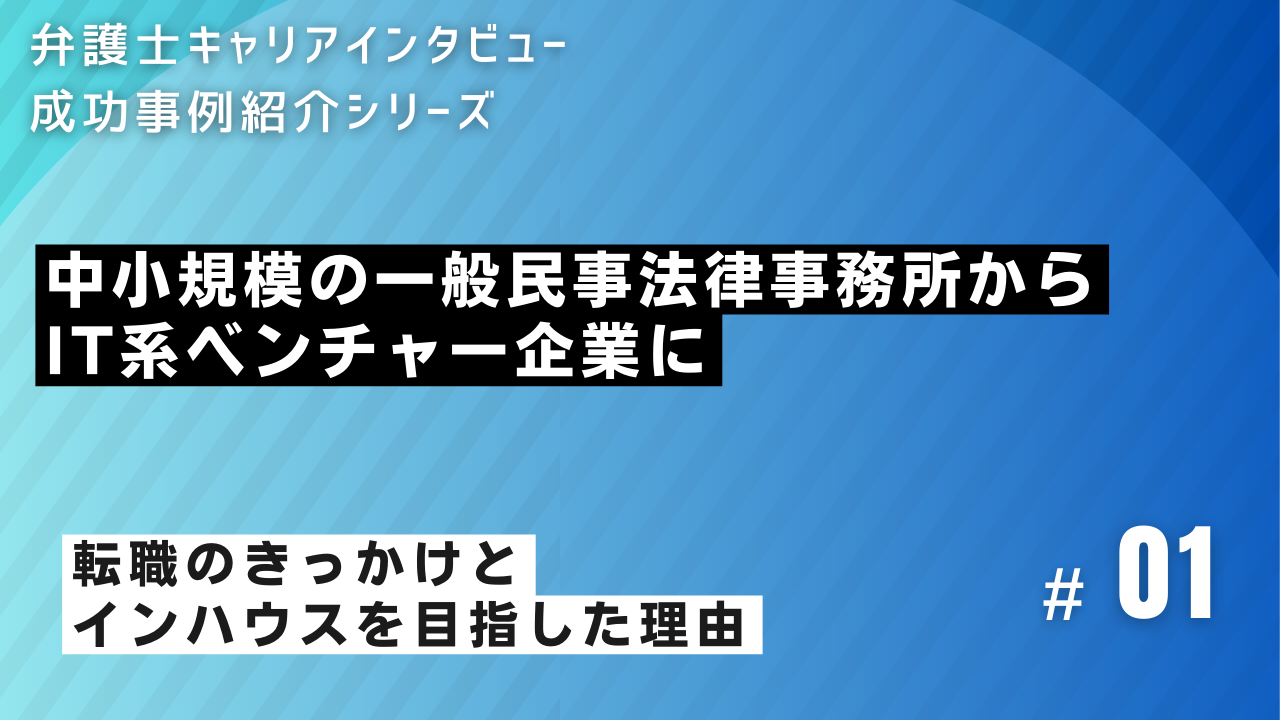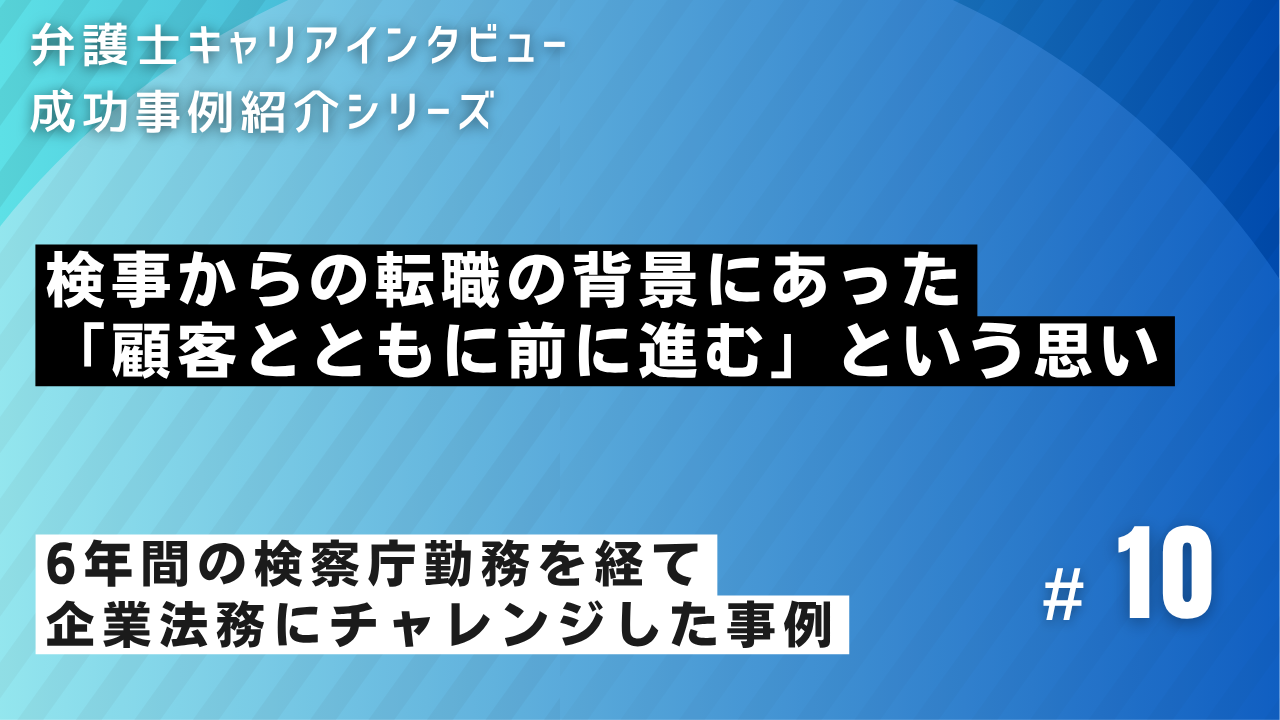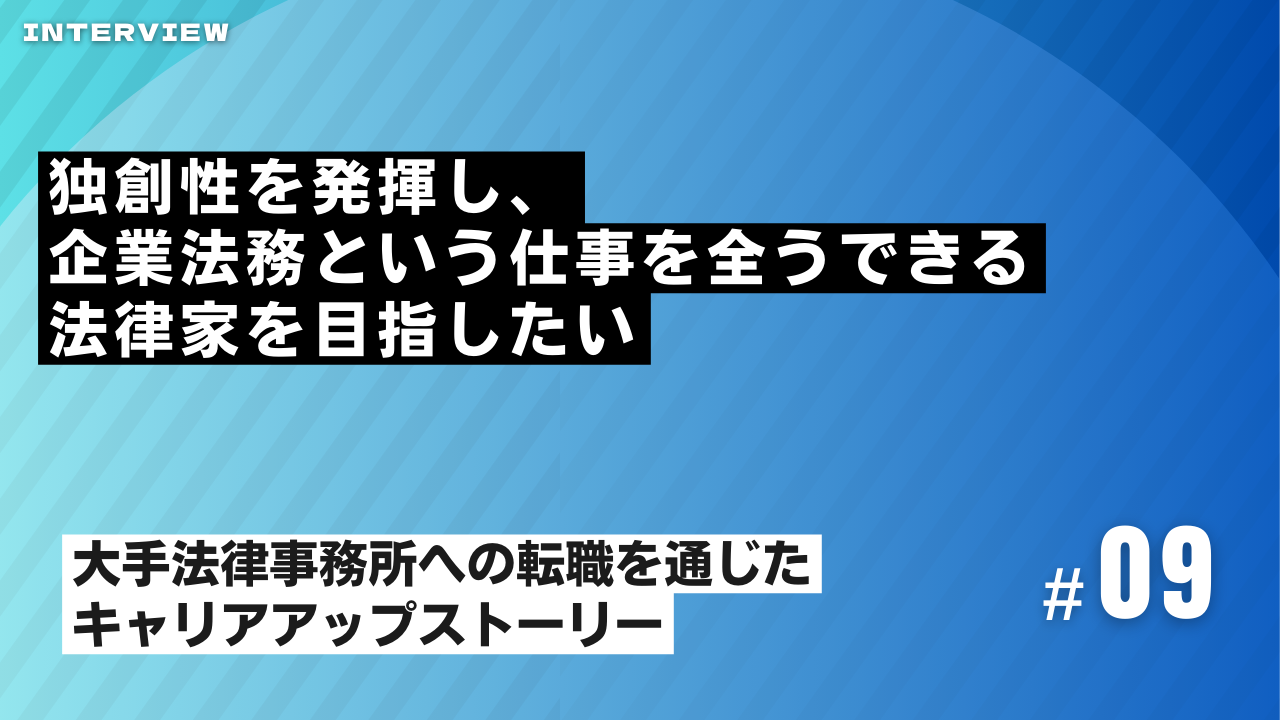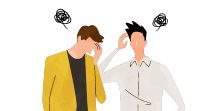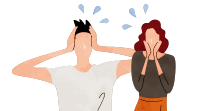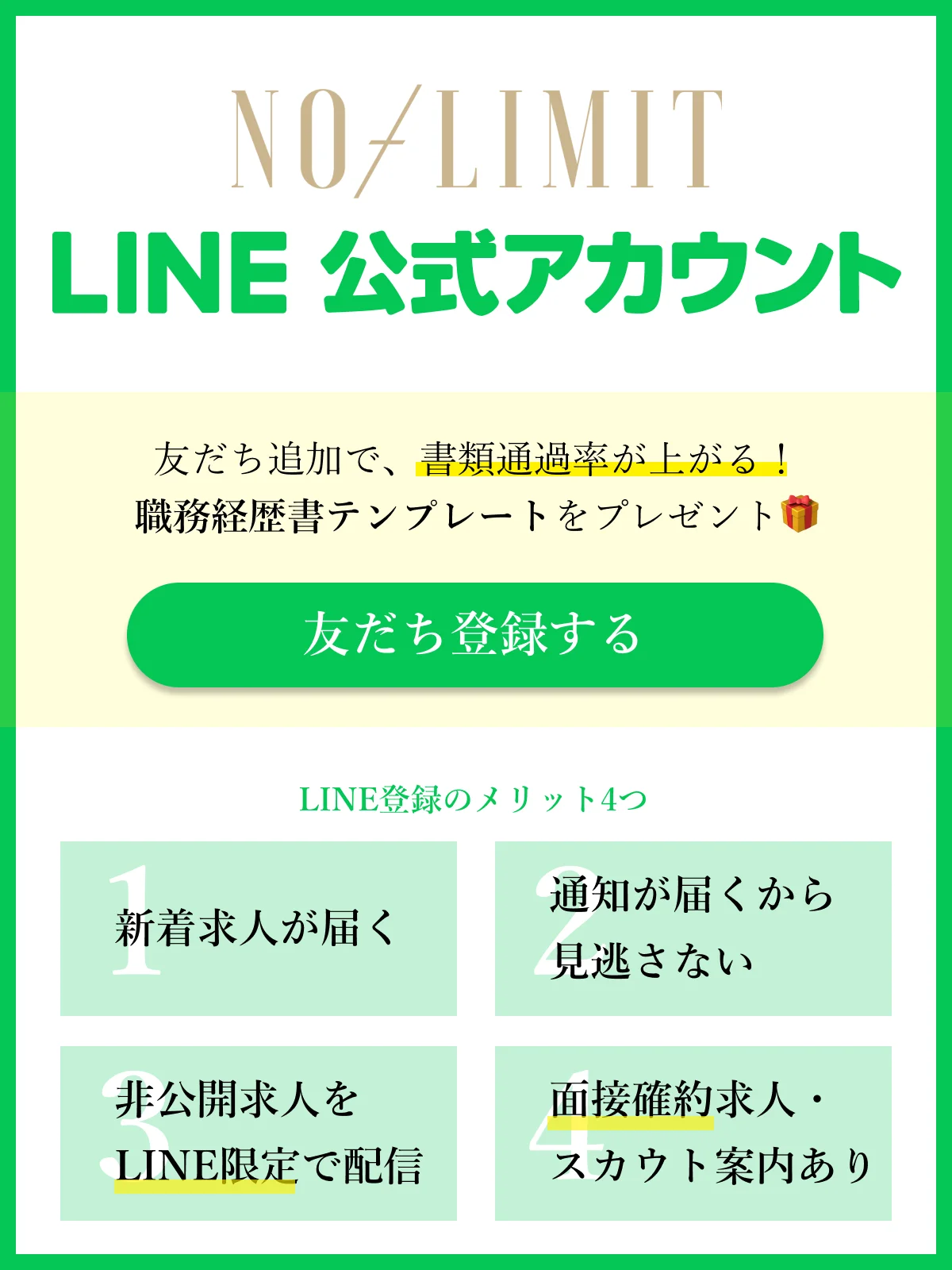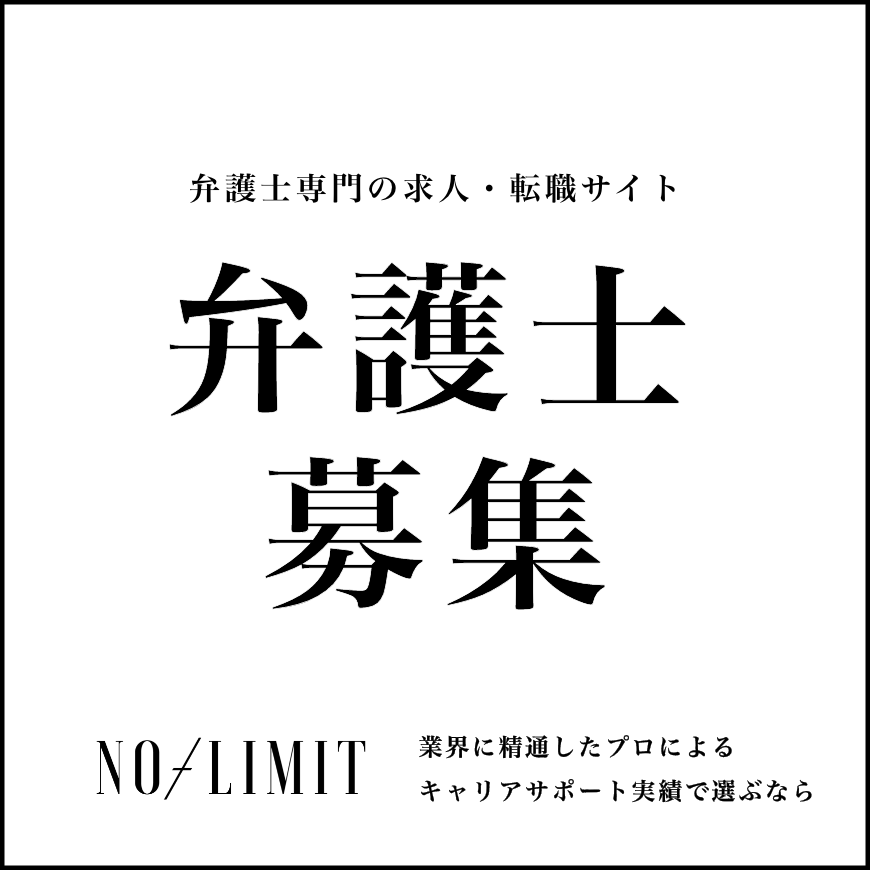こんにちは、弁護士特化の転職エージェント『NO-LIMIT』です。
インハウスローヤー(企業内弁護士)への転職を考えているものの、志望動機の書き方や応募書類の作成に悩んでいませんか?実は、多くの弁護士が同じような不安を抱えています。
法律事務所での経験をどのように企業側にアピールすべきか、企業法務の経験が少ない場合にどう自己PRすればよいのか。本記事では、実際にインハウスローヤーとして転職に成功した方々の経験とアドバイスをもとに、効果的な志望動機の書き方や、企業の採用担当者の心に響く履歴書・職務経歴書の作成方法をご紹介します。
「インハウスローヤーになりたい」という思いは持っているけれど、実際の転職活動となると何から始めればよいのかわからない。そんな方のために、本記事では以下のような疑問にお答えしていきます。
- 企業はインハウスローヤーに何を求めているのか?
- 法務経験が少なくても転職は可能なのか?
- 志望動機は具体的にどう書けばよいのか?
- 履歴書・職務経歴書では何をアピールすべきか?
これらの疑問に対して、弁護士専門の転職支援を行うNO-LIMITの編集部が、実例を交えながら具体的な解決方法をお伝えします。さらに、実際の転職成功者の体験談も紹介することで、あなたの転職活動を成功に導くためのヒントを見つけていただけるはずです。
また、NO-LIMITは『日本組織内弁護士協会』の公式スポンサーです。昨今のインハウス事情や転職市場において、弁護士が活躍できるスキルや経験などを詳しくご紹介します。
目次
インハウスローヤー(企業内弁護士)の役割と求められる資質
インハウスローヤーの志望動機を考えるまえに、企業にとってインハウスローヤーはどのような役割を持っているのか、何が求められているのかを探っていきましょう。
インハウスローヤーの主な業務内容
インハウスローヤーは、企業内において幅広い法務業務を担当します。主な業務は大きく以下の4つに分類されます。
まず1つ目は契約書の作成・審査業務です。取引先との契約書のチェックや修正、社内の各部門からの法的相談対応など、日常的な法務サポートを行います。
2つ目は法的リスク管理です。コンプライアンス体制の構築・運用、役職員への法務研修の実施、各種社内規程の整備などを通じて、企業活動における法的リスクの予防と管理を担います。
3つ目は取引先や株主とのネゴシエーションです。M&A案件や重要な取引における交渉、株主総会の運営支援など、企業の重要な局面での法務サポートを提供します。
4つ目は訴訟対応です。企業が当事者となる訴訟案件について、社内の窓口として外部の法律事務所と連携しながら対応を進めます。
法律事務所の弁護士とは何が違う?
法律事務所の弁護士とインハウスローヤーには、仕事の進め方や求められる視点に大きな違いがあります。
法律事務所の弁護士は、様々なクライアントの個別案件に対して、法的な観点から専門的なアドバイスを提供します。一つの案件に対して深く掘り下げた法的分析を行い、純粋に法的な解決策を提示することが求められます。
一方、インハウスローヤーは企業という「唯一のクライアント」に対して、より広い視点でのアドバイスが求められます。法的リスクの分析だけでなく、ビジネス上の影響や実現可能性、コストなども考慮しながら、総合的な判断のもとで解決策を提案する必要があります。また、社内の各部門と密接に連携しながら、予防法務の観点からも活動することが特徴です。
インハウスローヤーと顧問弁護士はどう違う?
インハウスローヤーと顧問弁護士は、どちらも企業の法務支援を行いますが、その立場や関わり方に明確な違いがあります。
インハウスローヤーは企業の従業員として、日常的に社内の様々な法務案件に関与します。経営陣や各部門との密接なコミュニケーションを通じて、企業の事業戦略や文化を深く理解した上で、予防法務を含めた包括的な法務サポートを提供します。
これに対し顧問弁護士は、外部の専門家として必要に応じて企業の法務支援を行います。特に専門性の高い案件や、利害関係者との調整が必要な重要案件において、その専門知識と経験を活かした支援を提供します。多くの場合、インハウスローヤーは顧問弁護士と協力しながら、企業の法務体制を強化していきます。
同じインハウスでもベンチャー企業と大企業で違いはある?
ベンチャー企業と大企業では、インハウスローヤーに求められる役割や業務内容に大きな違いがあります。
ベンチャー企業では、少人数で幅広い業務をカバーすることが求められます。法務部門が自分一人という場合も多く、契約審査から労務問題、知的財産管理まで、様々な法務課題に単独で対応する必要がでてくるでしょう。また、事業のスピードが速いため、迅速な判断と柔軟な対応力が重視されます。時には経営判断にも関与する機会が多くなりがちです。
一方、大企業では比較的細分化された業務を担当することが一般的です。たとえば契約審査専門、M&A専門、コンプライアンス専門といった具合です。チームで業務を進めることが多く、社内の確認プロセスも整備されています。その分、専門性を活かした深い分析や、組織的なリスク管理が求められます。
企業がインハウスローヤー人材に求める人物像
企業がインハウスローヤーを採用する際、多くの方が思い浮かべるのは「高度な法律知識」や「豊富な実務経験」でしょう。しかし、実際の採用現場では、それ以外の要素がより重視されることも少なくありません。
企業内で法務部門の一員として働くインハウスローヤーには、法的スキルに加えて、ビジネスパーソンとしての資質も求められます。以下では、具体的なスキル要件と、さらに重要な「人物像」について、詳しく解説していきます。
インハウスローヤーとして働くうえで求められる7つのスキル
企業に採用され、会社員と同じように働きながら法務に携わっていくインハウスでの仕事は法律事務所と異なり、自分の所属する部門以外の部署、他の弁護士とも連携しながら法務を進めていく必要があります。
インハウスに求められるスキルの大前提として、以下の10個が求められます。
| スキル | 詳細 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 法律知識 | 企業法務に関連する法律(会社法、契約法、労働法等)の深い理解と実践的な知識 | 企業活動のあらゆる場面で法的判断が求められるため。 特に予防法務の観点から、潜在的なリスクを事前に発見し対処する必要がある。 |
| 法的思考力 | 法的リスクを分析し、適切な解決策を導き出す能力 | 複雑な事案でも論理的に整理し、法的観点から問題の本質を見抜き、実務的な解決策を提示する必要があるため。 |
| 状況判断能力 | ビジネス上の要請と法的リスクのバランスを取りながら、最適な判断を下す能力 | 法的リスクを完全に排除することは現実的ではなく、ビジネスの推進とリスク管理のバランスを取る必要があるため。 |
| コミュニケーション能力 | 法律の専門家ではない社内の各部門のメンバーと円滑にコミュニケーションを取る能力 | 法律用語を平易な言葉で説明し、各部門の担当者と建設的な対話を行う必要があるため。 また、経営陣への報告・提案も重要な役割となる。 |
| 英語力 | グローバルビジネスに対応するための英語でのコミュニケーション能力(※業種・企業により要求レベルは異なる) | 海外取引や外国企業との契約交渉、国際的な法務対応が増加しているため。英文契約書の作成・審査も必要となる。 |
| 文書作成能力 | 契約書やリーガルメモ等、正確かつ分かりやすい文書を作成する能力 | 法的な正確性を保ちながら、非法務部門の担当者にも理解しやすい文書を作成する必要があるため。 |
| 交渉力 | 社内外の関係者と建設的な交渉を行い、合意形成を図る能力 | 取引先との契約交渉や、社内での各部門との調整など、様々な場面で交渉・調整が必要となるため。 |
| ビジネスセンス | 企業活動全体を理解し、経営的視点から法務課題を捉える能力 | 法的判断だけでなく、事業戦略や収益性も考慮した総合的な判断が求められるため。 |
| 実務経験 | 会社の発展にも貢献する分野での実務経験 | 複雑な法務課題への対応や、外部弁護士との効果的な協働に役立つため。 また、企業によっては法律事務所以外の会社での勤務経験を持っていたほうが良いとされる場合がある。 |
| マネジメント経験 | チームやプロジェクトのマネジメント経験(※上位職位では重視) | マネジメント経験のある弁護士は非常に少なく、インハウス転職市場では非常に珍しい人材とされている。 企業では、年代が上がると後輩をマネジメントするスキルが問われてくる。 |
【重要】スキルや経験よりも人柄が重視されがち
法務としての経験が浅い方でも、、『コミュニケーション能力』『意欲』『業務への興味関心』がある方であれば、多くの内定事例があります。
経験弁護士はより高いポジションでの採用をされている傾向にあるものの、やはり大事なのは相手の対話であると言えます。
そのため、必ずしも企業法務系事務所での長期経験や、高いスキルなどは無くてもインハウスローヤーになれるのです。
法務経験や足りないスキルは「人間力」で埋められる
弁護士としての経験、年齢などがほぼ同じ求職者がいたとします。大きく異なるのは「企業法務の経験」だけ。1人は5年以上企業法務事務所でレピュテーションリスクや法務マネジメントを経験、もう一人は一般民事事件はやってきたものの、企業法務は未経験です。
この条件だけで見た場合、1人を採用するなら、5年以上企業法務の経験がある弁護士を採用するでしょう。
では、法務未経験の弁護士が採用されるにはどうしたらよいでしょうか?
結論から言うと、コミュニケーション力や会社業務内容の理解度を高める、企業理解を高め、これから組織の中で高いパフォーマンスを発揮できる「人間力」を高めて差をつけることです。
企業研究もかなり大事な内定ポイント
一見すると難しいことを言っているように聞こえるかもしれませんが、「入社時の能力に差があったとしてもそれは努力で埋められる」と採用側は考えています。例えば面接のスタートラインで能力・経験に差があったとしても、対人コミュニケーションに癖のある人とは仕事の効率化は図れません。
そこで大事になる要素が『企業研究』です。
「企業の法務部」といっても、求められることやその実態は企業ごとに違います。これは、企業のフェーズ(上場前、上場直後、一部上場企業・・・etc)や、業態、カルチャーによって、事業の推し進め方が違い、法務部に求められる役割も異なってくるからです。
企業研究は採用側からしても興味を持って面接に臨んできているという評価になりますし、企業への理解が得られ単純に興味が持てるようなところがあれば、その分ミスマッチもしづらくなります。
企業は事務所以上に「人」を重視している
実は、法律事務所よりも企業の方がスキルよりも「人柄」を重要視する傾向にあります。もちろん法律事務所が「人柄」を見ていないということではありません。
特に弁護士を採用するフェーズの企業、すでにインハウスローヤーを抱えてらっしゃる企業は、「人材マネジメント制度」「人事評価システム」「人事考査」などがしっかりしています。
採用に関わる人事の方も、『この人は法務部で他の方とうまくできるか』『実際に入社した際に活躍できるか』など、面談の時点でかなりはっきりイメージしています。
「人」「人間力」とはコミュニケーション能力はもちろん、機転、想像力、調和力といったさまざまな要素を総合したものです。そのため、ただスキルが高いだけではなく、人柄が良いと思われる人、なにより誠実な人であれば、未経験でもインハウスへの道は開けると、断言できます。
インハウスローヤーとしての志望動機の作り方
志望動機は、単なる「なぜインハウスローヤーになりたいのか」という理由以上に、あなたの価値観や将来のビジョン、そして企業との相性を伝える重要な要素です。企業の採用担当者は、あなたの志望動機を通じて、組織への適合性や将来性を判断します。
ここでは、効果的な志望動機の作り方について、具体的な例を交えながら解説していきます。
説得力のある志望動機の3つの要素
説得力のある志望動機には、以下の3つの要素が欠かせません。
- 動機の具体性
- なぜ法律事務所ではなく企業なのか
- なぜその業界なのか
- なぜその企業なのか
- 企業との接点
- 企業の事業内容や課題への理解
- 自身のスキルや経験が企業にどう貢献できるか
- 企業の価値観との共感点
- 将来ビジョン
- インハウスローヤーとしてどのように成長していきたいか
- 企業の中でどのような役割を果たしていきたいか
- 中長期的なキャリアプラン
【経験別】志望動機の書き方
経験によって志望動機の重点を置くべきポイントは異なります。以下、経験別の効果的なアプローチ方法を解説します。
法律事務所からの転職の場合
法律事務所での経験を持つ方は、以下の点を意識して志望動機を組み立てましょう。
- 事務所での経験を活かせる点を具体的に説明
- 契約審査や法務相談の経験
- クライアントとのコミュニケーション経験
- 業界特有の法務知識
- インハウスを選択する明確な理由
- 事業への深い関与
- 予防法務の実践
- 企業の意思決定プロセスへの参画
- 避けるべきポイント
- 事務所での不満や消極的な理由
- 単なる働き方の改善目的
- 漠然とした企業への憧れ
企業法務部からの転職の場合
企業法務部での経験者は、以下の点を中心に志望動機を構成しましょう。
- 現在の企業での経験・知見
- 担当した法務業務の具体例
- 各部門との協働経験
- 成果や改善事例
- 転職を希望する理由
- より専門的な法務業務への挑戦
- 業界特有の法務課題への関心
- キャリアステップとしての意義
- 強調すべきポイント
- 企業文化への理解
- ビジネス感覚の習得
- 実務経験を通じた成長
新卒・司法修習生の場合
経験が少ない分、以下の点に焦点を当てて志望動機を作成しましょう。
- インハウスローヤーを志望する理由
- 司法修習や学生時代の経験
- 企業法務への興味を持ったきっかけ
- 業界・企業研究を通じて感じた魅力
- アピールすべき要素
- 学習意欲と成長への意志
- 柔軟な思考力とコミュニケーション能力
- 新しい視点や発想
- 重要なポイント
- 謙虚さと学ぶ姿勢
- 具体的な目標設定
- 企業・業界への深い理解
志望動機の具体例と解説
上記で解説した要素を踏まえ、実際の志望動機の具体例を見ていきましょう。これらの例は、企業の採用担当者から高評価を得た実例をもとに、ポイントを解説します。
【業界別】志望動機例
まずは、業界別にそれぞれの業界特性を踏まえた志望動機の例をご紹介します。
IT業界の場合:
「法律事務所での実務経験を通じて、テクノロジーの進化に伴う新たな法的課題に数多く触れ、その重要性を実感してきました。特に、AIやデータプライバシーに関する案件を担当する中で、テクノロジー企業の法務部門では、イノベーションを促進しながら適切な法的リスク管理を行うという重要な役割があると考えるようになりました。御社は、〇〇分野での先進的な取り組みを行っており、私の経験を活かしながら、新しい領域での法務課題に挑戦したいと考えています。」
製造業の場合:
「製造業の契約案件や知的財産関連の案件を多く担当してきた経験から、グローバルな製造拠点における品質管理や知的財産保護の重要性を深く理解しています。御社は海外展開を積極的に進めており、私のこれまでの経験を活かして、国際取引における法務リスクの管理や、各国の規制対応をサポートしていきたいと考えています。」
金融業界の場合:
「法律事務所で金融機関の各種規制対応や金融商品開発の法的サポートに携わる中で、金融法務の専門性とともに、事業戦略との整合性の重要さを実感してきました。御社は、フィンテックを活用した新規サービスの開発に積極的に取り組まれており、私のこれまでの金融法務の経験と、新しい技術・サービスへの関心を活かして、事業展開の法的支援に貢献したいと考えています。」
商社の場合:
「多岐にわたる事業領域と国際取引における法務課題に関心を持ち、これまで国際取引法務や各国の規制対応に重点的に取り組んできました。御社は、新興国市場での事業展開を強化されており、私の国際契約実務の経験を活かしながら、新たな事業機会の創出と適切なリスク管理の両立に貢献していきたいと考えています。また、各国の現地法務担当者との協働経験を活かし、グローバルな法務体制の強化にも寄与したいと思います。」
【企業規模別】志望動機例
次に、企業規模別で適した志望動機の例を紹介します。
大手企業の場合:
「グローバルに展開する大手企業の法務部門では、国際的な法務課題への対応や、コンプライアンス体制の整備など、幅広い業務が求められます。私は、これまでの法律事務所での経験を通じて、複数の大手企業の法務支援に携わり、組織的な法務管理の重要性を学んできました。御社の法務部門で、その経験を活かしながら、さらなる成長を目指したいと考えています。」
ベンチャー企業の場合:
「急成長するベンチャー企業では、スピーディーな意思決定と適切なリスク管理の両立が求められます。私は、スタートアップ企業の法務支援を通じて、成長フェーズに応じた柔軟な法務サポートの重要性を実感してきました。御社の〇〇という事業領域に強く共感し、事業の成長をリーガル面からサポートしていきたいと考えています。」
中堅企業の場合:
「中堅企業の強みである機動的な意思決定と、安定的な事業基盤を両立させた経営に魅力を感じています。私は、これまで様々な規模の企業の法務支援に携わる中で、企業の成長フェーズに応じた法務体制の構築が重要だと学んできました。御社は、〇〇事業で独自のポジションを確立されており、今後のさらなる成長に向けて、私の経験を活かしながら、効率的かつ実効性のある法務体制の構築に貢献していきたいと考えています。」
上場準備中の企業の場合:
「上場準備段階にある企業の法務支援を通じて、コーポレートガバナンスの構築やコンプライアンス体制の整備の重要性を実感してきました。御社は、〇〇分野でユニークな技術・サービスを持ち、今後の成長が期待される企業です。私は、上場準備に関する法務支援の経験を活かし、御社の持続的な成長を支える管理体制の整備に貢献したいと考えています。また、上場後の様々な法的課題にも、経営目線で対応していきたいと思います。」
よくある失敗例と改善ポイント
志望動機でよく見られる失敗例とその改善方法をご紹介します。
失敗例1:抽象的な表現に終始
- NG例: 「企業の中で法務の仕事がしたいと思いました」
- OK例: 「〇〇案件を担当した際、企業の意思決定プロセスに深く関わることの重要性を実感し...」
失敗例2:ネガティブな理由
- NG例: 「事務所の働き方に疑問を感じ、より働きやすい環境を求めて...」
- OK例: 「企業の中で予防法務の実践や事業戦略への関与を通じて、より深く法務に携わりたいと考え...」
失敗例3:企業研究不足
- NG例: 「大手企業で安定した環境で働きたいと思い...」
- OK例: 「御社の〇〇という事業戦略や、△△分野での先進的な取り組みに強く関心を持ち...」
改善のポイント:
- 具体的なエピソードや経験を必ず含める
- 企業・業界研究に基づく具体的な言及を行う
- 自身の経験や強みと企業のニーズを結びつける
- 前向きな理由を中心に構成する
- 実現可能な将来ビジョンを示す
インハウスローヤーの履歴書作成ガイド
インハウスローヤーの採用において、履歴書は応募書類の重要な一部です。法律事務所への応募とは異なり、企業への応募では、法務スキルだけでなく、企業人としての適性も評価されます。ここでは、企業の採用担当者の目に留まる効果的な履歴書の作成方法について解説します。
履歴書の基本フォーマット
一般的なJIS規格の履歴書をベースに、以下の点に注意して作成しましょう。
基本情報の記載
- 氏名:司法修習期(〇〇期)を括弧書きで記載
- 現住所:連絡がつきやすい住所を記載
- 連絡先:日中連絡可能な電話番号とメールアドレス
- 生年月日:西暦表記が望ましい
学歴・職歴の記載
- 学歴:法科大学院修了以降は必ず記載
- 職歴:
- 司法修習の経験を含める
- これまでの勤務先での具体的な担当業務
- 企業法務に関連する経験は詳しく記載
資格・特技欄の効果的な書き方
法曹資格以外の強みを効果的にアピールすることが重要です。
記載すべき資格例
- 語学関連:TOEIC、英検、その他言語の資格
- 業務関連:ビジネス法務検定、知的財産管理技能検定
- IT関連:基本情報技術者、ITパスポート
アピールポイント
- 資格取得年月を記載し、最新の学習状況を示す
- スコアや級を具体的に記載
- 業界特性に応じた資格を優先的に記載
自己PR欄のポイント
企業が求める人材像を意識しながら、簡潔に自己PRを記載します。
記載のポイント
- 3つ程度の強みに絞って記載
- 法務スキル
- コミュニケーション能力
- ビジネス感覚
- 具体的なエピソードを含める
- 実際の案件での成功体験
- 組織での協働経験
- 問題解決の実績
- 企業の求める人物像との接点を示す
写真・身だしなみの注意点
企業文化に合わせた適切な印象管理が重要です。
写真撮影時の注意点
- サイズ:
- 標準的なサイズ(40mm×30mm)を使用
- 3ヶ月以内に撮影したもの
- 服装:
- スーツ着用が基本
- 清潔感のある黒または紺色を推奨
- 派手な装飾品は避ける
- 表情:
- 自然な笑顔
- 真正面から撮影
- 背景は無地
身だしなみのチェックポイント
- 髪型:清潔感のある整った髪型
- メイク:ナチュラルなメイク(必要な場合)
- 写真全体:明るく好印象を与える仕上がり
これらの要素に気を配ることで、企業の採用担当者に好印象を与える履歴書を作成することができます。また、履歴書は定期的に更新し、最新の情報や実績を反映させることも重要です。
説得力のある職務経歴書の作成方法
職務経歴書は、あなたの専門性と実績を企業に伝える最も重要な書類です。インハウスローヤーの採用において、企業は単なる法務スキルだけでなく、ビジネスへの理解や組織での活躍可能性を重視します。ここでは、企業の期待に応える効果的な職務経歴書の作成方法を解説します。
職務経歴書の基本構成
効果的な職務経歴書は、以下の要素で構成します。
1. 基本情報(1ページ目)
- 氏名、連絡先
- 保有資格(弁護士登録年数、専門分野)
- 希望職種・職務内容
2. 職務要約(1ページ目)
- これまでのキャリアの概要(3~4行程度)
- 特に強みとする専門分野
- 主な実績のハイライト
3. 職務経歴(2ページ目以降)
- 時系列での経歴詳細
- 各役職での具体的な職責
- プロジェクト・案件実績
経験・スキルの効果的なアピール方法
経験やスキルは、具体的な実績とともに、その価値を明確に示すことが重要です。
法務実務経験のある場合
1. 専門分野の明確化
- 得意分野(例:M&A、知的財産、労務etc.)
- 取扱案件の規模や件数
- 業界特有の専門知識
2. 具体的な実務経験
- 重要案件の担当実績
- クライアント企業との協働経験
- チームマネジメントの経験
企業法務未経験の場合
1. 転用可能なスキル
- 法的分析力・文書作成能力
- クライアントコミュニケーション
- プロジェクトマネジメント経験
2. 自己啓発の取り組み
- 企業法務関連の研修・セミナー受講
- 業界知識の習得状況
- 関連資格の取得
具体的な成果の記載方法
成果は、可能な限り数値化して具体的に記載します。
数値化できる実績例
- 契約審査件数:「年間約200件の契約書審査を担当」
- 業務改善効果:「契約審査期間を平均30%短縮」
- コスト削減:「外部委託コストを年間20%削減」
定性的な成果例
- 「全社的な契約書テンプレートを整備し、業務効率化を実現」
- 「法務研修プログラムを確立し、社内の法務リテラシー向上に貢献」
- 「クロスボーダーM&Aにおいて主導的役割を果たし、案件を成功に導く」
企業視点で考える強みの表現方法
企業が求める価値の観点から、自身の強みを表現します。
1. ビジネス貢献の視点
- コスト意識:「効率的な外部弁護士の活用による費用最適化」
- リスク管理:「予防法務の実践による法的リスクの低減」
- 業務効率化:「法務プロセスの標準化による生産性向上」
2. 組織への貢献
- チーム協働:「他部門との円滑な連携体制の構築」
- 知識共有:「法務ナレッジの組織的な蓄積・活用」
- 人材育成:「若手法務担当者の指導・育成」
3. 将来性のアピール
- 成長意欲:「新規分野への積極的なチャレンジ」
- 学習姿勢:「最新の法改正や判例の研究」
- 変化対応:「デジタル化への対応力」
これらの要素を適切に組み合わせ、貴社の事業特性や求める人材像に合わせて強調点を調整することで、より説得力のある職務経歴書を作成することができます。
インハウスローヤーとしてのキャリアプラン
インハウスローヤーとしてのキャリアは、従来の法律事務所での働き方とは異なり、より多様な選択肢があります。企業内での役割の拡大や、経営層への参画など、自身の適性や志向に合わせた成長が可能です。ここでは、具体的なキャリアプランの立て方と、そのために必要な準備について解説します。
一般的なキャリアパス
インハウスローヤーのキャリアパスは、主に以下の3つのルートがあります。
1. 法務部門でのスペシャリストとして成長し、専門性を深め組織の中核へ
-
- 1~3年目:入社初期は、契約審査や法務相談対応といった基本的な業務を通じて、企業法務の基礎を徹底的に習得します。日々の業務を着実にこなす中で、企業特有の法務ニーズを理解し、実務スキルを磨きます。
- 4~6年目:経験を積むにつれて、重要案件の主担当を任されるようになり、チームリーダーとしての役割も担うようになります。プロジェクトを推進する能力や、チームをまとめる力が求められます。
- 7~10年目:マネージャーとして、法務部門の中核人材として活躍します。部門全体の業務を管理し、後進の指導育成にも携わります。
- 10年目以降:法務部長や統括マネージャーとして、法務部門全体を統括する責任者となります。経営戦略に法務の視点を取り入れ、組織全体を牽引する役割を担います。
このキャリアパスは、法務の専門性を深く追求したい方に適しています。企業内での経験を通じて、特定の業界やビジネスモデルに精通した法務スペシャリストへと成長することができます。
2. 法務の知見を活かし、企業経営に参画する経営層へのキャリアアップ
-
- 法務部長から、法務部門を管掌する執行役員へと昇進する。
- 企業の最高法務責任者であるCLO(Chief Legal Officer)に就任し、全社的な法務戦略を策定・実行する。
- 取締役(法務・コンプライアンス担当)として、経営の中枢に参画し、企業全体の意思決定に深く関与する。
法務の専門知識だけでなく、経営的な視点やマネジメント能力を兼ね備えた人材に開かれる道です。企業全体の戦略策定に法務の観点から貢献したい、という意欲のある方に向いています。
3. 他部門との連携により、法務の枠を超えて活躍の場を広げるキャリア展開
-
- コンプライアンス部門との連携を強化し、より統合的なリスク管理体制を構築する
- 経営企画部門と協働し、法務の観点から企業の戦略策定や新規事業開発を支援する。
- グローバル展開を進める企業において、海外法務部門と連携し、国際的な法務課題に対応する。
法務の専門性を活かしつつ、他の部門と連携することで、より幅広い視野を養うことができます。企業全体の成長に貢献したい、多様な経験を積みたいという方に適したキャリアパスです。
業界・企業選びのポイント
キャリアプランを実現するための業界・企業選択は重要です。次のようなポイントを考慮しながら、飛び込む業界や企業を選びましょう。
1. 業界選択の基準
携わりたい業界を選ぶ際は、「成長性」「専門性」の2つを軸にしながら選びましょう。
- 成長性
- 今後の市場成長が見込まれる業界かどうか
- 法規制の変化やグローバル化の進展に伴い、法務の専門性や需要がより重要となりそうか
- 国際的な法務知識や語学力が求められるような海外展開を進めているか
- 専門性
- 専門性の高い知識や経験が求められるような業界特有の法務課題に携われるか
- 規制環境の複雑で、より法規制に対する理解を深められるか
- 求められる専門知識が自身の専門性を活かせる業界かどうか
2. 企業選択のポイント
業界を選択したら、次は企業の選択です。「企業における法務部門の立ち位置」「企業文化」の2つを軸にしながら、じっくりと選びましょう。
- 法務部門の位置づけ
- 経営層が法務部門をどのように評価しているか、その重要度を把握しましょう。
- 法務部門が企業の意思決定にどの程度関与しているかを確認し、自身の意欲を活かせる環境を選びましょう。
- 法務部門の人員体制や、育成制度の有無は、今後のキャリア形成に大きな影響を与えるため、しっかりと確認しておきましょう。
- 企業文化
- 企業全体で法務部門の役割を理解しているかどうかは、働きやすさやキャリア形成に影響します。法務部門への理解度を確認しましょう。
- 人材育成に積極的な企業では、成長の機会が多く、スキルアップが期待できます。人材育成への投資をしているかを確認しましょう。
- ワークライフバランスを重視する場合は、企業ごとの働き方や制度を事前に確認しましょう。
求められるスキルの習得方法
インハウスローヤーとしてキャリアアップするためには、専門知識だけでなく、ビジネススキルや人脈も欠かせません。
次のようなスキルを身に着けながら、キャリアを着々と重ねていきましょう。
1. 法務の専門性を向上させる
- 実務経験を蓄積する
- 日常的な法務業務を、一つ一つ丁寧に、着実に遂行することで、実務スキルを着実に高めましょう。
- 重要案件には積極的に関与し、高度な法務知識と問題解決能力を身につけましょう。
- 外部弁護士との協働を通じて、様々な視点や専門性を学びましょう。
- 継続的な学習
- 法改正情報は常に最新のものを把握し、知識をアップデートしましょう。
- 業界特有の法務知識を習得し、専門性を深めましょう。
- 専門セミナーや勉強会に積極的に参加し、最新の情報を収集しましょう。
2. ビジネススキル面を強化する
- 基本的なビジネススキル
- 財務・会計の基礎知識を習得することで、ビジネス全体を理解し、法務の視点からより的確なアドバイスをすることができます。
- プロジェクトマネジメントの知識は、複雑な案件を効率的に進める上で役立ちます。
- ビジネス英語を習得することで、グローバルな環境でも活躍の場を広げることができます。
- マネジメントスキル
- チームマネジメントスキルは、チームをまとめ、目標を達成するために不可欠です。
- リーダーシップ開発は、組織を牽引し、より大きな責任を担うために重要です。
- 予算管理スキルは、組織運営において重要な役割を果たします。
3. 社内外の人脈を広げる
- 社内の人脈
- 各部門との関係を構築することで、円滑な業務遂行と相互理解につながります。
- 経営層とのコミュニケーションは、法務の重要性を理解してもらう上でも重要です。
- 後進の育成は、組織全体のレベルアップに貢献します。
- 社外の人脈
- 業界内の人脈形成は、最新の情報収集やキャリアアップに繋がります。
- 法務関連団体への参加は、同じ分野の人たちとの交流や情報交換の場となります。
- 勉強会や研究会への参加は、専門知識を深め、刺激を受ける良い機会になります。
これらのスキルを計画的に習得することで、より充実したキャリアパスを実現できるでしょう。また、定期的に自身のキャリアプランを見直し、必要に応じて軌道修正を行うことも重要です。
変化の激しい現代社会において、柔軟な姿勢を持ち、常に学び続けることが、インハウスローヤーとして成功するために欠かせない要素です。
選考対策と面接準備
インハウスローヤーへの転職活動において、選考対策と面接準備は非常に重要なステップです。企業は、応募書類だけでなく、面接を通じてあなたの人物像、スキル、企業への適性を見極めようとします。
ここでは、選考プロセスを理解し、効果的な面接対策を行うためのポイントを解説します。事前の準備を徹底することで、自信を持って選考に臨み、内定獲得に大きく近づくことができるでしょう。
選考プロセスの概要
インハウスローヤーの選考プロセスは、一般的に以下の流れで進みます。企業によって多少の違いはありますが、基本的な流れはほぼ同じです。
- 書類選考: 履歴書、職務経歴書、志望動機書などの応募書類をもとに、企業の求める人物像と合致するかどうかを判断します。弁護士としての経験やスキル、企業法務への関心度などが評価されます。
- 一次面接: 人事担当者や配属先の部門長などが面接官となり、あなたの経歴や志望動機、スキル、人柄などについて質問します。企業によっては、適性検査や筆記試験が実施されることもあります。
- 二次面接(または最終面接): 役員や社長などが面接官となり、企業理念への共感度や将来性、企業文化との適合性などについて見極めます。企業によっては、リファレンスチェック(前職の上司や同僚への照会)が行われる場合もあります。
- 内定: 選考の結果、企業があなたを組織の一員として迎え入れたいと判断した場合、内定が通知されます。
- 入社: 内定承諾後、入社手続きを経て、インハウスローヤーとしてのキャリアがスタートします。
企業によっては、面接回数が異なったり、選考プロセスに独自のステップを設けている場合があります。応募先の企業の選考フローを事前に確認し、しっかりと対策を立てることが重要です。
よくある面接質問と対策
面接では、あなたの経験やスキルだけでなく、企業への適性や熱意なども見られます。ここでは、インハウスローヤーの面接でよく聞かれる質問と、効果的な対策について解説します。
- 志望動機:
- 質問例: 「なぜ、インハウスローヤーを目指そうと思ったのですか?」「数ある企業の中から、当社を選んだ理由は何ですか?」
- 対策: 企業理念や事業内容を深く理解し、自身の経験やスキルと結びつけて、具体的なエピソードを交えながら説明しましょう。企業への貢献意欲や熱意を伝えることが重要です。
- 自己PR:
- 質問例: 「あなたの強みと弱みは何ですか?」「これまでの仕事で最も達成感を感じたことは何ですか?」
- 対策: 弁護士としての専門性だけでなく、コミュニケーション能力、問題解決能力、ビジネス感覚など、インハウスローヤーに必要なスキルをアピールしましょう。具体的なエピソードを交えながら、実績や成果を伝えられるように準備しておきましょう。
- キャリアプラン:
- 質問例: 「入社後、どのようなキャリアを築きたいですか?」「将来、当社でどのような貢献をしたいですか?」
- 対策: 企業内でのキャリアパスを理解し、自身の目標と企業の成長を結びつけられるように説明しましょう。長期的な視点で、企業への貢献意欲を示すことが重要です。
- 企業に関する質問:
- 質問例: 「当社の事業内容についてどのように考えていますか?」「当社の課題点は何だと思いますか?」
- 対策: 企業Webサイトやニュース記事などを参考に、企業の事業内容、業界動向、強みや課題などを理解しておきましょう。企業への関心度や企業研究の度合いを示すことが重要です。
- 逆質問:
- 質問例: 「入社前に準備しておいた方が良いことはありますか?」「配属先のチームはどのような雰囲気ですか?」
- 対策: 企業の事業内容や仕事内容、組織文化、今後のキャリアパスについて積極的に質問しましょう。企業への関心度や入社意欲を示すと同時に、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
面接では、質問に対して正直かつ誠実に答えることが大切です。また、面接官の目を見て、ハキハキと話すことも好印象を与えるポイントです。
企業研究の進め方
面接対策において、企業研究は欠かせません。企業のことを深く理解することで、より説得力のある志望動機や自己PRを作成することができます。
- 企業Webサイトの確認: 企業の理念、事業内容、組織体制、IR情報などを確認しましょう。企業の強みや課題、今後の戦略などを把握することで、企業への理解を深めることができます。
- ニュース記事や業界誌の確認: 企業の最新ニュースや業界動向をチェックしましょう。企業の最新情報を把握することで、企業への関心度や業界への知識を示すことができます。
- 社員インタビューの確認: 企業ホームページや転職サイトに掲載されている社員インタビューを参考に、企業の社風や働き方を理解しましょう。社員の生の声を聞くことで、入社後のイメージをつかむことができます。
- 企業説明会への参加: 企業説明会に参加することで、企業の担当者から直接話を聞くことができます。企業の雰囲気や社員の熱意を感じることができ、企業理解を深めることができます。
- OB・OG訪問: 可能であれば、企業で働くOB・OGに訪問し、仕事内容や企業文化について質問しましょう。実際に働く社員の話を聞くことで、より具体的なイメージをつかむことができます。
- 転職エージェントの活用: 転職エージェントは、企業の内部情報や選考対策に関するノウハウを持っています。転職エージェントに相談することで、より効率的に企業研究を進めることができます。
企業研究を徹底することで、入社後のミスマッチを防ぐだけでなく、面接で企業に対する熱意を効果的に伝えることができます。企業に対する理解度を深め、自信を持って面接に臨みましょう。
弁護士特化の転職エージェント
[NO-LIMIT]に登録する
転職成功者の体験談とアドバイス
【成功事例その1】弁護士1年目から某メーカー企業のインハウスローヤーに
K先生は、インハウスローヤーの講演を機にその魅力に惹かれ、司法修習直前期から就職活動を開始しました。法律事務所のサマークラークで経験を積むも、自身の適性と異なることを感じ、企業法務の道へ進むことを決意。20社ほどに応募し、5社から面接の機会を得ました。選考では、一般的なSPIや英語力テストに加え、英文契約書のレビューなどの実務能力を測る試験もあったとのことです。
現在の業務は、契約書レビュー、ドラフティング、プロジェクトのリーガルサポート、社内教育、訴訟など多岐にわたります。特に多国間契約の業務では、英語や第三言語でのコミュニケーションに苦労する一方、達成感も大きいと語ります。
K先生は、社内からの相談で感謝の言葉をいただく時にやりがいを感じ、現在の職場環境にも満足しているようです。将来的なキャリアビジョンとしては、マネジメントよりも法務スペシャリストとして現場でキャリアを磨いていきたいと考えています。
インハウスローヤーを目指す方へのアドバイス
インハウスローヤーに向いているのは、プライドが高すぎず、物事を素直に受け入れられる柔軟性を持つ人です。必要なこととしては、企業風土へのマッチングが非常に重要であり、企業法務の経験があれば有利に働くものの、能力よりも人格面が重視される傾向にあります。
業界による違いとしては、業務内容は業種によって異なりますが、待遇は大企業かベンチャーかで差が出やすいです。また、チーム法務か一人法務かで業務負担も変わるため、自身の働き方に合った環境を選ぶと良いでしょう。企業内には弁護士資格者がいると、弁護士会費や義務研修などへの理解が得やすいこともメリットです。
インハウスローヤーの仕事は、毎日違う人と出会い、違う課題に奔走するドラマチックな側面があり、決して法律事務所の下請け的な仕事ではありません。インハウスローヤーの魅力は、自分の知識や経験をフルに活かし、事業部門との連帯感を持って働ける点にあります。
【成功事例その2】中小規模の一般民事法律事務所からIT系ベンチャー企業に
地方の一般民事法律事務所に勤務していた弁護士は、結婚と家族の誕生を機に、ワークライフバランスを重視した働き方を求め、転職を決意しました。法律事務所での長時間労働を課題に感じており、企業法務に挑戦したいという思いが強かったようです。
また、会社勤めの経験がなかったため、企業内で法務の需要を肌で感じたい、会社勤め自体を経験してみたいという好奇心も転職の理由の一つでした。転職先を選ぶ際には、ワークライフバランスだけでなく、会社の業務内容に興味を持てるかを重視しました。
転職活動では、既にインハウスで活躍している知人の弁護士の紹介で転職エージェントを利用。求人情報が少ないインハウスの転職活動では、エージェントのサポートが不可欠だったと語ります。
インハウスローヤーを目指す方へのアドバイス
ワークライフバランスを改善したいというニーズが、転職活動の大きな動機付けになるでしょう。
インハウスを目指す理由としては、法律事務所とは異なる業務を経験したい、企業内で法務の需要を理解したい、会社勤めを経験したいといった、多様な動機がありえます。転職時に重視することとしては、ワークライフバランスだけでなく、企業の事業内容に興味を持てるかどうかも重要です。
また、インハウスの求人は少ないため、転職エージェントの利用が有効な手段となるでしょう。弁護士の働き方に決まった答えはなく、ライフプランに合わせて変化させても良いという考え方が大切です。
そして、職場を変え、新しい仲間と働くことは、新しい視点と価値観を得る機会となるはずです。
【成功事例その3】大手企業法務系事務所から転職先企業初の企業内弁護士に
Mさんは、大手企業法務系事務所から、転職先企業初の企業内弁護士として転職を果たしました。事務所勤務時代と比較して、プライベートの時間が大幅に増え、仕事とプライベートの両立を楽しんでいます。
転職先では、業務を任せてもらえる裁量の大きさにやりがいを感じており、1から10まで自分で考えて進められる環境に満足しています。以前の事務所では業務の一部にしか携われなかったため、自分が何をしているのか分からなかったという経験から、現在の責任感と達成感のある働き方に大きな魅力を感じているようです。
転職活動では、インハウスローヤーに関する情報が少ないと感じていたため、転職エージェントを活用。複数のエージェントを利用する中で、大手企業ばかりを紹介される状況に苦戦していましたが、最終的に、紹介された企業すべてで選考が進み、複数内定を得ることに成功しました。
インハウスローヤーを目指す方へのアドバイス
この事例では、転職によって、求めていたワークライフバランスと、裁量権のある仕事の両方を手に入れたという点がポイントです。転職エージェントをうまく活用することで、自分に合った企業を見つけることができたという点も重要です。
転職活動においては、情報収集が非常に大切です。転職エージェントをうまく活用することで、より効率的に転職活動を進めることができます。面接後には、エージェントと密にコミュニケーションを取って、自分の考えを整理することも大切です。
法律事務所とは異なり、企業の面接は形式的な部分もあるので、自分を飾らず率直に話すことが良い結果に繋がるかもしれません。自分の働き方を見つめ直し、転職を通じて理想のキャリアを築くことができるはずです。
弁護士がインハウスローヤー(企業内弁護士)に転職する方法
企業側がインハウスを求める傾向は強いため、インハウスへの転職チャンスは十分にあります。しかし、インハウスの求人数が多いわけではありません。では、インハウスへ転職するためにはどうしたらよいのでしょうか。
インハウスローヤーへ転職した弁護士からの紹介
すでにインハウスへ転職をした弁護士からの紹介で転職をするという方法です。
特に大企業の場合、インハウス人材を増やそうとしている傾向にあります。そのため、すでに自社インハウスの弁護士に対して、良い人材がいないかを打診する場合があります。
また、紹介という方法は、紹介してもらった側も一生懸命働きますし、紹介する側も中途半端な人を紹介することはありません。
希望条件がマッチし、仕事を任せても問題ないだろうと判断されると、勤め先の企業で募集が開始されたタイミングで声をかけてもらえる可能性があるのです。
弁護士に特化した転職エージェントを利用する
インハウスへ転職を行うための最良の方法は、転職エージェントの力を借りることです。
転職エージェントを利用すると、忙しいあなたに代わって希望するインハウスの労働条件や職場環境、さらには年収を見たうえで、あなたに合った企業をピックアップしてくれます。
また、アドバイザーが弁護士やインハウスについてどれだけ専門性を持っているかも、より良い転職エージェントの選び方においても重要です。
「NO-LIMIT」のアドバイザーへご相談ください
「インハウスローヤーへ転職したい」そう考えている人には、ぜひ「弁護士特化の転職エージェント:NO-LIMIT」をオススメします。
- ・履歴書と職務経歴書の圧倒的な添削力
- ・応募先企業を知り尽くしたエージェントによる志望動機作成のサポート
- ・あなたに合った求人を丁寧にご提案
- ・ブラック法律事務所の徹底排除
- ・企業法務未経験でも応募可能な求人を多数保持
このように、あなたのインハウスローヤーへの道を、力強くサポートする体制が整っています。
弁護士特化の転職エージェント
[NO-LIMIT]に登録する
まとめ:インハウスローヤーへの転職を成功させるために
インハウスローヤーへの転職は、弁護士としてのキャリアを大きく広げるチャンスです。この記事では、インハウスローヤーの役割、求められる資質、志望動機の作成方法、応募書類の書き方、選考対策、そして転職成功者の体験談まで、多岐にわたる情報をお届けしました。
インハウスローヤーへの転職は、決して簡単な道ではありません。しかし、この記事で解説したポイントを参考に、しっかりと準備を進めることで、必ず成功に近づけるはずです。
この記事が、あなたのインハウスローヤーへの転職活動を成功に導く一助となれば幸いです。自信を持って、あなたのキャリアを切り拓きましょう!