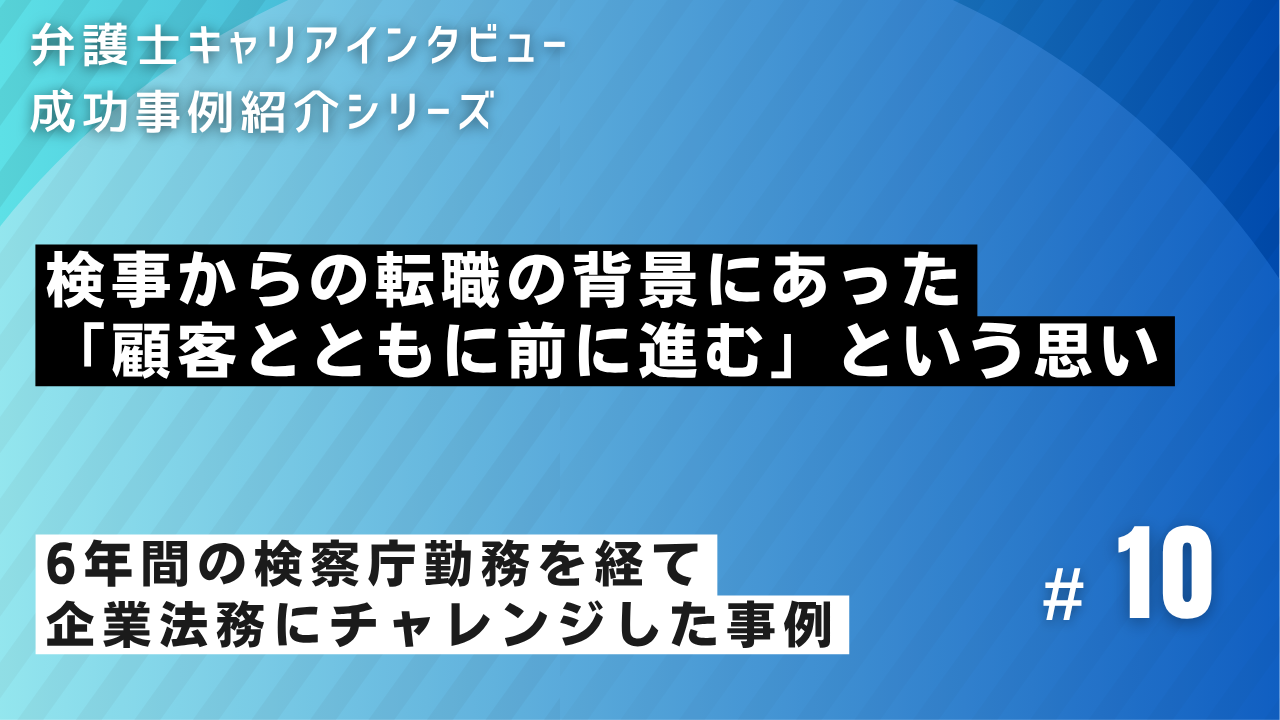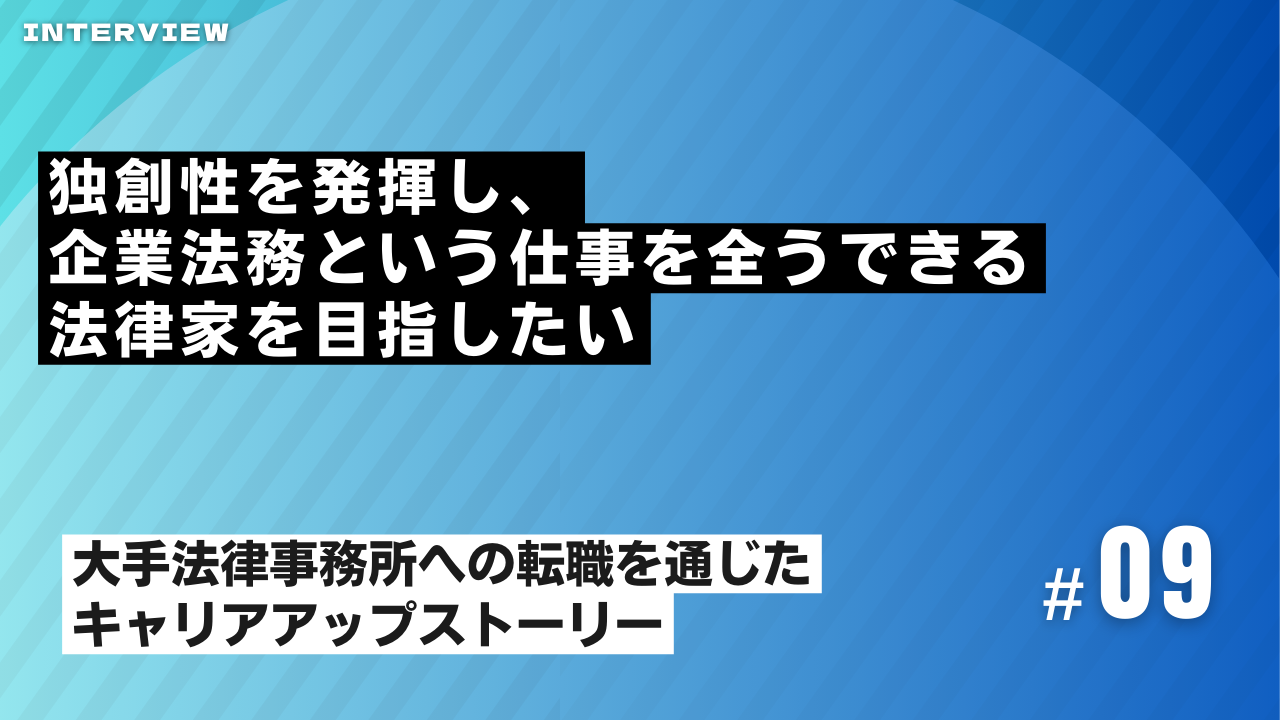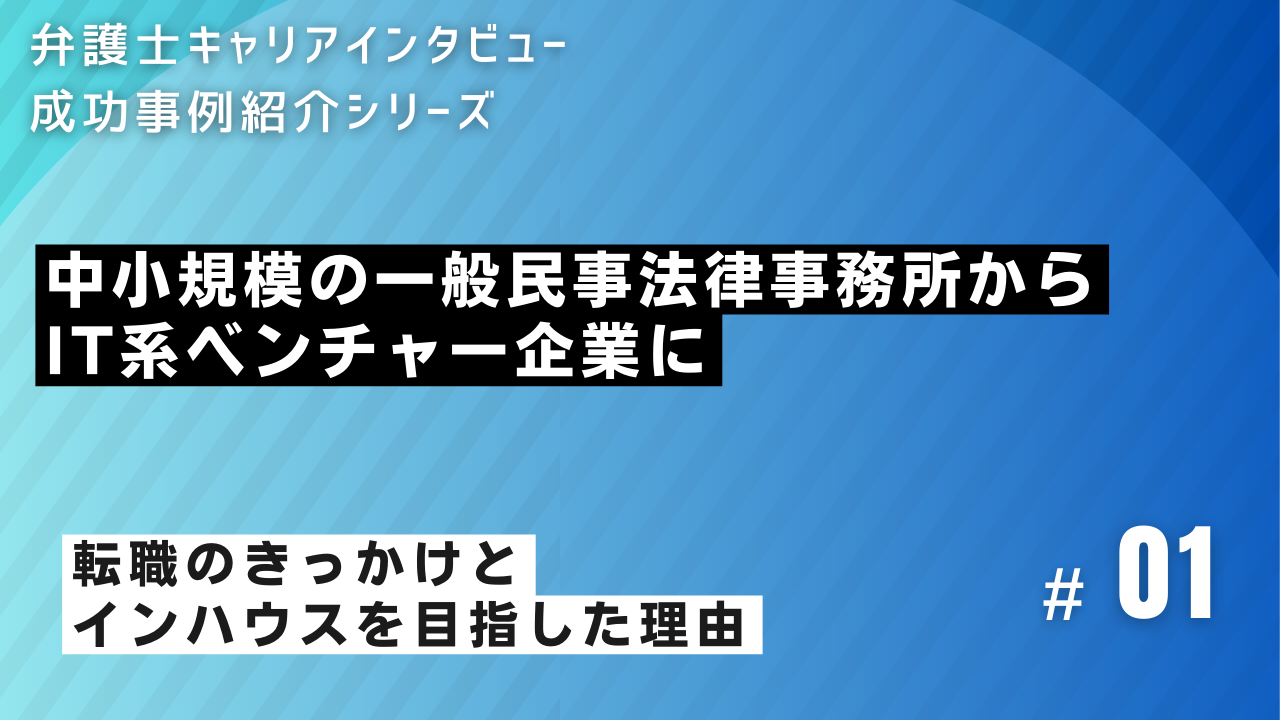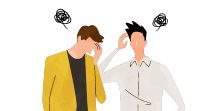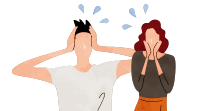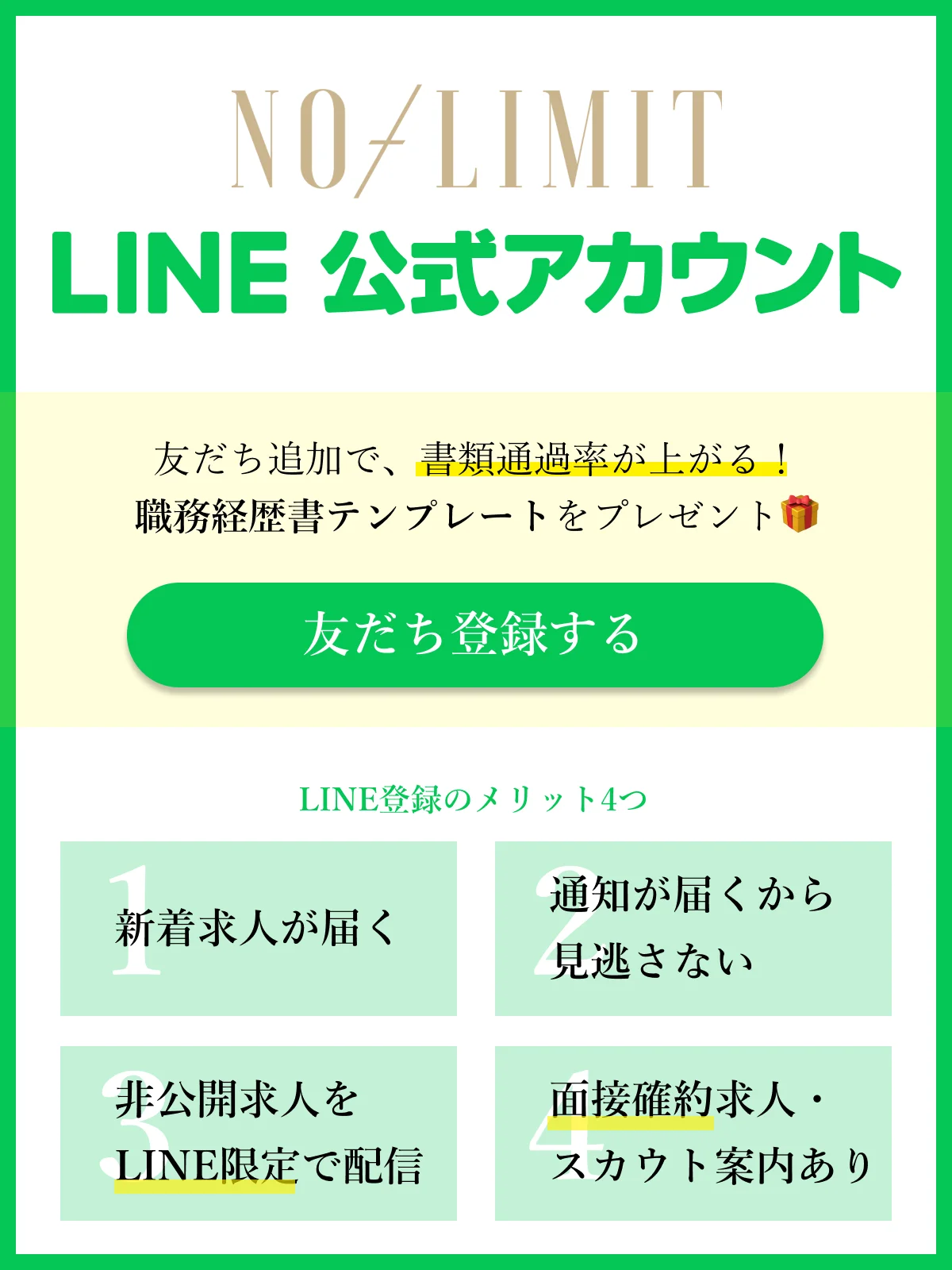弁護士としてのキャリアを積み重ねる中で、中小企業診断士の資格取得を考える弁護士は少なくありません。
法的な知識に加えて経営の視点をもつことで、より広範な業務に対応でき、顧客へ提供できる価値も飛躍的に向上するでしょう。
本記事では、弁護士が中小企業診断士資格を取得する背景やメリット、実際にどのように活用できるのかについて解説します。
No-Limit弁護士にお任せください
無理な転職は勧めません。市場価値の確認や、今の環境に残るべきかの判断から、弁護士特化のプロが徹底サポートします。
今ならあなただけの「キャリア戦略シート」を無料プレゼント中!
プロに相談する(無料)
※履歴書や職務経歴書は不要です。
※相談した事実が公開されることはございません。
目次
中小企業診断士とは
弁護士がキャリアを多角化し、経営の分野にも対応するスキルを身につけるための資格として注目されているのが中小企業診断士です。
この資格は、中小企業の経営課題を解決する専門家として活躍できる国家資格であり、経営コンサルタントとしての知識と実践力を証明できます。
ここでは、中小企業診断士の役割や試験内容、難易度や実務補習について解説します。
中小企業診断士の役割
中小企業診断士は、中小企業の経営に関する幅広い課題を分析し、適切な助言や改善提案をおこなう職業です。
経営コンサルタントとして活動するのに資格は必要ありませんが、中小企業診断士は経営コンサルタントの唯一の国家資格として知られています。
日本の経済を支える中小企業が直面する経営課題は、業績改善や事業承継、DX(デジタルトランスフォーメーション)などです。
この資格をもつことで、経営に関する深い知識と実践的なスキルを活用し、企業の持続的な成長を支援する専門家として活動できます。
試験内容
中小企業診断士の資格取得には、一次試験と二次試験をクリアする必要があります。
一次試験の受験資格はありませんが、一次試験を突破しないと二次試験を受けることができません。
一次試験は中小企業診断士になるために必要な知識を備えているかが問われ、以下の7科目について筆記試験(多肢選択式)で実施されます。
- 経済学・経済政策
- 財務・会計
- 企業経営理論
- 運営管理(オペレーション・マネジメント)
- 経営法務
- 経営情報システム
- 中小企業経営・中小企業政策
なお、弁護士の場合は財務・会計および経営法務科目が免除対象です。
二次試験では、中小企業診断士になるために必要な応用能力があるかを問われます。診断および助言に関する実務の事例4科目について、筆記試験と口述試験が実施されます。
参考:どうしたら中小企業診断士になれるの?|一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会
勉強時間や難易度
中小企業診断士試験の最終合格率は、例年4〜5%で推移しています。
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会によると、令和5年の合格率は一次試験が29.6%(A)、二次試験が18.9%(B)で、最終合格率は約5.6%(A×B)です。
参考:中小企業診断士試験 申込者数・合格率等の推移|一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会
合格率4〜5%の試験は、一般的には極めて難易度が高い試験に該当します。
もっとも、文系最難関の司法試験を突破している弁護士の方にとって、一般的な難易度は必ずしも当てはまりません。
中小企業診断士試験の合格までに必要な勉強時間は1,000時間が目安とされているため、3,000時間〜8,000時間が必要とされる司法試験に比べれば合格しやすい試験と捉えることもできます。
実務補習
中小企業診断士として登録するには、第二次試験に合格後の3年以内に15日以上の実務経験を積むことが必要です。
具体的には、「実務補習を修了する」か「診断実務に従事する」の2つの方法がありますが、多くの方は実務補習を選択します。
実務補習では、6名以内でグループを編成し、指導員の指導を受けながら実際の企業に対して経営診断や助言業務をおこないます。
実務補習のコースは、以下の2つがあります。
- 15日間コース:1企業目8日間、2企業目7日間、計2企業を診断するコース(1回受講)
- 8日間コース:8日間で1企業を診断するコース(2回受講)
なお、5日間で1企業を診断する5日間コース(3回受講)もありますが、令和7年2月実施をもって廃止されます。
参考:令和7年2月実施中小企業診断士実務補習のご案内|一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会
No-Limit弁護士にお任せください
無理な転職は勧めません。市場価値の確認や、今の環境に残るべきかの判断から、弁護士特化のプロが徹底サポートします。
今ならあなただけの「キャリア戦略シート」を無料プレゼント中!
プロに相談する(無料)
※履歴書や職務経歴書は不要です。
※相談した事実が公開されることはございません。
弁護士が中小企業診断士に興味をもつ背景
弁護士として法律の専門性を極める一方で、近年では経営や事業運営に関する知識やスキルへの関心を高める動きが見られます。
中小企業診断士は、経営課題に対する実践的な解決能力を証明する資格であり、法務と経営の視点を融合させるための有効な手段なのです。
経営コンサル分野への関心の高まり
弁護士の業務範囲は、従来の法律相談や紛争解決を超え、企業の経営や事業戦略に深く関わる領域に広がっています。
特に中小企業においては、法務面だけでなく、経営戦略や事業再生に関する助言が求められるケースが少なくありません。
このような背景から、顧客企業の期待に応えるために、経営コンサルタントとしてのスキルを身につけたいと考える弁護士が増えています。
中小企業診断士の資格を取得することで、企業の財務状況や経営戦略を分析し、法的な視点と経営的な視点を組み合わせた助言が可能です。
これにより、企業に対してより包括的なサポートを提供できます。
さらに、自身の業務範囲を拡大させ、新たな専門分野を開拓する契機とすることもできるでしょう。
多様化する企業ニーズに対応するためのスキル拡張
企業活動が複雑化する現代において、法務の枠を超えたスキルの必要性が高まっています。
たとえば、事業承継や企業再生の分野では、法務の専門知識に加えて経営課題への理解が不可欠です。
また、M&Aや事業売却の案件では、法務と経営分析を組み合わせた総合的な支援が求められる場面が多々あります。
こうしたニーズに対応するためには、法律の専門性にとどまらず経営全般に関する知識やスキルを習得することが重要です。
中小企業診断士の資格取得を通じて得られる分析力や提案力は、企業の成長を加速させ、企業との信頼関係をさらに強化します。
企業が直面する課題に対して、多面的な視点でアプローチできる弁護士は、今後の市場においてますます価値が高まるはずです。
No-Limit弁護士にお任せください
無理な転職は勧めません。市場価値の確認や、今の環境に残るべきかの判断から、弁護士特化のプロが徹底サポートします。
今ならあなただけの「キャリア戦略シート」を無料プレゼント中!
プロに相談する(無料)
※履歴書や職務経歴書は不要です。
※相談した事実が公開されることはございません。
弁護士が中小企業診断士資格を取得するメリット
弁護士が中小企業診断士資格を取得することは、業務の可能性を広げ、顧客に対する付加価値を高めるうえで大きなメリットをもたらします。
ここでは3つの観点から、弁護士が中小企業診断士資格を取得するメリットを解説します。
業務範囲の拡大
中小企業診断士の資格を取得することで、法務分野にとどまらず、経営全般にわたるコンサルティングサービスを提供できます。
たとえば、事業承継における経営計画の立案や企業再生案件での収益構造の分析など、法律と経営の両面からの支援を求められる場面が想定可能です。
このような複合的なニーズに対応できることは、弁護士としての市場価値を高めるとともに、これまでリーチできなかった案件にもアプローチできます。
また、法務と経営の両面から顧客企業の課題解決に取り組むことで弁護士としての役割がより広がり、顧客の満足度を向上させることが可能です。
新規顧客の獲得
中小企業診断士の資格を保有している弁護士は、経営支援に関する相談を通じて新たな顧客層を開拓することが可能です。
従来の法律相談に加え、経営課題の解決を目的としたコンサルティングサービスを提供することで、特に中小企業や個人事業主といった経営層との接点を広げることができます。
たとえば、事業承継やM&Aの場面で、法律の視点だけでなく経営面のアドバイスにニーズのある企業はあります。
このような場面で中小企業診断士としての専門知識を活かせることで、企業からの信頼を得るとともに、新たな案件や紹介を通じて顧客基盤を強化できるかもしれません。
経営者視点の強化
経営者視点を強化できる点も大きなメリットです。
法務の専門家として企業を支援する際には、企業のビジネス全体を俯瞰し、経営者の立場に立ったアドバイスを提供することが重要になります。
中小企業診断士の資格取得を通じて経営分析や事業戦略の策定、マーケティング手法などを学ぶことで、企業の課題をより深く理解できるようになるでしょう。
また、このような視点をもつことで、企業が直面している課題の本質を捉え、的確な解決策を提案することが可能です。
No-Limit弁護士にお任せください
無理な転職は勧めません。市場価値の確認や、今の環境に残るべきかの判断から、弁護士特化のプロが徹底サポートします。
今ならあなただけの「キャリア戦略シート」を無料プレゼント中!
プロに相談する(無料)
※履歴書や職務経歴書は不要です。
※相談した事実が公開されることはございません。
弁護士×中小企業診断士の活用が想定できるケース
弁護士と中小企業診断士のスキルを組み合わせることで、単なる法的支援にとどまらず、経営面までを見据えた包括的な支援が可能です。
ここでは、活用が想定できる具体的なケースを解説します。
事業承継における法務・経営支援
事業承継では、法的手続きと経営計画の策定が密接に関わります。
たとえば遺言書の作成や株式の譲渡に関する法的助言だけでなく、後継者の選定や事業の引き継ぎ計画の立案に対応することも必要です。
弁護士は法的リスクを特定し、適切な契約を整備する役割を担います。
一方で中小企業診断士としての視点を活かせば、事業の収益構造や将来的な成長戦略を分析し、法務と経営の両面から企業をサポートできます。
このような統合的な支援は、事業承継をスムーズに進めるために役立つでしょう。
企業再生
企業再生では、法務と経営の観点からの支援が求められる複雑な課題が多く発生します。
特に、企業再生に関する法律や再生手続きの専門的な知識に加え、経営改善のための実行可能な戦略が必要です。
弁護士の立場からは、債権者との交渉や再生計画の法的側面の調整を担当し、中小企業診断士の視点からは、経営改善のための具体的な施策の提案や、財務データの分析を通じた再生計画の策定をおこなうことができます。
これにより、法的再建と経営改善の双方を支援し、企業の持続可能性を高めることが可能です。
M&Aにおける法務と経営分析
M&Aでは、法務と経営の連携が成功の鍵を握ります。
弁護士は、法的リスクの特定や契約書の作成、法的手続きのサポートなど、M&Aプロセス全体を通じた法的支援を提供しますが、M&A後の統合支援も重要です。
契約の整理や雇用契約の見直し、紛争リスクの管理などにも対応します。
一方で中小企業診断士としてのスキルを活かせば、対象企業の収益構造や成長可能性を評価し、M&A案件の経済的な実現性を高めることが可能です。
こうした経営分析を加えることで、単なる法的支援の枠を超え、企業にとって真に価値のあるアドバイスを提供できます。
顧客企業向けセミナーや研修
中小企業診断士として得た知識を基に、顧客企業の経営者や従業員向けにセミナーや研修を実施することも可能です。
たとえば法改正への対応や労務管理に関するテーマに加え、マーケティングや事業戦略といった経営課題についても講義できます。
これにより、顧客企業との信頼関係をより深めることが可能です。
このような活動は、新たな顧客の開拓や既存顧客の満足度向上にも寄与し、弁護士としての市場価値を高められます。
No-Limit弁護士にお任せください
無理な転職は勧めません。市場価値の確認や、今の環境に残るべきかの判断から、弁護士特化のプロが徹底サポートします。
今ならあなただけの「キャリア戦略シート」を無料プレゼント中!
プロに相談する(無料)
※履歴書や職務経歴書は不要です。
※相談した事実が公開されることはございません。
中小企業診断士の取得に向いている弁護士の特徴
中小企業診断士の資格取得は、キャリアの多角化や新たな視点の獲得を目指す弁護士にとって大きな意味をもちます。
ここでは、中小企業診断士の取得を特におすすめしたい弁護士のタイプについて解説します。
弁護士業務に新しい視点やスキルを加えたい弁護士
弁護士としての経験が豊富でも、業務内容が固定化し、視野が狭くなると感じることがあります。
このような状況において、中小企業診断士の資格取得は、新たな視点を加える絶好の機会です。
中小企業診断士の資格取得を通じて経営や財務、マーケティングの知識を体系的に学ぶことで、顧客企業に対する総合的な提案力が向上します。
また、経営者の視点を理解することで、顧客とのコミュニケーションが深まり、実務における説得力も向上するでしょう。
将来的に独立を視野に入れている弁護士
将来的に独立を考えている弁護士にとって、中小企業診断士の資格は強力な武器です。
まず、独立後の収入源を多角化できます。
たとえば、法律業務と中小企業診断士としてのコンサルティング業務を組み合わせることで、事業承継や企業再生といった領域での受任可能な案件を増やすこが可能です。
また、経営の基礎知識を身につけることは、自身の法律事務所の運営を成功させるためにも役立てられます。
企業法務の範囲を拡大させたいインハウスローヤー
企業でインハウスローヤーとして活躍する弁護士にとっても、中小企業診断士の資格は大いに役立つでしょう。
企業法務は、法的リスクの管理にとどまらず、経営戦略や意思決定への貢献が求められることが増えています。
中小企業診断士資格を取得することで、財務分析や市場調査のスキルを獲得し、経営陣との議論においても一層の説得力をもつことが可能です。
さらに法務部門の枠を超えて、経営企画や内部監査など他部門と連携した業務に従事することもできるでしょう。
弁護士×中小企業診断士を活かせるキャリアの相談はNo-Limit弁護士へ!
中小企業診断士の資格は、弁護士としての専門性に経営の視点を加え、キャリアの幅を広げる大きな可能性を秘めています。
ただし、その価値を最大限に活かすためには、資格をどのように業務や転職に結びつけるかが重要です。
そのようなときの転職・キャリア相談は「No-Limit弁護士」にご相談ください。
No-Limit弁護士は、弁護士に特化した転職支援サービスを提供するエージェントで、中小企業診断士資格を活かした新たな役割を見つけるお手伝いするとともに、転職後に活躍できるよう実務に即したアドバイスも提供します。
弁護士としてのキャリアをさらに発展させたい、または新しい視点を加えたいとお考えの方は、お気軽に面談にお申込みください。
No-Limit弁護士にお任せください
無理な転職は勧めません。市場価値の確認や、今の環境に残るべきかの判断から、弁護士特化のプロが徹底サポートします。
今ならあなただけの「キャリア戦略シート」を無料プレゼント中!
プロに相談する(無料)
※履歴書や職務経歴書は不要です。
※相談した事実が公開されることはございません。
まとめ
弁護士が中小企業診断士資格を取得することで、法的知識に経営の視点を加え、業務の幅を広げることができます。
事業承継や企業再生、M&Aなど多様な案件で活躍できるチャンスが増え、さらなるキャリアのステップアップが期待できるでしょう。
今後のキャリア形成において、ダブルライセンスは強力な武器となるはずです。
自分の市場価値、入所時に聞いた条件との乖離、ワークライフバランスへの不安。
弁護士という多忙な職業だからこそ、一人で抱え込みがちな悩みに、私たちは徹底的に伴走します。
【No-Limit弁護士】は、単なる求人紹介ではなく「失敗しない転職」を追求する弁護士特化の転職エージェントです。
- 1. ムリな転職は勧めません
- お話を伺った結果「今は動かないほうが良い」とアドバイスすることも珍しくありません。
- 2. 徹底した透明性を担保
- 良い面だけでなく、その職場の「マイナス面」も事前にお伝えし、転職後の後悔をゼロにします。
- 3. 多忙なあなたをサポート
- 書類作成から日程調整、内定後のフォローまで、すべての工程を私たちが代行いたします。
- 4. 定着率98.6%(※)のマッチング精度
- 他では知り得ないリアルな職場情報が充実。求人票の「裏側」まで包み隠さず共有するからこそ、ミスマッチのない転職をお約束します。
- 5. あなただけのキャリアシートをプレゼント
- 面談を実施した方全員に、プロのアドバイザーがあなたの経歴と強みを分析し、今後の可能性をまとめた「個別キャリア戦略シート」を無料で作成・進呈いたします。
- 履歴書・職務経歴書は不要です。
- オンライン(Google Meet)やお電話で、15分から気軽にご相談いただけます。
- 相談や転職活動の事実が、外部に漏れることは一切ございません。