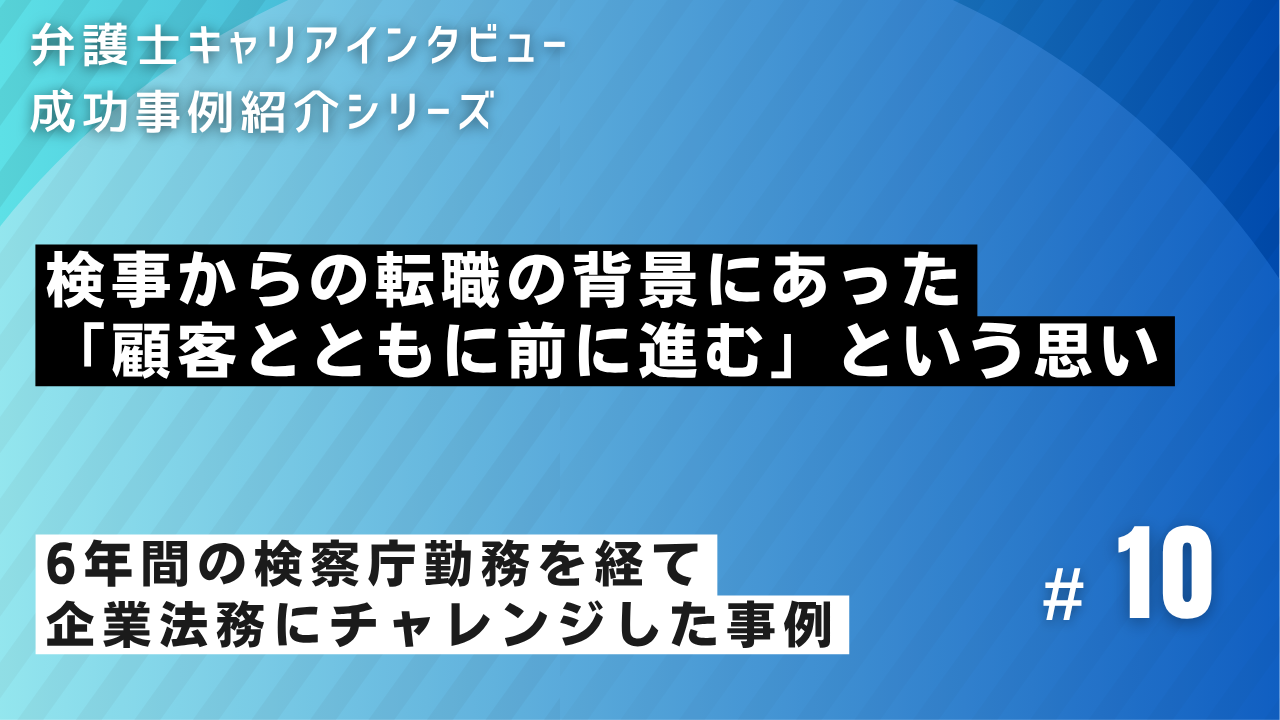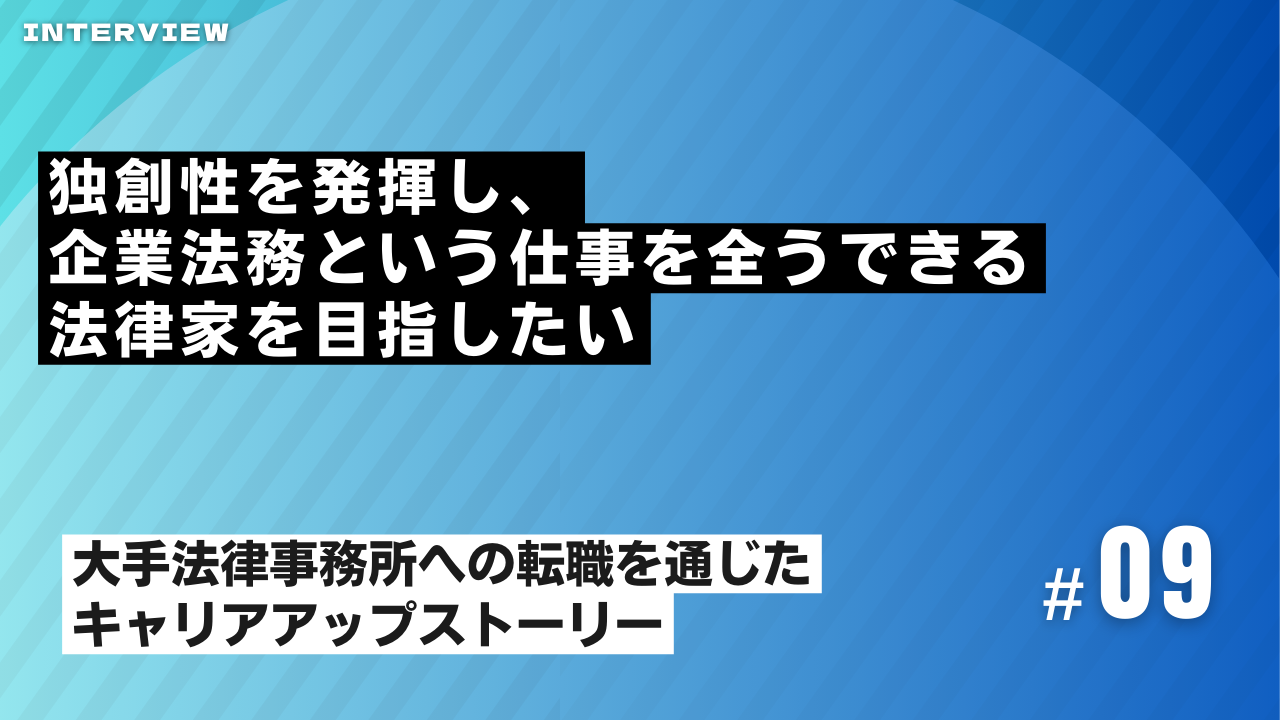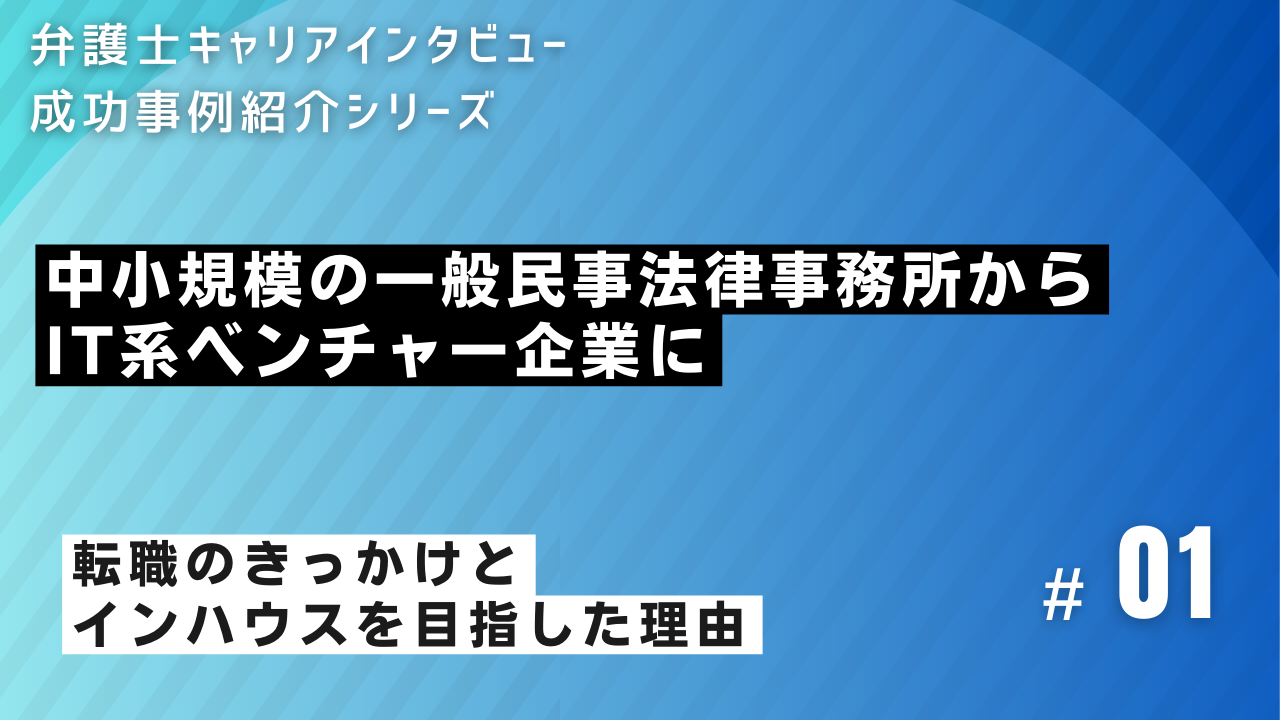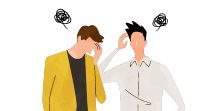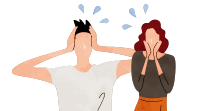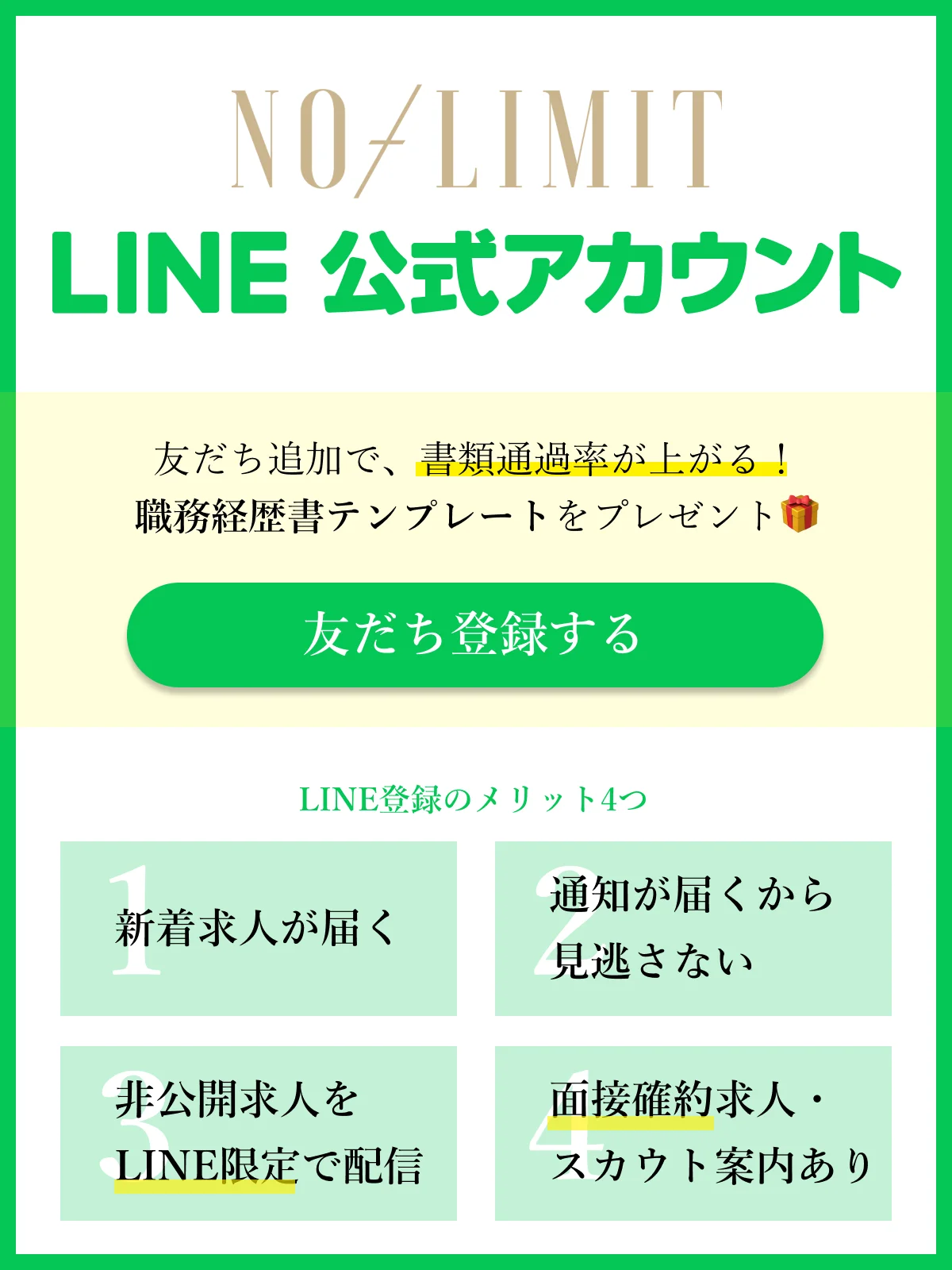弁護士業界における副業は、従来の法律実務に加えて新たな収入源や事業機会を創出する重要な戦略として注目を集めており、法律事務所の激しい競争環境、事務所給与の伸び悩み、そして多様化するクライアントニーズに対応するため、多くの弁護士が副業や複業という選択肢を検討しています。
そして、近年の弁護士業界では、単一の収入源に依存するリスクが高まっており、キャリアの安定性とスキルの多様化を図る観点から副業への関心が急速に高まっている状況です。
本記事では、弁護士がこれからの時代においてマルチキャリアという観点から、どのように副業戦略をとるべきかを解説していきます。
目次
弁護士業界における副業とは?
弁護士業界において「副業」はどのように位置づけられ、どのように認識されているでしょうか。
弁護士業務以外の事業チャネル・収入源の獲得
弁護士が副業を検討する最大の理由は、法律業務以外での事業チャネルや収入源の獲得です。
従来の弁護士業務は時間単価に依存する収益モデルが中心でしたが、副業により異なる収益構造を構築することで、より安定した経済基盤を築くことが可能になります。
具体的な事業チャネルとしては、オンライン教育事業、コンテンツ制作事業、投資事業、コンサルティング事業などです。
これらの事業は、弁護士の専門知識を活かしながらも、従来の労働集約的な働き方から脱却し、スケーラブルな収益モデルを実現できるでしょう。
特に注目されているのは、デジタル化の進展により可能になった遠隔でのサービス提供です。
地方在住の弁護士でも、オンラインプラットフォームを活用することで全国規模での事業展開が可能になり、地域的制約を超えた収入機会を獲得できます。
また、弁護士の専門性を活かした事業として、法務関連のSaaSサービス開発、リーガルテック企業への投資やアドバイザー業務、企業の社外取締役就任なども増加傾向です。
これらの事業は、弁護士の法的専門知識を直接的に活用でき、高い付加価値を創出できる分野として注目されています。
弁護士業務自体が「副業」になるケースも
現代の働き方の多様化に伴い、弁護士業務自体が副業として位置づけられるケースも増加しています。
これは特に、他業界で主たる事業を営みながら、弁護士資格を活かして法律業務を行う場合に見られる現象です。
たとえば、企業内弁護士が自社以外で法人クライアントを獲得して法務顧問を担当したり、一般民事の案件に対応して収益を得ることが考えられます。
あるいは、中小企業診断士など隣接資格を活かしてコンサルティング会社を主業とする弁護士が、クライアント企業の法的課題解決を付加サービスとして提供する場合も、弁護士業務が副業的な位置づけです。
このような働き方は、弁護士資格の活用方法に新たな可能性をもたらしています。
従来の法律事務所での勤務や独立開業以外にも、多様なキャリアパスが存在することを示しており、特に若手弁護士にとっては魅力的な選択肢となるでしょう。
さらに、フリーランス弁護士として複数のプロジェクトに参画し、それぞれを並行して進める働き方も普及しています。
この場合、どの業務を主業とし、どれを副業とするかの境界線は曖昧になり、むしろポートフォリオ型の働き方として捉えることが適切です。
弁護士の「事業ポートフォリオ」という発想
このポートフォリオという考え方は、ビジネスマンにとっては一般的ですが、現代の弁護士にとって重要な概念が「事業ポートフォリオ」の発想です。
これは、複数の事業や収入源を組み合わせることで、リスク分散と収益最大化を図るアプローチになり、弁護士のキャリア戦略として注目されています。
事業ポートフォリオのメリットは、景気変動や業界の構造変化に対する耐性を高められることです。
たとえば、法律業務が低調な時期でも、他の事業が好調であれば全体の収益を維持できます。また、異なる事業間でのシナジー効果により、単体では得られない価値創出も期待できます。
また、成功する事業ポートフォリオの特徴は、各事業間の相関性が低いことです。つまり、一つの事業が不調でも他の事業への影響が限定的であることが重要。
弁護士の場合、法律業務、教育事業、投資事業は比較的相関性が低く、効果的なリスク分散が可能です。
弁護士のよくある副業5選
弁護士が取り組む副業には様々な選択肢がありますが、中でも特に人気が高く、成功事例の多い副業を5つ紹介します。
これらの副業は、弁護士の専門知識を直接的に活用でき、比較的参入しやすいことが特徴です。
司法試験予備校講師
司法試験予備校講師は、弁護士の副業として最も伝統的で人気の高い選択肢の一つです。
自身の受験経験と実務経験を組み合わせた指導ができるため、受験生からの信頼も厚く、安定した収入源となります。
講師業務の収入は、大手予備校の場合、1コマ(90分)あたり8,000円から15,000円程度が相場です。
人気講師になると1コマ20,000円以上の報酬を得ることも可能です。年間を通じて継続的な収入が見込めるため、月収20万円から50万円の副収入を得ている弁護士も存在します。
近年はオンライン講義の普及により、地方在住の弁護士でも大手予備校の講師として活動できるようになりました。
また、個人でオンライン講座を開設し、より高い収益率を実現する弁護士も増加しています。
講師業務のメリットは、教える過程で自身の知識も整理・深化されることです。
また、多くの受験生との接触により、法曹界の将来を担う人材とのネットワークも構築できますが、その一方で、講義準備に相当な時間を要するため、時間管理が重要な課題となります。
他士業の資格業務
弁護士が他士業の資格を取得し、その業務を副業として行うケースも増加しています。
弁護士資格により一定の他士業資格が付与される場合もあり、比較的参入しやすい副業分野です。
特に人気が高いのは税理士業務です。弁護士は税理士法第3条により税理士資格となりうる資格があり、一定の要件を満たすことにより税務業務を行うことができます。
企業法務を扱う弁護士にとって、税務知識は重要であり、クライアントへのワンストップサービス提供も可能です。
行政書士業務も弁護士が取り組みやすい分野です。許認可申請、契約書作成、相続手続きなど、法律知識を活かせる業務が多く、個人クライアントとの接点も増やせます。
社会保険労務士業務は、労働法に詳しい弁護士にとって有力な選択肢になり、企業の人事労務コンサルティング、就業規則作成、労働紛争の予防的対応など、弁護士業務との親和性も高い分野です。
これらの他士業業務の収入は、業務内容や顧客規模により大きく異なりますが、月収10万円から100万円以上の幅があります。
重要なのは、本業の弁護士業務との相乗効果を狙い、総合的なサービス価値を高めることです。
法律系Webライター
デジタル化の進展により、法律系Webライターとしての需要が急速に拡大しています。
企業のオウンドメディア、法律情報サイト、一般向けの法律解説コンテンツなど、様々な媒体で弁護士の専門知識を活かした記事執筆の機会は幅広いです。
法律系ライティングの報酬は、記事の長さ、専門性、媒体により大きく異なります。
一般的な法律解説記事の場合、1記事あたり5,000円から30,000円程度が相場。高度な専門知識を要する企業向けコンテンツでは、1記事50,000円以上の報酬を得ることも可能です。
継続的な執筆契約を獲得できれば、月収20万円から80万円程度の安定した副収入源となります。
また、執筆実績を積むことで単価向上や大型案件の獲得も期待できるでしょう。
ライティング業務のメリットは、時間と場所の制約が少ないことです。
隙間時間を活用した執筆が可能で、本業との両立もしやすい副業。さらに、執筆を通じて法律知識の整理・深化が図れ、本業にも好影響をもたらします。
成功するためには、読者のニーズを理解し、専門的な内容を分かりやすく伝える文章力が重要です。また、SEOの知識があると、より価値の高いコンテンツ制作が可能になります。
不動産投資
不動産投資は、弁護士の副業として長期的な資産形成と安定収入の確保を目指せる選択肢です。
法律知識を活かして契約関係のリスクを適切に評価できるため、一般投資家よりも有利な条件で投資を行える可能性があります。
不動産投資の収益は、賃料収入(インカムゲイン)と売却益(キャピタルゲイン)の両方が期待できます。
弁護士が不動産投資で有利な点は、不動産売買契約、賃貸借契約、管理委託契約などの法的リスクを的確に評価できることです。また、トラブル発生時の対応能力も高く、投資リスクの軽減が図れるでしょう。
近年は、不動産投資型クラウドファンディングやREIT(不動産投資信託)など、少額から始められる投資手法も普及しています。これらは管理の手間が少なく、多忙な弁護士にも適した投資方法です。
ただし、不動産投資にはまとまった初期資金が必要で、市場変動リスクや空室リスクなども存在します。十分な知識習得と慎重な投資判断が成功の鍵となります。
出版、執筆、講演
出版・執筆・講演活動は、弁護士の専門知識を広く社会に発信し、同時に収入も得られる魅力的な副業です。
個人ブランドの構築にも大きく貢献し、長期的なキャリア形成の観点からも価値の高い活動になるでしょう。
書籍出版の収入は、出版形態により大きく異なります。
商業出版の場合、印税率は一般的に8%から12%程度で、定価1,500円の書籍が10,000部売れれば120万円から180万円の収入です。
電子書籍の自費出版では印税率が35%から70%と高い一方、販売部数は限定的になる傾向があります。
講演活動の報酬は、講演者の知名度、講演内容の専門性、主催者の規模により大きく変動する傾向です。
企業向けセミナーでは1回30万円から100万円、一般向け講演では5万円から30万円程度が相場。人気講師になると年間100回以上の講演を行い、数千万円の収入を得るケースもあります。
近年はオンライン講演の機会も増加しており、移動時間の削減により効率的な活動が可能なうえに、録画配信により一度の講演で継続的な収入を得ることも可能です。
加えて、SNSやブログを活用した情報発信により認知度を高め、講演や執筆の機会創出につなげることが重要になります。
弁護士の副業トレンド3選
弁護士業界でも新しい技術やビジネスモデルの普及により、従来にはなかった新しい形の副業が登場しています。
これらのトレンド副業は、時代の変化に敏感な弁護士にとって新たな収入機会とキャリア展開の可能性をみいだせるでしょう。
法律系YouTuber
YouTube等の動画プラットフォームを活用した法律系コンテンツ配信が、弁護士の新しい副業として急速に普及しています。
法律知識を分かりやすく解説する動画は視聴者からの需要が高く、収益化の可能性も大きい分野です。
法律系YouTuberの収入源は多岐にわたり、YouTube広告収入のみならず、企業からのスポンサー案件、法律相談への誘導、オンライン講座販売、書籍販売促進など、複数の収益チャネルを構築できます。
特に、時事問題と法律を組み合わせたコンテンツや、身近な法律問題の解説動画は高い視聴数を獲得する傾向です。
そして、動画制作のメリットは、一度作成したコンテンツが継続的に視聴され、長期間にわたって収益を生み出せるうえに、動画を通じて多くの人に法律知識を提供することで、社会貢献の側面も持てることにあります。
ただし、継続的なコンテンツ制作には相当な時間と労力が必要です。また、炎上リスクや法的責任の問題もあるため、発信内容には細心の注意が必要です。
AIエンジニア
弁護士がプログラミングスキルを習得し、AIエンジニアとして活動するケースが増加しており、新しいキャリアパスとして注目されています。
リーガルテック分野でのAI開発は、契約書レビュー自動化、判例検索システム、法律相談チャットボット、コンプライアンスチェックツールなど多岐です。
これらの開発に法律知識を持つエンジニアが参画することで、より実用的で精度の高いシステム構築が可能になります。
AIエンジニアとしての収入は、関わるプロジェクトの規模や専門性により大きく異なり、フリーランスとしてリーガルテック企業の開発に参画する場合、月収50万円から200万円程度が相場です。自社でAIサービスを開発・運営する場合は、さらに高い収益も期待できるでしょう。
弁護士がAIエンジニアとして成功するメリットは、法律とITの両方の専門知識を持つ希少性の高い人材になれることです。
この組み合わせにより、他の専門家では代替困難な価値を提供できます。
スキル習得には相当な時間投資が必要ですが、将来的な法律業界のデジタル化を考えると、長期的な競争優位性を構築できる投資と言えるでしょう。
VC、エンジェル投資
ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家としての活動も、弁護士の新しい副業形態として注目されています。
法務の専門知識を活かした投資判断や、投資先企業への法的支援を組み合わせることで、従来の投資家とは異なる価値を提供できるでしょう。
弁護士投資家の強みは、投資契約の法的リスクを適切に評価できることです。株主間契約、投資契約、労働契約などの法的条項を的確に査定し、投資リスクの軽減を図れます。
投資収益は、投資先企業の成長により大きく左右され、成功した場合のリターンは非常に大きく、投資額の10倍から100倍以上になることも。
その一方で、投資失敗のリスクも高く、投資元本を失う可能性もあります。
こうした投資活動を通じて、スタートアップ企業やベンチャー業界のネットワークを構築できることも大きなメリットです。
これにより、新たなビジネス機会や法務案件の獲得につながる可能性もあります。
弁護士業務以外を「副業」とする場合の手続きは?
弁護士が法律業務以外の事業を副業として行う場合、弁護士法に基づく適切な手続きを行う必要があります。
これらの手続きを怠ると、弁護士会からの指導や処分の対象となる可能性があるため、事前の確認と適切な対応が重要です。
弁護士法30条に基づく届出が必要
弁護士法第30条は、弁護士が他の事業を営む場合の届出義務を規定しています。
同条では「弁護士は、その品位を保持し、弁護士の使命及び職責にふさわしくない業務を行ってはならない」とされており、副業を行う場合は所属弁護士会への届出が必要です。
届出書には、副業の内容、実施期間、収入見込み、本業への影響などを詳細に記載します。
弁護士会は届出内容を審査し、弁護士の品位や職責に問題がないかを、届出から1か月から3か月程度の期間で判断します。
届出手続きの流れは以下の通りです。
①所属弁護士会の事務局に届出書の書式を確認し、必要書類を準備。
②副業の具体的な内容、実施方法、収入計画などを詳細に記載した届出書を作成
③弁護士会に届出書を提出して、審査結果を待ち
届出が承認された場合でも、副業の内容や規模に変更があった場合は、改めて変更届出が必要で、副業を終了する場合も終了届出を行う必要があります。
重要なのは、届出義務は副業開始前に行う必要があることです。
事後的な届出は弁護士会からの指導の対象となる可能性があるため、必ず事前の手続きを行うことが重要になります。
対象となるケース
弁護士法30条の届出が必要となるケースは、法律業務以外の事業を継続的・反復的に行う場合です。
具体的には、以下のような活動が対象となります。
営利目的の事業活動
会社経営、店舗運営、不動産賃貸業、投資業務などが含まれます。また、非営利活動であっても、継続的に報酬を得る活動は届出の対象となる場合があります。
教育関連の活動
大学や専門学校での非常勤講師、予備校講師、セミナー講師などが対象。ただし、単発の講演や短期間の研修は除外される場合があります。
執筆・出版活動
継続的な執筆業務、出版社との専属契約、定期的な雑誌連載などが対象。一方、単発の書籍出版や論文執筆は通常対象外です。
投資活動
ファンド運営、投資顧問業務、不動産投資業などが対象。個人的な株式投資や不動産投資は通常対象外ですが、規模や頻度により判断が分かれる場合があります。
その他
コンサルティング業務、IT関連事業、芸能活動、スポーツ選手活動なども、継続性と収益性があれば届出の対象となります。
判断に迷う場合は、所属弁護士会に事前相談することをお勧めします。弁護士会では、具体的な活動内容に基づいて届出の要否を判断してくれます。
弁護士の形態別 副業時の注意点
弁護士の勤務形態により、副業を行う際の注意点や制約が異なります。
所属する組織の規則や利益相反の可能性を十分に検討し、適切な対応を取ることが重要です。
事務所勤務弁護士
法律事務所に勤務する弁護士が副業を行う場合、最も重要な注意点は雇用契約や就業規則における副業規定の確認です。
多くの法律事務所では、副業に関する規定が設けられており、事前許可が必要な場合が一般的になります。
利益相反の回避は特に重要な課題です。
副業で扱う案件が所属事務所のクライアントと利害対立する可能性がある場合、深刻な問題となります。
たとえば、企業法務を扱う事務所に勤務しながら、競合他社の法務コンサルティングを行うことは利益相反に該当する可能性があります。
守秘義務の遵守も重要な注意点です。
所属事務所で得た情報や知識を副業で利用することは、守秘義務違反となる可能性があります。
副業での発言や執筆内容について、所属事務所の機密情報が含まれていないか常に注意を払いましょう。
時間管理も重要な課題です。
副業により本業の業務に支障をきたすことは、雇用契約違反となる可能性があります。副業に充てる時間は、勤務時間外に限定し、本業のパフォーマンス維持に努めましょう。
所属事務所への報告義務も忘れてはいけません。
副業の内容、収入、時間配分などについて、定期的に上司や事務所に報告することが求められる場合があります。
企業内弁護士
企業内弁護士(インハウスローヤー)の場合、一般的な会社員と同様の副業規制が適用されることが多く、勤務先企業の就業規則や社内規定の確認が必要です。
最重要の注意点は、副業が勤務先企業の事業と競合しないことにあります。
たとえば、IT企業の企業内弁護士が同業他社の法務コンサルティングを行うことは明確な利益相反です。
副業選択時は、勤務先企業の事業領域との関係を慎重に検討する必要があります。
そして、勤務時間中の副業活動は厳格に禁止です。
企業内弁護士は会社の従業員として労働契約を結んでおり、勤務時間中は会社業務に専念する義務があります。
会社の資源や情報の私的利用も禁止です。
会社のパソコン、プリンター、会議室などを副業に使用することはできません。また、会社で得た情報やノウハウを副業で活用することも制限されます。
副業申請・承認手続きは多くの企業で義務付けられています。
副業開始前に人事部や上司への申請を行い、承認が必要です。承認後も、副業の状況について定期的な報告が求められる場合があります。
社外活動に寛容な企業文化の場合でも、副業内容について慎重な判断が必要です。企業のブランドイメージや評判に影響を与える可能性のある副業は避けましょう。
自治体所属弁護士
地方自治体に所属する弁護士の場合、地方公務員法の適用を受けるため、副業に関する制約は厳格です。
地方公務員法第38条により、営利企業等の従事制限が規定されています。
自営業、会社役員、営利企業の従業員など、営利を目的とする副業は原則として禁止されています。この制限により、多くの一般的な副業が実施困難です。
非営利活動であっても、継続的に報酬を得る活動については事前許可が必要です。大学での講義、執筆活動、講演活動などが該当する場合があります。
公務員としての中立性・公正性の確保も重要な制約です。特定の政治的立場や営利企業の利益を代弁するような活動は制限されています。
また、職務上知り得た情報を副業で活用することも厳格に禁止です。
弁護士が副業・複業をするメリット
弁護士が副業や複業に取り組むことで得られるメリットは多岐にわたります。
これらのメリットを理解することで、副業への取り組み方針や目標設定がより明確になるでしょう。
顧客獲得の拡大
副業を通じた顧客獲得の拡大は、弁護士にとって最も直接的なメリットの一つです。
従来の法律業務だけでは接点のなかった新しい顧客層にアプローチできることで、クライアントベースの大幅な拡大が可能になります。
異業種の人脈獲得により、これまでアクセスできなかった業界や企業からの法務案件獲得が可能になるかもしれません。
収益チャネルの補完になる
副業による収益チャネルの多様化は、弁護士の経済的安定性を大幅に向上させます。
法律業務単体では達成困難な収益の安定化と拡大が可能になります。
経験や知見の相互還元
副業と本業の間での経験や知見の相互還元は、弁護士のスキル向上と専門性深化に大きく貢献します。
この相乗効果により、単独の業務では得られない価値創出が可能です。
弁護士が副業を考える際の3つの視点
弁護士が副業を成功させるためには、戦略的な視点での選択と実行が重要です。
以下の3つの視点を総合的に検討することで、最適な副業選択と効果的な運営が可能になります。
異質性
副業選択における異質性の視点は、本業との差別化と独自性の確保を重視するアプローチです。
既存の法律業務とは異なる特徴を持つ副業を選択することで、リスク分散と新たな価値創出を同時に実現できます。
業界の異質性を追求する場合、法律業界以外の分野での副業が有効です。
たとえば、エンターテインメント業界、スポーツ業界、ファッション業界など、従来の法律業務では接点の少ない分野への進出により、新しい市場機会を発見できるでしょう。
レバレッジ効果
弁護士業務以外での限られた時間と労力を最大限活用し、効率的な収益創出を実現することはビジネスにおける基本です。
弁護士の副業において、このレバレッジ効果を意識することで、投入リソースに対する収益の最大化が可能になります。
時間のレバレッジ効果を実現する方法として、一度作成したコンテンツを継続的に活用する戦略があります。
オンライン講座、電子書籍、動画コンテンツなどは、初期制作時の労力は大きいものの、継続的な販売により長期間の収益創出が可能です。
シナジー効果
副業と本業の相互作用により、単体では実現できない価値創出を図ることで、副業が本業を強化し、本業が副業を促進する好循環を創出できるでしょう。
このシナジーは、いくつかのカテゴリーが考えられます。
スキルシナジー
副業で習得したスキルが本業のサービス品質向上に貢献します。
たとえば、マーケティングの副業で得た顧客分析スキルを、法律事務所のクライアント開拓戦略に活用することで、営業効率の向上が期待できます。
顧客シナジー
副業の顧客が本業のクライアントになったり、その逆の流れが生まれたりします。
オンライン講座の受講生が法律相談を依頼したり、既存クライアントが副業サービスを利用したりすることで、顧客生涯価値の最大化が可能になるでしょう。
ネットワークシナジー
副業で構築した人脈が本業の案件獲得に貢献します。
また、本業の人脈が副業の事業拡大をサポートすることもあり、相互の人的資源が有効活用されるでしょう。
ブランドシナジー
複数の事業領域での活動が個人ブランドの多面性と専門性を同時に向上させます。
法律の専門家でありながら、投資家、教育者、コンテンツクリエイターとしても認知されることで、より強固なブランドポジションを構築できるでしょう。
リスクシナジー
副業が本業のリスクヘッジ機能を果たすこともあります。
法律業務の低調期に副業収入でカバーし、副業の不調時には本業で安定性を確保するという相互補完関係が構築が可能です。
まとめ
弁護士の副業は、従来の法律業務のみに依存するキャリアから脱却し、安定した経済基盤を構築する重要な戦略です。
成功には、法律知識を活かせる分野選択、利益相反の適切な管理、長期的なキャリア形成の視点が必要になります。
そして、副業は単なる収入補完ではなく、専門性拡大とキャリア多様化への投資として位置づけることが重要。
AI技術やリーガルテックの発展により変化する業界で競争力を維持するため、副業を通じた新スキル習得が不可欠です。
異質性、レバレッジ効果、シナジー効果の3つの視点で戦略的に選択し、継続的な学習と柔軟な適応能力により、持続可能なキャリア構築を実現できるでしょう。