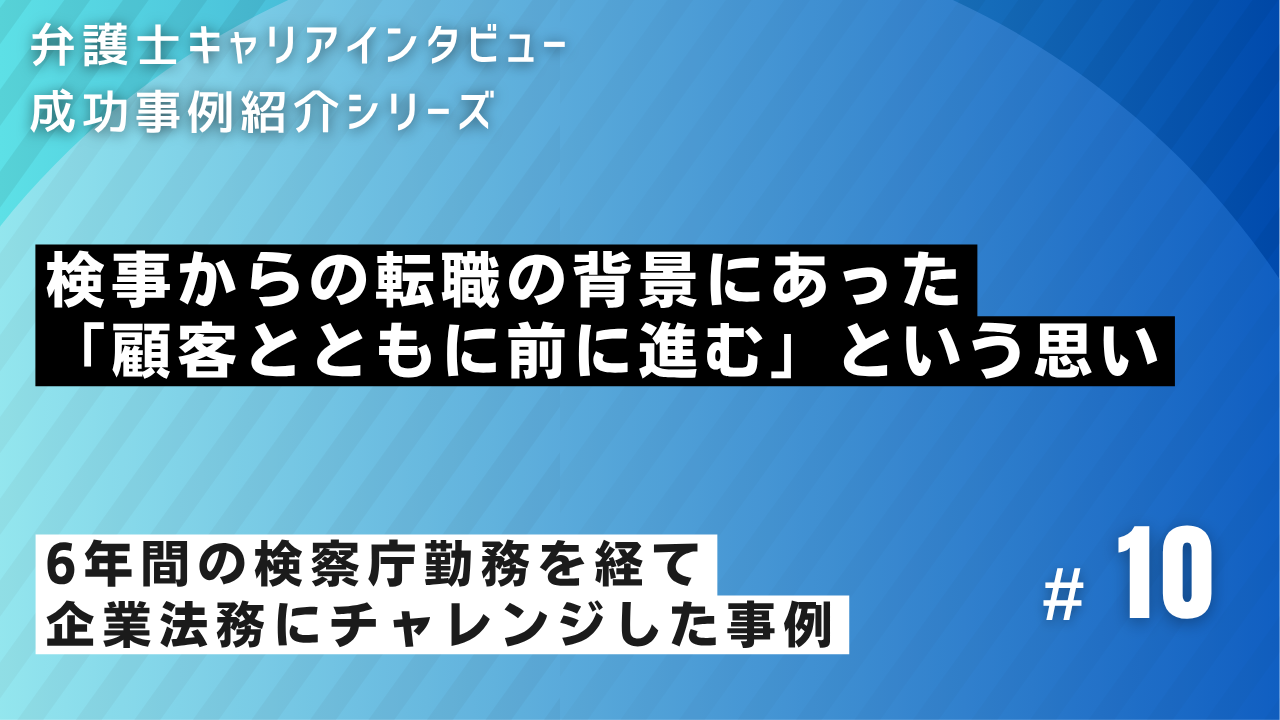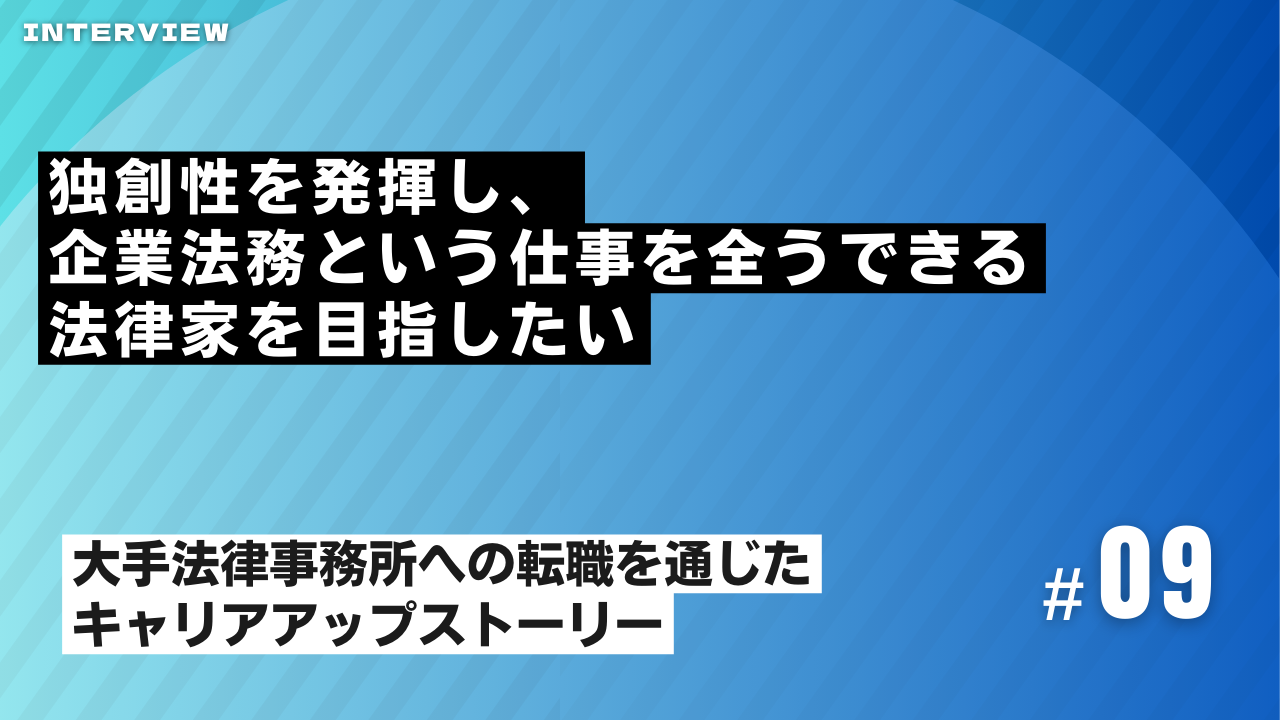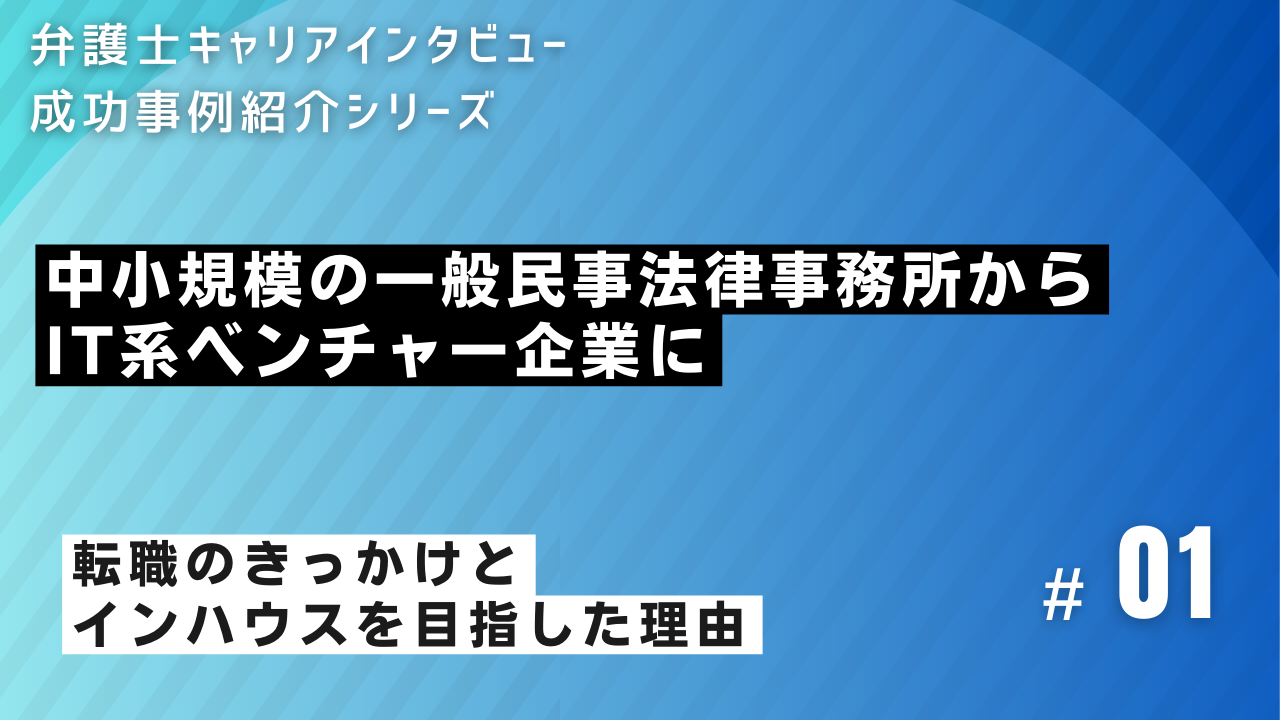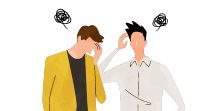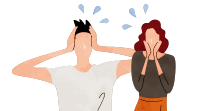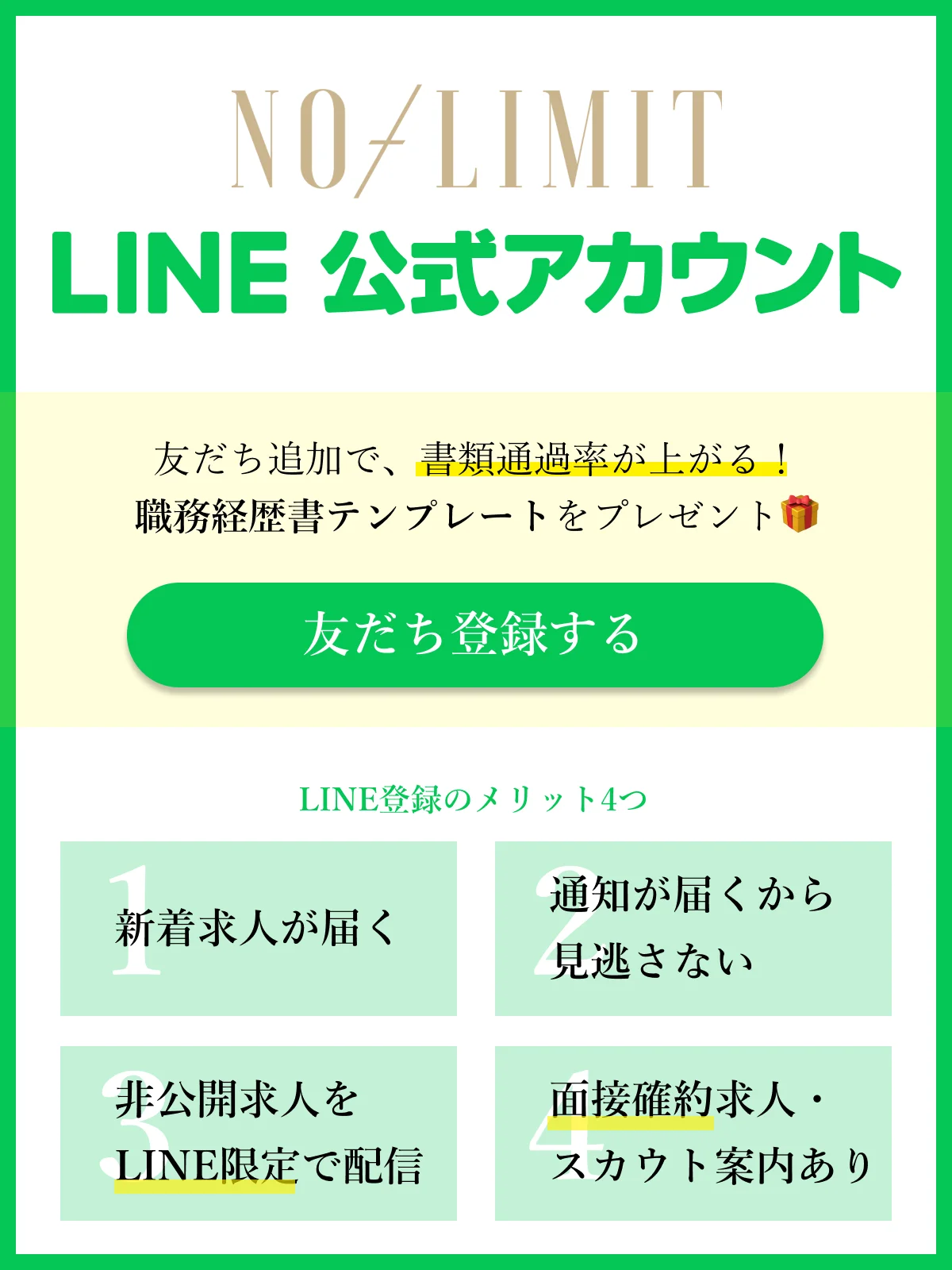近年、弁護士のキャリアパスが多様化する中で、任期付公務員としての出向が注目を集めています。
従来の法律事務所での勤務とは異なる経験を積みながら、社会貢献を実現できる魅力的な制度として多くの弁護士が関心を寄せています。
本記事では、弁護士の任期付公務員制度について詳しく解説し、具体的な募集事例やメリット、キャリアパスについてご紹介します。
目次
弁護士の任期付公務員とは
まず、任期付公務員とは何か、弁護士が任期付公務員として採用されるニーズはどういった点にあるのかなど背景や基本的なポイントをみていきましょう。
制度の概要
任期付公務員制度は、専門的な知識や技能を有する民間人材を一定期間公務に活用する制度です。
平成12年に一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(いわゆる任期付職員法)が制定されて以来、各省庁や地方自治体において専門性の高い人材の確保手段として活用されています。
弁護士の場合、法律の専門知識と実務経験を活かして、各省庁や地方自治体の政策立案、法務業務、訴訟対応、規制執行などに従事することになります。
通常の公務員採用試験を経ることなく、専門性を評価されて採用される点が大きな特徴です。
任期は概ね1年から5年程度で設定され、業務内容や省庁によって異なりますが、多くの場合は2年程度の任期で一定の期限のもと更新延長の可能性も用意されています。
原則として、常勤職員として採用されるため、職務専念義務が課され他の法律業務との兼業は制限されます。
弁護士のニーズの所在
現代社会において、行政機関が直面する課題はますます複雑化・専門化しています。
国際通商問題、金融規制、消費者保護、独占禁止法の執行、企業法制の整備など、高度な法律知識と実務経験を要する分野が拡大し続けています。
一方で、従来の公務員採用システムでは、こうした専門分野に精通した人材を迅速に確保することが困難でした。
特に、民間での実務経験を豊富に持つ弁護士の知見は、行政機関にとって極めて価値の高いものとなっています。
このようなギャップを埋めるため、各省庁では任期付公務員制度を活用して、弁護士の専門性を行政サービスの向上に活かそうとする動きが活発化しています。
企業内弁護士が一般化していることからも、組織内弁護士の一形態として、任期付公務員が浸透しているのです。
さらに、デジタル化の進展や国際化の加速により、新たな法的課題への対応も求められており、弁護士のニーズはさらに高まることが予想されます。
多様な弁護士のキャリアの1つ
弁護士のキャリアパスは従来、法律事務所での勤務、企業内弁護士(インハウスロイヤー)、独立開業が主な選択肢でした。
しかし、近年はこれらに加えて、任期付公務員としての出向が新たな選択肢として確立されつつあります。
この制度は、特に以下のような弁護士にとって魅力的な選択肢でしょう。
まず、民間での実務経験を積んだ後、より社会的影響力の大きい仕事に携わりたいと考える弁護士です。
また、特定の専門分野を深く追求したい弁護士にとっても、その分野を所管する省庁での経験は貴重な機会となるでしょう。
そして、一定期間の区切りごとに人材の流動性を確保することができる行政側のメリットと、特定の分野について知見を深めたいというニーズもあることから双方のニーズが合致している領域ともいえます。
さらに、将来的に政策立案や行政に関わる仕事に従事したいと考える弁護士にとって、任期付公務員の経験は重要なステップとなり得ます。
ワークライフバランスを重視し、安定した環境で専門性を活かしたい弁護士にとっても、公務員としての働き方は魅力的な選択肢です。
No-Limit弁護士にお任せください
無理な転職は勧めません。市場価値の確認や、今の環境に残るべきかの判断から、弁護士特化のプロが徹底サポートします。
今ならあなただけの「キャリア戦略シート」を無料プレゼント中!
プロに相談する(無料)
※履歴書や職務経歴書は不要です。
※相談した事実が公開されることはございません。
弁護士の任期付公務員を募集している省庁等の6つの例
早速、弁護士有資格者を任期付公務員として募集している省庁の例をいくつかご紹介していきます。
経済産業省
経済産業省では、複数の部署で任期付職員として弁護士を募集しています。
現在募集中の案件として、電力・ガス取引監視等委員会事務局の各部署(ネットワーク事業監視課、総合監査室、取引監視課、取引制度企画室)、中小企業庁事業環境部金融課、経済産業政策局産業組織課、商務情報政策局商品市場整備室、中小企業庁訟務・債権管理室などがあります。
経済産業省の任期付職員募集は、エネルギー政策、産業政策、中小企業支援など多岐にわたる分野で展開されており、それぞれの専門分野で弁護士の法的知見が求められています。
応募資格としては、弁護士資格を有することが必須条件となり、実務経験年数については募集部署により異なりますが、一般的に2年以上から3年以上の実務経験が求められることが多くなっています。
特に、担当する業務分野に関連する法務経験(企業法務、行政法務、訴訟実務等)があることが望ましいとされていますが、必ずしも特定分野の経験を必須としない場合もあります。
また、日本国籍を有することが要件とされ、国家公務員法上の欠格事由に該当しないことも求められます。
最新の募集情報については、経済産業省の公式ウェブサイトで随時更新されています。
金融庁
金融庁では複数の部署で任期付弁護士を募集しています。現在募集中の案件として、監督局では主要行等の監督事務に従事する弁護士(課長補佐クラス)を募集しており、法令照会・ノーアクションレターに関する業務、各種施策策定に際しての法制面からの検討、監督指針等の改正に関する業務などを担当します(令和7年7月募集、9月から2年間程度の任期)。
金融庁に属する証券取引等監視委員会では、複数の職種で任期付の弁護士を募集しています。
現在募集中の案件として、証券検査業務に従事する職員(令和6年12月25日募集開始)があります。
この職種では、証券検査官等とともに金融商品取引業者等に対して検査及びモニタリングを実施し、リスク管理・内部管理体制等の適切性・実効性や法令違反行為の有無などの検証を行います。
採用時から原則として2年程度の任期で、勤務成績や業務の必要に応じて延長の可能性があるでしょう。
これらの業務では、金融市場の公正性と透明性を確保する重要な役割を担い、市場の健全な発展に直接貢献することができます。
具体的には、関係者への質問調査、強制調査権限の行使、調査結果の分析・整理、告発や課徴金納付命令勧告に向けた手続きなどを担当します。
応募資格として弁護士資格が必須であり、金融商品取引法や会社法などの企業法務、金融法務に関する専門的知識・経験が望ましいとされていますが、これらの分野に関心がある場合でも応募可能とされており、入庁後の研修制度も充実しています。
参考:職員の募集(主要行等の監督事務に従事する職員【弁護士】):金融庁
任期付職員の募集について(弁護士:証券検査に従事する職員)
消費者庁
消費者庁でも、取引対策課や表示対策課において、任期付弁護士を募集していた例がいくつかあります。今回は2つの例をご紹介します。
取引対策課では、消費者取引対策官(課長補佐級職員)として弁護士を募集しています。
主な業務内容は、デジタル技術を活用した消費者取引への対策等に関する業務(新政策の立案・検討等を含む)、特定商取引法及び預託法に関する法執行業務(事件調査及び行政処分に係る業務)、法解釈に関する検討・相談対応業務、訴訟対応業務、審査請求に係る審理員業務などです。
消費者庁では、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から特定商取引法を活用し、消費者の利益の保護及び取引の適正化を図っています。
また、販売預託の原則禁止等を規定した預託法を活用し、預託者の利益の保護を図っています。
総務課では、法規専門官として弁護士を募集しています。
主な業務内容は、消費者庁の所管法令(景品表示法、特定商取引法等)に基づく行政処分に対する行政訴訟その他の訴訟への対応業務及び消費者庁に対する審査請求への対応業務、消費者庁所管の各種消費者保護関係法令の執行等に係る公表文書等についての法的審査業務、その他消費者庁の所掌事務における法律問題及び公文書管理等についての重要事項に関する業務などです。
これらの職種では、法の精神を尊びつつ、条文案の起草作業や法案審査など法律の制定に係る一連のプロセスについても幅広く経験を積む機会があり、消費者被害の防止と救済に直接関わる重要な業務を担当します。
参考:消費者庁・課長補佐級・弁護士(任期付・消費者取引対策官) | VOLVE | 官と民をまたがる越境キャリア支援 | 国家公務員、官僚
消費者庁・一般職(任期付・弁護士) | VOLVE | 官と民をまたがる越境キャリア支援 | 国家公務員、官僚
公正取引委員会
公正取引委員会事務局では、独占禁止法の執行機関として弁護士を積極的に募集しています。
2024年から2025年にかけて継続的に募集が行われており、特に2025年には経験弁護士38名の大規模な公募が予定されています。
任期は約2年から2.5年間で、採用時期によって若干異なります。
業務内容は独占禁止法の執行業務として、カルテルや企業結合の審査・審判・調査等、競争政策の立案業務などがあります。
配属先に応じて担当業務が決定されますが、いずれも市場競争の促進と消費者利益の保護に直結する重要な業務です。
法曹有資格者で実務経験を有することが求められ、特に企業法務や独占禁止法関連の経験があることが望ましいとされています。
競争法分野でのキャリアを築きたい弁護士にとって、この上ない機会となっています。
参考:任期付職員(法曹資格者(弁護士))の募集について|公正取引委員会
法務省
民事局では、民事基本法の法律案等の立案事務を担当する任期付職員としての弁護士募集です。
令和7年6月2日に公示された募集では、令和7年8月から令和8年7月までの1年間の任期(状況により延長可能性あり)で、倒産法等を担当分野とする職員を1名募集しています。
主な業務内容は、破産法、民事再生法、会社更生法その他の倒産法に関する様々な検討作業等です。
応募資格として、倒産法等の実務に関する専門的な知識・経験を有し(弁護士として倒産法等に関する実務経験がおおむね5年以上)、かつ法律案等の立案を行うための法的・論理的な思考能力に秀でている方が求められています。
訟務局では、国が当事者となる訴訟事件への対応や法的支援業務を担当する弁護士を複数の拠点で募集しています。
令和7年4月1日に公示された募集では、訟務局での随時採用(令和7年7月以降)、訟務局国際業務での随時採用(令和7年7月以降)、東京法務局での採用(令和8年4月以降)、名古屋法務局での採用(令和7年7月以降)などの複数の募集が行われています。
これらの職種では、国の政策立案における訴訟リスク検討などの法的支援業務や、各省庁からの法的相談への対応など、行政の法的基盤を支える重要な役割を担います。
訟務実務経験のある弁護士が対象で、特に国や地方自治体の訴訟や行政法務の経験が望ましいとされています。
内閣府
内閣府の規制改革推進室では、参事官補佐級相当として弁護士の募集が行われています。
令和7年7月25日には募集期間が延長されており、現在も募集が継続されています。任期は通常1年間程度で、最大5年まで更新可能です。
主な業務内容は、規制改革に関する企画立案や総合調整業務です。
具体的には、規制や制度の現状・課題の専門的調査分析、改革の方向性の検討、関係省庁や有識者との調整、規制改革推進会議の運営補助などを行います。
日本の経済成長や社会の効率化に直接貢献する政策立案の中枢で活躍することができます。
応募資格として弁護士資格に加え、一般的に実務経験3年以上または規制改革関連分野の専門知見と実務経験が求められます。
規制緩和や制度改革に関心のある弁護士にとって、理想的なキャリア機会といえるでしょう。
外務省
外務省の国際法局経済条約課では、経済連携協定(EPA/FTA)、投資協定、租税条約、世界貿易機関(WTO)交渉などの各種協定・条約の締結、解釈及び実施や国内法制の国際法整合性の観点からの検討等に対応する特定任期付職員として弁護士の募集をしています。
主な業務内容は、貿易・投資・租税分野(特にEPAにおける物品・サービス、投資、知的財産、競争等の各分野、投資協定、租税条約)の交渉業務や条約の締結手続き、条約に関する解釈の対応などです。
現在、既に複数名弁護士が在籍しているため、弁護士としてのスキルアップも期待できる環境が整っているといえるでしょう。
応募資格は、弁護士としての実務経験3年以上と、国内外のやり取りが発生するため英語スキルも求められます。
英語スキルを活かして、グローバルな環境で働きたい方に向いているキャリアでしょう。
参考:特定任期付外務省職員の募集|外務省
任期付職員|外務省
また、No-Limit弁護士では外務省国際法局経済条約課にお伺いし、弁護士のキャリアについてインタビューを実施しました。ぜひこちらもご覧ください。
弁護士の任期付公務員を募集している地方自治体等の3つの例
次に、地方自治体で募集している弁護士の例をいくつかご紹介していきます。地方創生の観点など、地元貢献を目指す弁護士はぜひ参考にしてみてください。
都道府県
都道府県レベルでも、任期付公務員として弁護士の募集が活発に行われています。
過去の募集例として、東京都労働委員会事務局では、審査調整法務担当課長職として弁護士を募集した事例があります。
2024年10月公告で令和7年10月採用予定、2年間の任期で最長5年まで延長可能とされ、主な業務内容は不当労働行為救済申立事件の審査実務と職員指導、訟務事務等でした。
労働法分野の専門知識を活かして、労使紛争の適正な解決に貢献する重要な職務です。
また、三重県総務部法務・文書課でも、2024年7月に2年間の任期で法務業務全般を担当する弁護士を募集した事例があります。
業務内容は県施策の法的妥当性検証、法令解釈や訴訟事務の助言・指導、条例案等の審査、職員への法律相談・研修実施など多岐にわたり、自治体法務の中核的役割を担い、地域住民の利益を守る重要な職責となっています。
これらの例に見られるように、都道府県レベルでは労働委員会、総務部法務課、人事委員会などの部署で弁護士の専門性を活かした任期付職員の募集が行われており、地方行政の法的基盤を支える重要な役割を担っています。
市区町村
市区町村レベルにおいても、弁護士の専門性を活かした任期付公務員の募集が増加しています。
過去の募集例として、奈良県生駒市総務部では、法務担当として弁護士を募集した事例があります。
2024年11月公告で令和7年4月採用予定、3年間の任期で最長5年まで延長可能とされ、職員からの政策法務相談へのアドバイス、条例・規則案の審査、職員研修の実施、行政不服審査の審理員業務などを担当する基礎自治体の法務機能強化に直接貢献する意義深い職務です。
準公的機関
独立行政法人や準公的機関でも、任期付で弁護士を募集するケースが増えている傾向です。
日本司法支援センター(法テラス)では、スタッフ弁護士として継続的に募集を実施しています。
司法修習生向けには募集期間を限定して実施され、法曹経験者については随時募集を行っています。原則として3年契約で、新人弁護士は養成1年+ 3年、その後3年ごとの更新となります。
民事法律扶助事件や刑事国選弁護事件などの法律相談・訴訟代理業務を行い、弁護士過疎地域や地方で幅広い分野の案件を担当することが特徴です。
司法アクセスの向上に直接貢献する社会的意義の高い業務で、完全給与制により安定した環境で法的サービスを提供することが可能です。
中小企業基盤整備機構においても、中小企業活性化協議会のサブマネージャー・エリア担当弁護士などの募集が行われることがあります。
地方の中小企業活性化協議会において、経営者保証ガイドライン活用による中小企業再生支援や再チャレンジ支援、再生計画策定支援などを行い、地域経済の活性化に法的専門性を活かす重要な役割を担う仕事です。
No-Limit弁護士にお任せください
無理な転職は勧めません。市場価値の確認や、今の環境に残るべきかの判断から、弁護士特化のプロが徹底サポートします。
今ならあなただけの「キャリア戦略シート」を無料プレゼント中!
プロに相談する(無料)
※履歴書や職務経歴書は不要です。
※相談した事実が公開されることはございません。
弁護士が任期付公務員に出向するメリット
弁護士が任期付公務員として出向することは、メリットが多々ありますが、その中でも3つご紹介していきます。
ドメインエキスパートになりやすい
任期付公務員として特定の省庁や機関で働くことで、その分野の深い専門知識を獲得することができます。
たとえば、金融庁で証券調査官を経験すれば金融規制の専門家として、公正取引委員会で独占禁止法の執行に携われば競争法の専門家としての地位を築くことが可能です。
民間の法律事務所では、幅広い案件を扱うことが多く、特定分野を深く掘り下げる機会は限られがちです。
しかし、任期付公務員として働くことで、その分野の法制度の成り立ちから運用の実際まで、体系的かつ実践的な知識を身につけることができます。
また、政策立案プロセスに関与することで、法律がどのような背景で制定され、どのような意図で運用されているかを深く理解することができます。
この経験は、民間に戻った際の法的助言の質を格段に向上させ、クライアントにより価値の高いサービスを提供することにつながるでしょう。
政策立案に携われる可能性がある
任期付公務員として働く最大の魅力の一つは、法律や政策の立案プロセスに直接関与できることです。
法律事務所で働いているだけでは経験できない、社会制度の根本的な部分に関わることができます。
たとえば、法務省の民事局で会社法の改正作業に携わったり、内閣府の規制改革推進室で規制緩和の企画立案に参加したりすることで、日本社会全体に影響を与える政策決定プロセスを間近で体験することが可能です。
このような経験は、弁護士としての視野を大幅に広げるだけでなく、将来的に政策に関わる仕事に従事したい場合の貴重な基盤となります。
また、政策立案の現場を知ることで、民間セクターに戻った際にも、より効果的な政策提言や制度改善の提案ができるようになります。
ワークライフバランス
公務員としての働き方は、民間の法律事務所と比較して安定しており、ワークライフバランスを保ちやすい環境が整っています。
勤務時間が明確に定められており、長時間労働が常態化することは少なく、有給休暇も取得しやすい環境です。
また、給与体系も安定しており、業績に左右されることなく一定の収入を確保することができることに加えて、健康保険、厚生年金、各種手当など、公務員としての充実した福利厚生恩を受けられます。
特に、子育て世代の弁護士にとって、育児休業制度や時短勤務制度などが充実している点は大きなメリットです。
民間の法律事務所では実現困難なワークライフバランスを保ちながら、専門性を活かして社会貢献することができます。
No-Limit弁護士にお任せください
無理な転職は勧めません。市場価値の確認や、今の環境に残るべきかの判断から、弁護士特化のプロが徹底サポートします。
今ならあなただけの「キャリア戦略シート」を無料プレゼント中!
プロに相談する(無料)
※履歴書や職務経歴書は不要です。
※相談した事実が公開されることはございません。
実際の任期付公務員の弁護士出向例
ここで、実際の任期付公務員として出向した弁護士のキャリア例を1つご紹介します。
秋山一弘弁護士(第二東京弁護士会所属、1970年生まれ)は、東京都町田市総務部法制課で法務担当課長として2010年4月から2013年3月まで3年間勤務されました。
町田市は東日本で最初に公募により弁護士を採用した基礎自治体として制度の先駆的役割を果たしています。
秋山弁護士は、特定任期付職員として採用された同氏の業務は多岐にわたり、訴訟事務・指定代理人としての訴訟活動、職員を対象とする「よろず法律相談」の常時受付、不服申立制度の裁決・決定、職員への法務指導・人材育成での研修講師など、自治体法務の全般をカバーする包括的な職責を担いました。
出向後は自治体法務関係の顧問、委員、研修、執筆等の業務を獲得し業務範囲が大幅に拡大し、現在は日弁連法律サービス展開本部自治体等連携センター委員、第二東京弁護士会行政連携センター部会副委員長として、自治体と弁護士会の連携強化に貢献しています。
弁護士が任期付公務員に出向した後のキャリア例
最後に、弁護士が任期付公務員として出向した後は、どのようなキャリア戦略を描くことができるかについて、いくつかの考え方を解説していきます。
法律事務所に戻り経験を活かして顧客拡大
任期付公務員の経験を終えて法律事務所に戻る場合、その分野の専門家として新たなクライアント層を開拓することが可能になります。
たとえば、金融庁での経験があれば金融機関や証券会社からの法務相談、公正取引委員会での経験があれば独占禁止法などを中心に企業取引におけるコンプライアンスの案件を獲得しやすくなります。
また、政策立案プロセスを熟知していることで、法改正の動向を先読みしたアドバイスや、規制当局の考え方を踏まえた実践的な法的助言を提供することができます。
これは、他の弁護士との差別化要因となり、より高い付加価値を提供することを可能にします。
さらに、省庁や自治体との人脈を築いていることも、法律事務所にとって貴重な資産です。行政機関からの委託業務や、官民連携プロジェクトへの参画機会を得やすくなる可能性があります。
関連する職種の任期付公務員にさらに渡り歩く
一つの省庁での任期付公務員経験を活かして、関連する分野の他の機関で再び任期付公務員として働くケースも増えています。
たとえば、経済産業省で通商法務を経験した後、外務省の経済局で国際経済交渉に携わったり、消費者庁での経験を活かして他の規制官庁で類似業務に従事したりすることが可能です。
このような「渡り歩き」により、複数の分野にわたる広範な専門知識と人脈を構築することができます。また、異なる省庁の文化や働き方を経験することで、行政機関全体への理解を深めることができます。
将来的に民間セクターに戻る際には、複数分野の専門性を持つ希少な人材として、より多くの選択肢とより高い待遇を得ることが期待できます。
No-Limit弁護士では、東京都庁の総務局総務部法務課に所属する弁護士に、キャリアインタビューを実施しました。ぜひこちらもご覧ください。
政策秘書
任期付公務員としての経験は、政治家の政策秘書としてのキャリアパスにもつながります。
政策立案プロセスを熟知し、特定分野の専門知識を持つ弁護士は、政治家にとって貴重なアドバイザーとなり得ます。
政策秘書として働く場合、政治家の政策判断を法的観点からサポートし、法案作成や政策提言に直接関与することが可能です。
また、国会での質疑準備や委員会での発言内容の検討など、立法府での活動を支援する重要な役割を担います。
このキャリアパスは、より直接的に政治プロセスに関与したい弁護士にとって魅力的な選択肢であり、任期付公務員での経験が重要な基盤となります。
まとめ
弁護士の任期付公務員への出向は、従来のキャリアパスにはない多くのメリットを提供する制度です。
専門分野の深い知識獲得、政策立案への参画、安定したワークライフバランスなど、民間の法律事務所では得られない貴重な経験を積むことができます。
各省庁や地方自治体、準公的機関において多様な募集が行われており、通商法務、金融規制、消費者保護、競争法、立法作業など、幅広い分野で弁護士の専門性が求められています。
任期終了後のキャリアパスも多様で、民間への復帰、他の公的機関への転職、政治分野への進出など、様々な可能性が開かれています。
法曹界の多様化が進む中で、任期付公務員制度は弁護士にとって重要なキャリア選択肢の一つとして定着しつつあります。
社会貢献を重視し、専門性を活かして新たな挑戦をしたい弁護士にとって、この制度は検討価値の高い選択肢といえるでしょう。
今後も各機関での募集は継続されることが予想され、弁護士のキャリア形成における重要な制度として発展していくことが期待されます。
自分の市場価値、入所時に聞いた条件との乖離、ワークライフバランスへの不安。
弁護士という多忙な職業だからこそ、一人で抱え込みがちな悩みに、私たちは徹底的に伴走します。
【No-Limit弁護士】は、単なる求人紹介ではなく「失敗しない転職」を追求する弁護士特化の転職エージェントです。
- 1. ムリな転職は勧めません
- お話を伺った結果「今は動かないほうが良い」とアドバイスすることも珍しくありません。
- 2. 徹底した透明性を担保
- 良い面だけでなく、その職場の「マイナス面」も事前にお伝えし、転職後の後悔をゼロにします。
- 3. 多忙なあなたをサポート
- 書類作成から日程調整、内定後のフォローまで、すべての工程を私たちが代行いたします。
- 4. 定着率98.6%(※)のマッチング精度
- 他では知り得ないリアルな職場情報が充実。求人票の「裏側」まで包み隠さず共有するからこそ、ミスマッチのない転職をお約束します。
- 5. あなただけのキャリアシートをプレゼント
- 面談を実施した方全員に、プロのアドバイザーがあなたの経歴と強みを分析し、今後の可能性をまとめた「個別キャリア戦略シート」を無料で作成・進呈いたします。
- 履歴書・職務経歴書は不要です。
- オンライン(Google Meet)やお電話で、15分から気軽にご相談いただけます。
- 相談や転職活動の事実が、外部に漏れることは一切ございません。