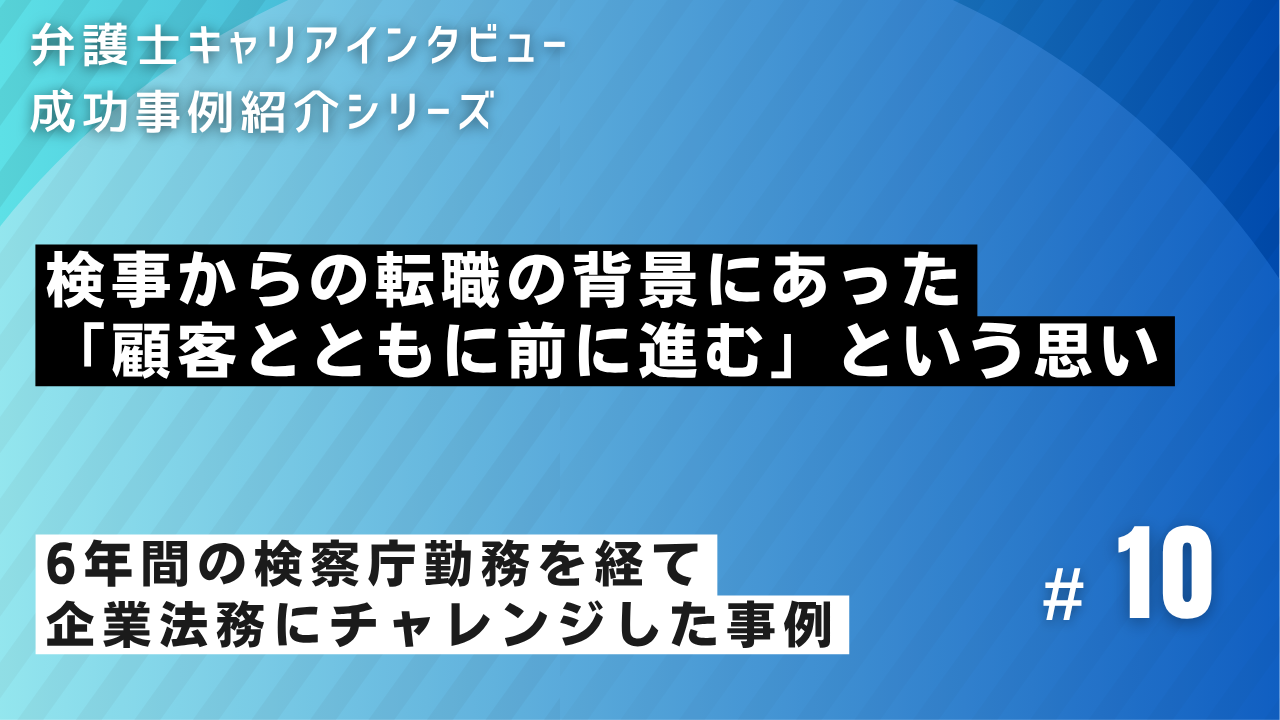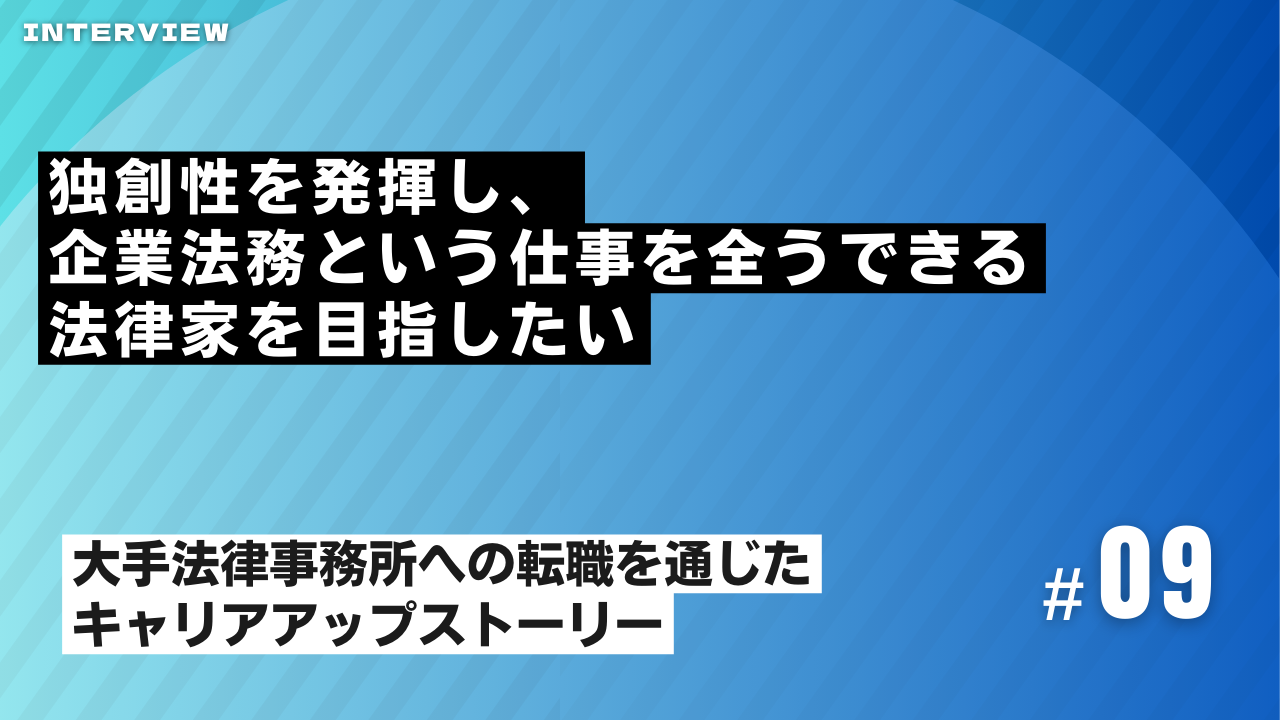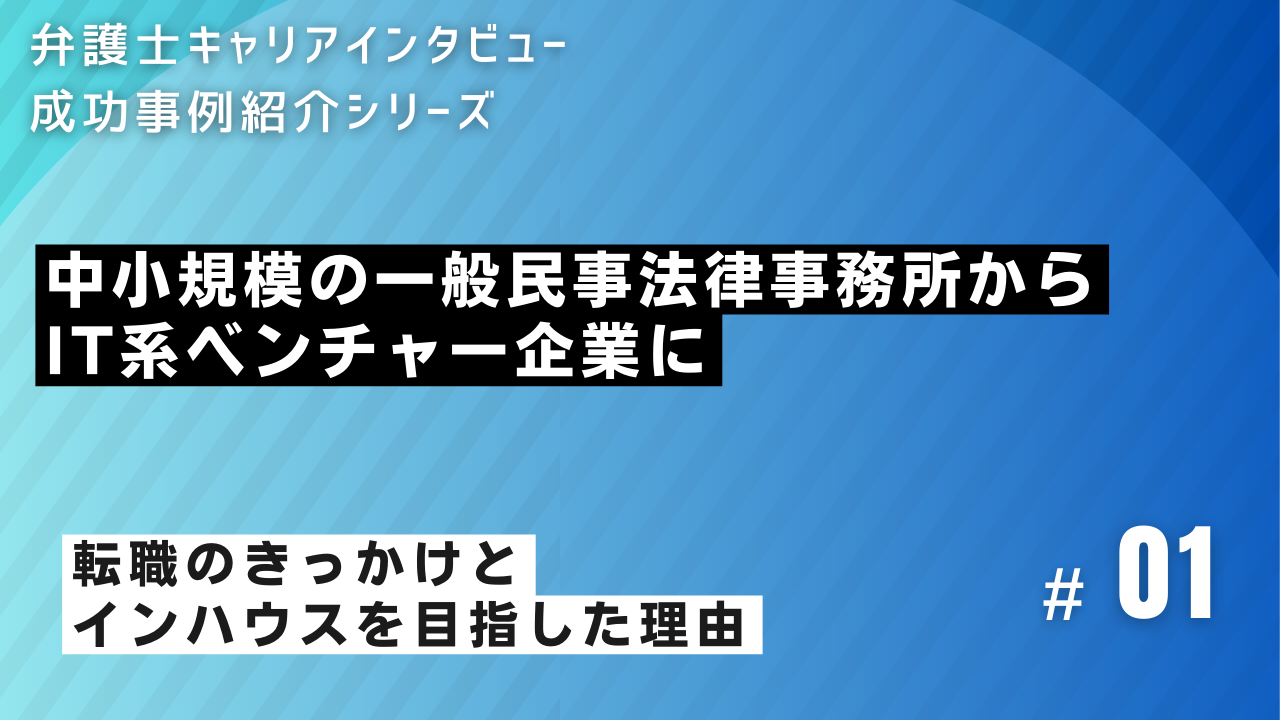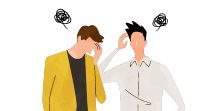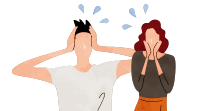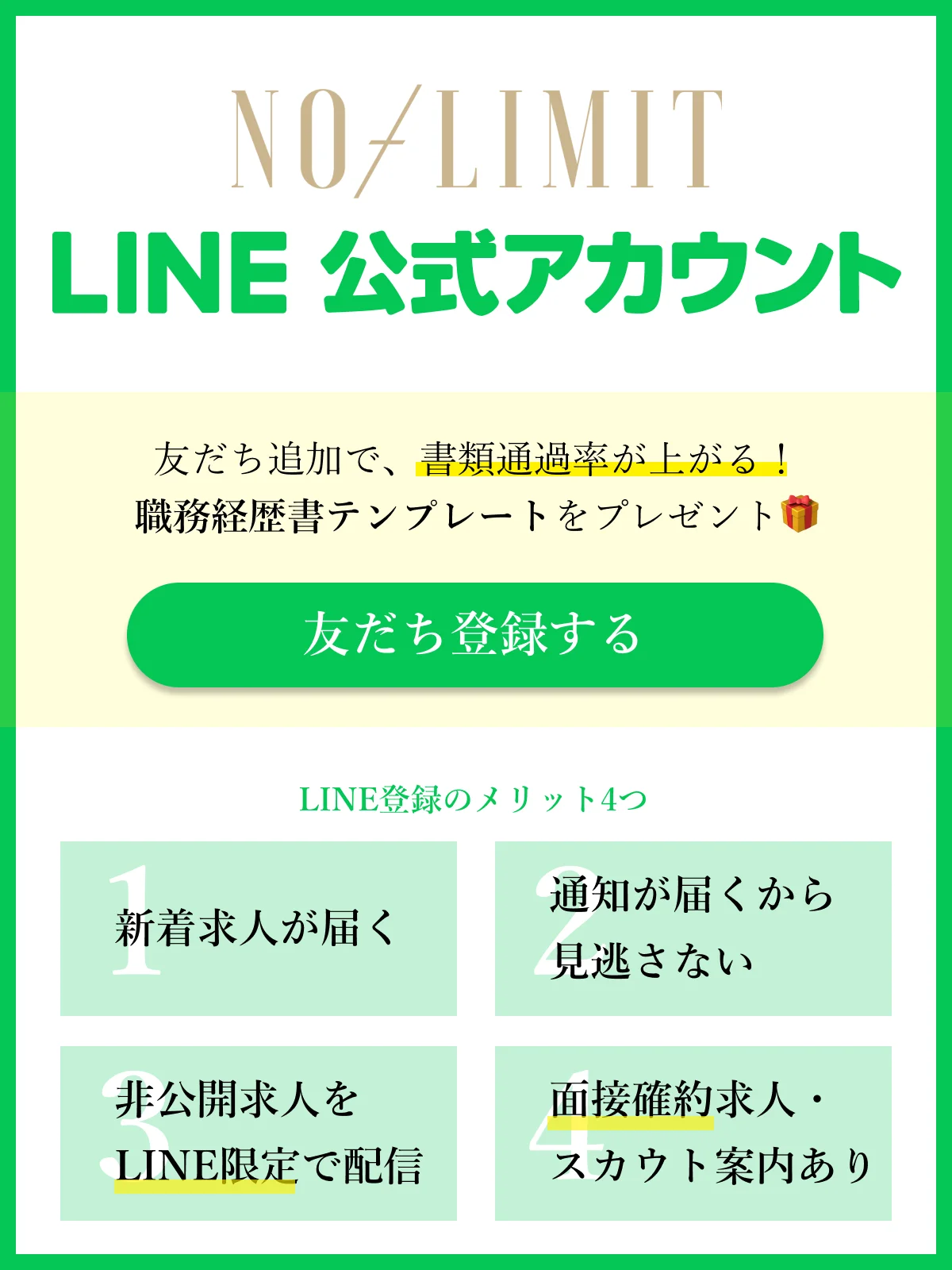司法試験という長く厳しい挑戦を終えた直後、多くの受験生が陥るのが、「何をすべきかわからない」という空白の時間です。
燃え尽き症候群、不安、将来への迷い……これらは珍しいものではありません。
本記事では、司法試験受験後に取り組むべき「法律以外のスキル」とキャリア形成のための実践的な行動を紹介します。
特に、弁護士業界の変化や競争環境を踏まえた「異質性戦略」の観点から、これからの法曹に必要な視座と行動を提案します。
目次
司法試験受験後にやることに迷ったら
司法試験後、その疲れを癒してやることに迷ったら、その迷っている時間さえも惜しいです。
アイデアがなければ、ぜひここでいくつかご紹介するような発想で、まずは行動ベースで始めてみてください。
非日常の体験をする
司法試験という一大イベントが終わると、日常生活にポッカリと穴が空いたように感じる方は少なくありません。
そんなときこそ、日常の枠から離れた非日常の体験に身を置いてみることをおすすめします。
旅行、ボランティア、アート鑑賞やワーケーションなど、普段の自分なら絶対に選ばないような経験に飛び込むことで、新しい刺激を受け、自分の価値観や思考パターンを客観的に見つめ直すことができます。
こうした非日常の体験は、今後のキャリア設計において「他人と異なる視点」を持つ大切な土台となります。
自分の選択肢の幅を広げるためにも、「学び」としての旅や出会いを積極的に取り入れることは非常に有意義です。
やったことがないことにチャレンジする
司法試験の勉強に没頭していた期間、多くの人が「法律」以外の世界に触れる機会を失ってきたはずです。
そんな今だからこそ、あえて「未経験」の分野に一歩踏み出してみることが、自分の思考回路や能力の幅を広げる絶好の機会となります。
たとえば、プログラミングに挑戦してみたり、イベント運営のボランティアをしてみたり、営業のアルバイトをしてみたりすることで、法曹という職業とは異なる「ビジネスの現場感覚」や「対人スキル」を養うことができるでしょう。
さらに、1つのアイデアとして、五感で感じることができる体験をしてみてください。
長期間にわたる机上中心の勉強で忘れられがちな「身体性」や「感覚性」に意識を向けてみるのも、水平的なキャリア形成の糸口になります。
たとえば、畑仕事、陶芸、サーフィン、登山、舞台鑑賞など、弁護士業界とは無縁に思える分野に身を置いてみることで、自分自身の「抽象的すぎる言語脳」に気づくかもしれません。
こうした体験で得た知見や体験、人脈から、将来、クリエイター支援法務やアート関連法務、環境・農業法務など、今までの自分が想像もしなかった道につながる可能性を秘めています。
法律以外の分野のスキル習得に取り組む
司法試験後の期間は、時間的にも精神的にも余裕があるからこそ、新しいスキルを習得するには最適です。
とくに近年は、生成AIの活用やデジタルマーケティング、情報セキュリティ、データ分析など、法律業務の枠を超えたスキルが求められる場面が増えています。
こうしたスキルを早期に習得しておくことで、法律事務所や企業法務の現場で「即戦力」としての評価を得られるほか、キャリアの選択肢そのものを増やすことにもつながります。
その際にどのようなスキルを習得するかという検討などにおいては、アート思考(Art Thinking)が参考になります。
アート思考とは、論理や再現性とは異なる「感性と思索の往復運動」によって独創的な問いを立てる力です。
未来をデザインする場面において、法律家が“答え”ではなく“問い”をつくる能力を求められる機会は増えています。
また、ストーリーテリングの技術や、ゲームの世界観設計、シナリオライティング、漫画編集など、一見無関係なクリエイティブ領域のスキルが、企業のブランディング戦略やパブリックアフェアーズ分野で生きてくることもあります。
法曹として生き残るために競争戦略上重要な”異質性”
弁護士として活躍していく上で、これからの時代は、生成AIの台頭やリーガルテック業界の成長や進展などに伴い、これまでの発想とは異なる競争戦略が求められます。
以下、異質性をテーマに具体的に解説していきます。
弁護士業界のコモディティ化
かつて弁護士は「資格さえ取れば一生安泰」と言われた時代がありました。
しかし現在では、弁護士数の増加、企業内弁護士の拡大、AIの登場によるリーガルテックの普及などにより、業界全体がコモディティ化しつつあります。
つまり、資格そのものが希少性を失い、「代替可能な存在」となりつつあるのです。
このような環境では、「同じことを同じようにできる」だけでは、差別化することはできません。
むしろ、「この人にしかできない」と思われる要素、つまり「異質性」が求められる時代になっています。
自分の名前で顧客からの認知度を獲得していくこと、自分にしかできない領域を持つことが非常に重要です。
多様なフィールドで活躍できる場が当たり前に
近年は、弁護士が活躍するフィールドも拡大しています。
企業のインハウスロイヤー、スタートアップの法務顧問、国際機関、官庁、さらにはクリエイターや発信者としての活動も珍しくありません。
特定分野に特化したスペシャリスト、あるいは法律×他分野のハイブリッド型人材が重宝される傾向は、今後さらに強まるでしょう。
いかに自分だけの”ブルーオーシャン”を獲得できるか
これからの時代、弁護士として生き残るためには、自分だけの「ブルーオーシャン=競争の少ない独自領域」を見つけ出すことが必要です。
たとえば、「法律×AI」「法律×教育」「法律×国際関係」といった掛け算がそれに当たり、掛け合わせの要素が多いほど、独自性は増していきます。
ただし、結局何を提供価値としているかが認識できる程度でなければ、要素が多すぎても複雑になり、社会や人々からは認識されなくなってしまうかもしれません。
要素を考える視点は、人生の中で大きな原体験のある領域、知見や経験を有する分野・業務、新規性といったものが考えられます。
そのためには、まず自分の興味・関心・価値観と向き合い、自分が情熱を持って取り組める分野を明確にすること。
そして、その分野で法律家としての専門性と“異質なスキル”をどう組み合わせるかを意識的に設計することが求められます。
今すぐできる!司法試験受験後に取り組むべき法律以外の分野5選
ここで、今すぐにでもできる法律以外のことや身に着けるべきスキルなど5つご紹介していきます。
AIを使い倒す
ChatGPTをはじめとする生成AIは、すでに法務の現場でも活用が進んでおり、文書作成、リーガルリサーチ、契約書レビューなどにおいて、AIは補助的なツールとして大きな威力を発揮します。
これらのツールを「使える」だけでなく、「業務設計に落とし込める」力は、現場での評価を大きく左右するでしょう。
とにかくあらゆる場面やシチュエーションにおいて、法律に関することであろうがなかろうが、AIと向き合って使いまくることが重要です。
実際に自分のアイデアをAIに提案させる練習をし、プロンプトエンジニアリングの基礎も学んでおくことで、実務でも“使いこなせる法務人材”としての武器となります。
SNS運用によるマーケティング
法律家として活動する上で、SNSによる自己発信はますます重要です。
特に個人事業として弁護士活動を行う場合、認知度の向上と信頼性の構築はSNS運用がカギを握ります。
X(旧Twitter)やnote、Instagram、LinkedInなどを活用し、法的な見解やキャリアの考察を定期的に発信することで、「誰が何に強いか」が明確になります。
これは営業力やブランド力の土台とも言えるスキルです。
情シス・セキュリティ
企業法務の現場では、契約やガバナンスだけでなく、情報セキュリティや社内インフラの理解が不可欠です。
特に、社内規定の策定やリスク対策において、情報システム部門と連携する場面が増えています。
IPA(情報処理推進機構)が提供する情報セキュリティマネジメント試験の学習などを通じて、基礎的な情報セキュリティリテラシーを身につけておくと、企業における法務人材としての評価は飛躍的に向上します。
さらに、AIが社会のインフラになっている中で、そもそも情報システムやセキュリティに疎い人々が少なくありません。
基本的なIT技術の仕組みや、情報セキュリティの知識がないと特に弁護士として大きく責任を問われるようなことになりかねないでしょう。
そのため、情報システムやセキュリティについて深掘りをしておくことで、弁護士業界内外でのプレゼンスを高めることができます。
データサイエンス
契約リスクの定量化や法務KPIの可視化など、定性的な議論だけでなく、数字で物事を語る力が求められつつあります。
Excel、Python、BIツールなどを用いたデータ分析の基礎は、どんな職種でも活きるスキルです。
特に、司法のDX化が著しく、とりわけ民事判決のデータベース化が来年にもスタートするというニュースが注目されますが、こうした動きからも弁護士業界においてもビックデータ活用やデータビジネスとしていかに競争力を高めるかが重要になってきます。
データサイエンスのスキルを身につけておくことで、「感覚ではなく数値で伝える」法務人材として、経営層との意思疎通力が格段に高まります。
toCビジネスとしても、一般民事事件において、個人の依頼者に対しての説明や、案件の戦略を練る際にデータドリブンの提案や戦略設計をすることで、差別化を図ることができるでしょう。
営業経験
あえて法律とは無関係な「営業経験」を積むことは、想像以上にキャリアの幅を広げる鍵となる要素です。
弁護士業務でも、依頼者との折衝、事務所の運営、顧客開拓など、「営業的思考」が必要になる場面は多々あります。
弁護士のコモディティ化の中で、いかに自分が異質であり、独自のリーガルサービスとしての提供価値があるかを認識させることは重要なポイントです。
その際には、営業職におけるトークスキルや自分自身の見せ方についても、最適なスキルを身に着けることにつながります。
飛び込み営業、テレアポ、イベントでのブース対応など、地道な経験を通じて得られる「人に話しかける力」「相手のニーズを引き出す力」は、法曹実務にも通じる普遍的なスキルです。
法律以外の分野への取り組み方
実際に法律以外の分野にはどのように取り組めばよいでしょうか。具体的な例を5つ紹介していきます。
企業インターン
司法試験後の期間に、法律事務所ではなく、一般企業のインターンに参加するという選択肢もおすすめです。
特に、スタートアップやベンチャー企業などでは、柔軟な発想力と行動力を重視しており、法務バックグラウンドを歓迎するケースもあります。
たとえば、スタートアップのカスタマーサクセス部門でインターンをすることで、「顧客目線」を学び直す貴重な機会となり、のちの法律相談における“現場感覚”の構築に大きく寄与することが期待できるでしょう。
営業、企画、広報、カスタマーサクセスなど、法律とは直接関係のない部門に身を置くことで、組織の実態や意思決定プロセス、現場の温度感を肌で感じることができます。
これは、後に企業法務を行ううえでも大きな財産です。
これらの体験は、企業法務への理解を深めるだけでなく、ビジネスセンスやマネジメント感覚を身につける絶好の機会になるでしょう。
資格試験の勉強
新しい分野に取り組むモチベーション維持のために、「資格」を目標に据えるのも有効です。
基本的なものとして、簿記などの勉強はやっておくべきであるといえるほか、会計士、税理士、弁理士などの隣接士業もよいでしょう。
さらには、中小企業診断士、情報処理安全確保支援士、ファイナンシャルプランナー、TOEIC、ITパスポートなど、体系的に学ぶ指標としての資格取得は、スキルの棚卸しや自己効力感の向上にもつながります。
SNSで異質な分野に取り組む弁護士にインタビューをしまくる
法律×異分野で活躍する先輩弁護士やロールモデルを探し、SNSやnoteを通じて直接アプローチしてみるのも大きな刺激になります。
インタビューをさせてもらい、その内容を発信することで、自分の情報発信にもなり、相手との信頼関係の構築にもつながるでしょう。
たとえば、「宇宙ビジネス×法務」「AI開発×知財法」「音楽業界×著作権」といった越境型の法務キャリアを持つ人々は、まさに“異質性”を体現している存在です。
イベントの企画や運営
イベントの企画や運営に挑戦することも、法律家として必要なプロジェクトマネジメント力を鍛えるのに最適です。
講演会、勉強会、パネルディスカッション、セミナーなどを企画し、集客、広報、当日の運営に関わる中で、予算管理や広報戦略、ファシリテーションといったビジネススキルも自然と身につきます。
また、登壇者としての場数を増やせば、プレゼン能力や伝達力の向上にもつながり、将来の法律家としての信頼構築にも直結するでしょう。
さらに、近年、弁護士であっても、自らが「小さな経済圏=ファンと価値の循環する空間」を持つ人が増えてきました。
たとえば、サブスクリプション形式で専門情報を発信する有料コミュニティ、法務系講座の個人開催、電子書籍販売、noteやVoicyでのマネタイズなどがその例です。
これは単なる副業ではなく、「個人でどれだけ価値を提供できるか」「マーケットのニーズをどう察知するか」という観点で、非常に良質な訓練になります。
これらの活動を通じて、法律というスキルが「市場でどう評価されるか」を肌で感じることができ、自分の商品化(パーソナルブランディング)の本質に近づくことができます。
また、「法務の専門性をどう切り出すか」「どの言葉なら届くか」といった、マーケティング的な感覚を身につけることは、企業法務や広報戦略の支援をする際にも活かせる普遍的な力です。
興味のある分野のコミュニティに参加
自分が興味を持っているテーマや業界(例:AI、教育、地方創生、宇宙、メディアなど)のコミュニティに参加するのも非常に有意義です。
SlackやDiscord、Facebookグループ、Meetupなど、オンラインでもオフラインでも活発なコミュニティは数多く存在します。
コミュニティでの発言や貢献を通じて、人とのつながりが生まれたり、協業や学びの機会が広がったりすることも多々あるでしょう。
法律家としての専門性を持ち込むことで、むしろ貴重な存在として重宝されることもあります。
法律以外の分野に取り組むメリット3つ
最後に、こうした法律以外の分野に取り組むことには、メリットばかりではありますが、その中でも3つ取り上げたいと思います。
人脈形成の幅が広がる
法律業界にとどまらず、異業種・異分野に足を踏み入れることで、出会う人の層が一気に広がります。
これは「情報」「協力」「仕事の機会」の源泉です。法務の仕事は、クローズドな環境で完結するものではありません。
自らの人脈を通じて、案件やアイデア、キャリアの選択肢が広がっていくのです。
異分野の人との接点を持つことで、自分が「法律のプロ」であることに価値があると再確認できる機会も多く、自己肯定感の回復にも寄与します。
さらには、人脈形成の幅も広がることで、より幅広い分野への取り組みにもつながる余地が生まれます。
たとえば、公共政策分野での人脈を拡げると、スタートアップの新規事業立ち上げや、行政・省庁における政策提言の場に参画するチャンスが増えるかもしれません。
規制のグレーゾーンを扱う新しいビジネスモデルの法務設計や、自治体のルール形成支援など、「法と社会の接点」にこそ、越境型の弁護士が求められていますが、そうしたニーズにも対応して、顧客領域を獲得していくことができるでしょう。
最近では「DAO(分散型自律組織)」や「Web3時代の個人情報管理」といった分野でも、法制度が未整備な部分に飛び込む姿勢を持つ法務人材が活躍しています。
こうした文脈で信頼されるには、既存の制度をなぞるだけではなく、「問いを立てる力」や「制度設計そのものに関与できる広い視野」が不可欠です。
スキルの掛け合わせができる
「法律×○○」というスキルの掛け算は、今後のキャリア戦略において極めて有効です。
たとえば、「法律×IT」であればリーガルテックや法務DXの世界、「法律×デザイン」であればUI/UX設計やサービス設計への応用もできます。
「法律×プログラミング」でAI契約レビューのプロトタイプを自作したり、「法律×データ可視化」で社内コンプライアンス研修をインタラクティブに再設計したりすることも考えられます。
自分だけの“ハイブリッドスキル”を持つことは、希少価値を高め、市場での競争優位性を確立するうえで非常に大きな武器となるでしょう。
認知度の向上
法律家は、専門性が高いにもかかわらず、社会的な認知が低いケースが多くあります。
法律以外の分野で活動し、発信することで、法律家としての「名前」と「顔」を知ってもらう機会が増え、信頼性や影響力が高まっていきます。
端的には、「この人なんか面白いことやっている」「弁護士らしいけど、弁護士っぽくもない」といった要素が増えるほど、競争力が向上していくでしょう。
とくにSNSやイベント登壇などを通じて、「この人はこんなテーマに強い法務人材なんだ」と思ってもらえる状態をつくることができれば、仕事も人も自然と集まってくるようになります。
まとめ
司法試験受験後の期間は、確かに曖昧で不安も大きい時間です。
しかしこの期間は、単なる「待機期間」ではなく、自分の将来を形づくるための「土壌づくりの時間」です。
法律という専門性をベースにしながらも、それだけにとらわれず、異分野の経験やスキルを積極的に取り入れることで、他者との差別化ができる“異質な法務人材”としての道が拓けていきます。
不安に押しつぶされそうになる日もあるかもしれませんが、自分だけの興味・関心・情熱を起点に、「今できる一歩」を踏み出すこと。
それが、未来のキャリアにおける最大の差になるはずです。
自分の「可能性」に蓋をせず、この貴重な時間を最大限活かしてください。