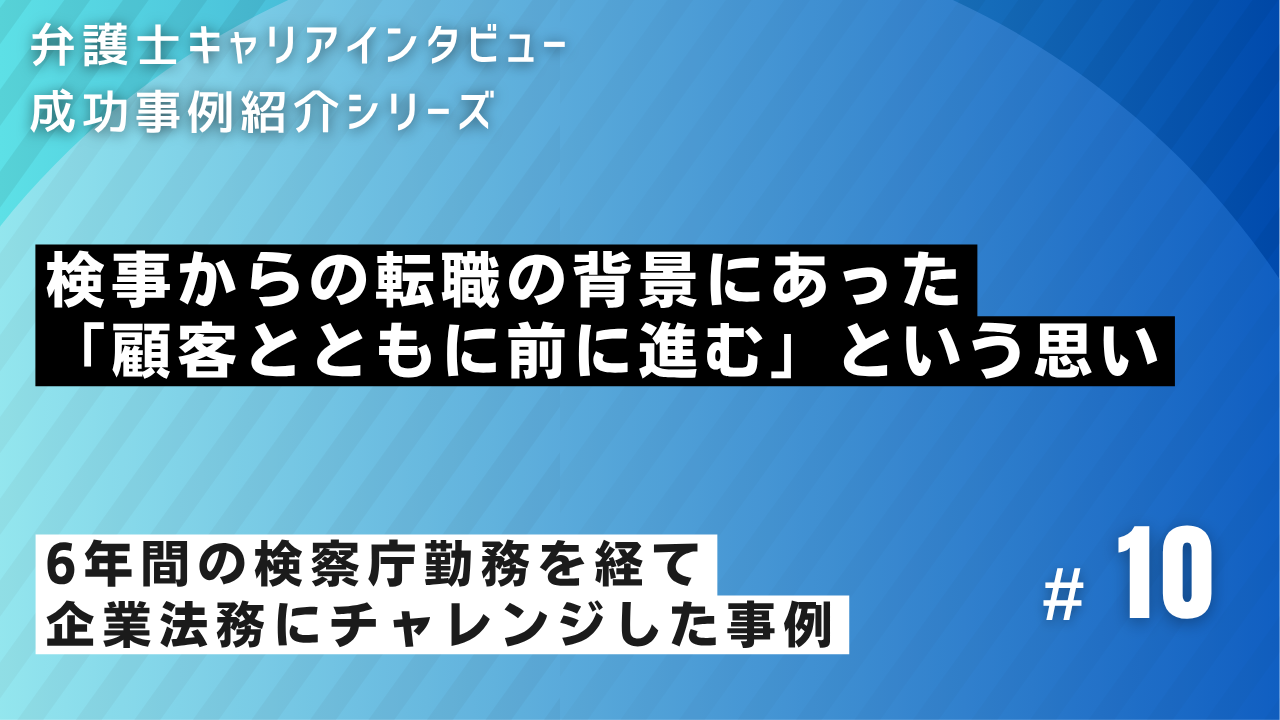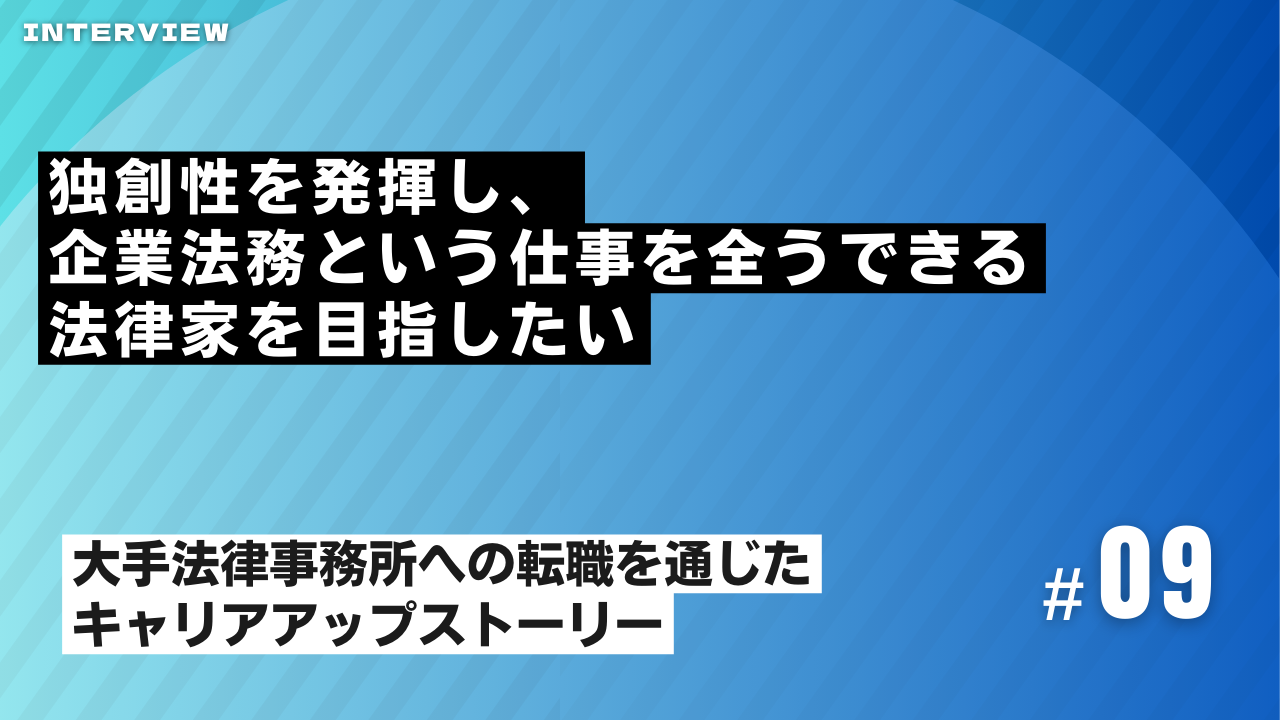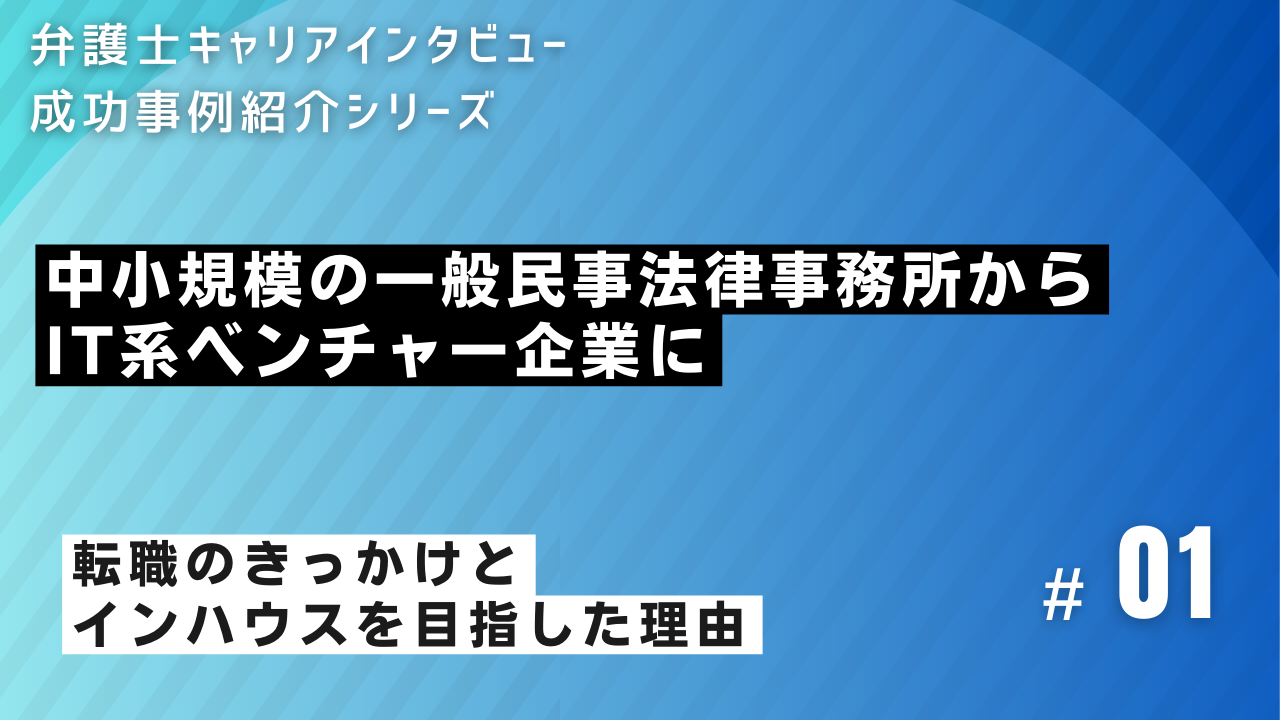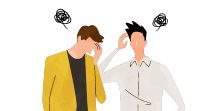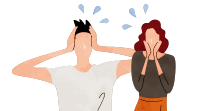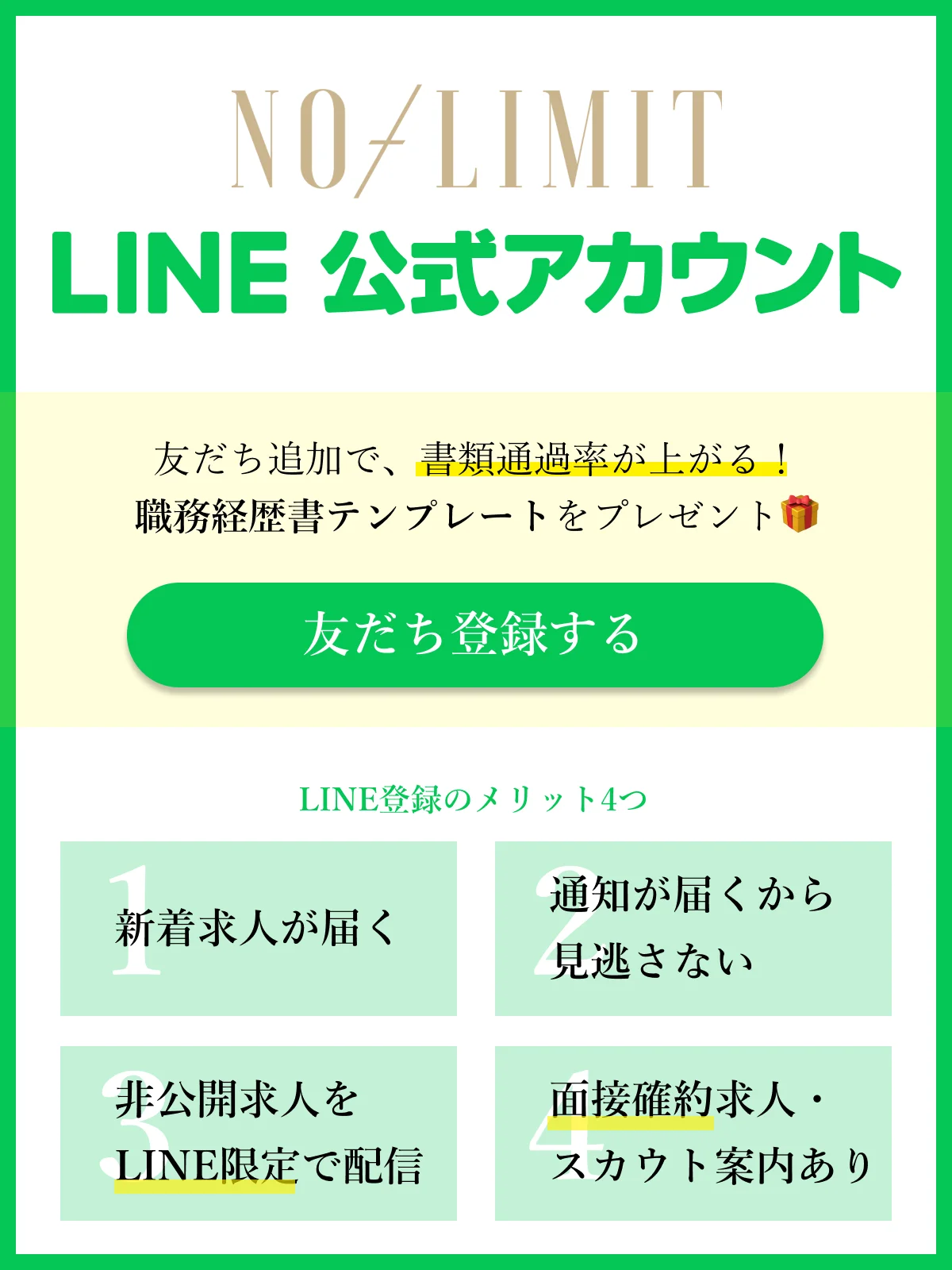司法修習の最終関門である「二回試験(司法修習生考試)」は、司法試験に合格した修習生にとって避けて通れない重要な試験です。
しかしながら、その情報は限られており、具体的な対策方法について明確なガイドラインがないことから、多くの修習生が不安を抱えています。
この記事では、二回試験の概要から試験形式、勉強法、各科目の対策ポイント、さらには陥りがちな「地雷」までを網羅的に解説します。
特に初めて修習に臨む方や、社会人経験を経てキャリアチェンジを目指す方にとって、安心して二回試験に臨むための実践的な情報を提供します。
二回試験(司法修習生考試)とは
そもそも、二回試験(正式名称:司法修習生考試)は、どのような試験かについて、基本的な内容は次のとおりです。
実施概要
司法修習の最後に行われる試験であり、司法試験合格後に法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)としての資格を得るための最終関門です。
合格しなければ司法修習を修了したことにならず、法曹資格を得ることができません。
二回試験の最大の特徴は、不合格者判定試験であるという点です。
あらゆる分野での試験において、基本的には一定の評価点構造の中で、相対評価あるいは絶対評価により合格水準を満たしているかどうかを判断するのが一般的です。
しかし、二回試験は、特に法曹としての資格を与えるに相応しくない者のみを落とす構造の試験であり、実際に結果発表は不合格者の番号を掲載する「不合格発表」の形式なのです。
逆に言えば、別に他の修習生を出し抜いて実力をつけるというよりも、二回試験を突破するという意味では「法曹実務家であれば誰でも当たり前にできるようなレベルのことをアウトプットできること」だけ満たしていれば必要かつ十分という主旨の試験です。
科目と形式
出題科目は以下の5科目です。
- 民事裁判
- 民事弁護
- 刑事裁判
- 刑事弁護
- 検察
いずれも起案形式の記述式問題です。ざっくり言えば、事件記録をもとに設問に関して書面を起案したり、小問をキーワード回答などで記述する形式のものがあります。
A4サイズの答案用紙に横書きで記載します。
※司法試験ではいわゆるCBTが導入されますが、現状、二回試験は引き続き手書き起案の運用です。
試験時間は各科目およそ7時間30分程度で、朝から夕方頃まであります。
配点や難易度は公表されていませんが、試験委員による定性的な評価を経て合否が決定します。
評価は優秀、良好、可、不可の4段階です。5科目全て「不可」がなければ合格となります(いずれか1科目でもD評価であれば不合格)。
※※実務修習中の起案評価は、ABCやABCDといった形で評価されることが多いとされます。
スケジュール
二回試験は選択型実務修習・集合修習の終了後、一定期間を置いた後に1日1科目を5日間連続で実施されます。
従前、74期を除いて基本的に11月頃に行われていましたが、78期以降は試験実施時期の変更などにより3月頃になるといわれています。
二回試験への対策はどうやればいい?
二回試験の対策について、具体的にいつから、何を教材として使い、どのように勉強していくべきなのか解説していきます。
いつからやるべき?
本格的な対策の開始時期は、修習生の志望によって差があります。
裁判官や検察官志望の場合、実務修習の時期から起案評価が採否に影響を及ぼすものとされていて、導入修習や実務修習の前半の段階で志望を出して教官との面談を受けつつ、二回試験でも好成績になるように対策をしていきます。
一方、多くの場合、集合修習の段階から本格的に始動します。
実務修習後は、先に集合修習と選択型修習の順番に先後が変わるので、自分がどちらが先になるか、追い込みタイプかコツコツタイプなのかといった性格・志向によっても変わってくるでしょう。
いずれにしても、少なくとも実務修習中の起案で自分の力量を計りつつ、遅くとも集合修習に際しては白表紙やA起案を読み込んだり、集合修習中の起案でアウトプットしながら、法曹実務のリーガルドキュメント作成の型や事案分析の思考回路に慣れる必要があります。
そして、特に社会人経験のある修習生や育児・介護との両立を図っている人にとっては、「軽くでも早めに始める」ことが直前期の負担軽減につながるため有効です。
何を使って勉強するべき?
司法試験のときのように、基本書や予備校のテキストが溢れているわけではありません。
名門のロースクールであれば、先輩から受け継ぐ対策法などがある場合もありますが、そうしたリソースがない人は、二回試験においてはどのようなものを教材とすべきでしょうか。
王道の教材として、3つほど紹介していきます。
※筆者も、基本的にはこの3種類で二回試験対策をして、無難に突破することができました。
同期修習生のA答案
可能な限り、先輩修習生や同期からPDFなどで入手し、複数年分を比較して読むことが効果的です。特に「教官に評価されたポイント」が明確にわかる答案は貴重です。
白表紙教材と起案例
修習で配布されるいわゆる「白表紙」は、法曹実務において最低限の基礎の基礎をまとめた教材であり、網羅性は低いですが、応用のためのエッセンスが詰まっています。
型を身に着ける意味では、優秀な評価を受けた起案の勉強が最適ですが、自分の素養として身に着けていくには、白表紙を反復しつつ勉強することが重要です。
教官コメントのメモ・講評集
修習中にメモした教官の講評は宝の山です。白表紙に書かれていない「本当に重視されている観点」が語られることがあります。
特に集合修習で教官が強調するポイントは、それを1つ1つ丁寧に押さえておくことで、起案の評価にもつながっていきます。
ネット上で出回っている「虎の巻」「まとめノート」などは便利ではありますが、盲信は禁物です。あくまで補助資料と位置付けましょう。
どのように二回試験の勉強をするべき?
最も重要なのは、実務的な起案能力を身につけることです。
つまり、「答案の構造・型」「論点の優先順位」「事実認定の整理手順」を再現可能なレベルに昇華することです。
おすすめは、「A答案→模範解答→自分の答案」の比較です。
同じ設問で実際に自分で答案を書いてみて、A答案とどこが違うのかを分析しながら復習することで、再現性の高い答案を書く力が身につきます。
二回試験対策のポイント3つ
ここからは、さらに二回試験対策における具体的なポイントについて3つ解説していきます。
各科目のA答案の収集や共有
すでに何回か述べているとおり、各科目のA答案をストックすることが重要です。
そのためには、修習の組や班、同じ修習地の同期との関係性をしっかり作りつつ、共有してもらったり、あるいは自分が頼まれた時には共有したり、そうしたつながりが欠かせません。
A答案で型を学んでいくことは、二回試験の合否という時点のみに向けた話だけでなく、実際に法曹実務家になってから仕事をこなしていく上で必要になります。
また、答案を共有し合う中で修習同期とのつながりを増やしていくことは、法曹になってから様々な仕事の場面でも生きるでしょう。
集合修習や各実務修習でやった起案の徹底復習
司法修習は、答案の原型である「起案」を訓練する場です。
試験と形式が酷似しているため、当時の自分の起案をもう一度見直すことで、答案作成時の癖や改善点が明確になります。
また、教官からの赤ペンコメントを再読することで、改善ポイントを短期間で学び直せるのも利点です。
白表紙と合わせてメモ
白表紙に書かれている内容はあくまで「最低限の共通知識」。試験委員はしばしば、授業中の講評やコメントで本当に重視している点(構成、言い回し、視点)を語っています。
こうした情報は同期との共有で強化できますし、場合によっては「設問の落とし穴」や「採点の基準」を読み解くヒントになります。
各科目ごとの主な対策
ここからは、さらに各科目ごとにおける主な対策のポイントを解説していきます。
民事裁判
民事裁判の要点は、①主張整理、②争いのない事実の抽出と事実認定の4パターン、③書面などの証拠評価、④典型的な訴訟指揮の知識です。
特に、①と②がしっかりと基礎に忠実にできていることが落ちないための鉄則になります。典型的な紛争類型の要件事実については、考えなくても起案できる程度に染み込ませることが重要です。これは、実務修習や集合修習の中で、着実に取り組むことで自然と身に付くでしょう。
民事弁護
民事弁護は、最終準備書面の起案の型と、証拠整理、小問になる基本的な実務知識を白表紙で押さえることがポイントです。
刑事裁判
刑事裁判は、証拠構造に沿った事実認定をする基本的な型を身に着けることが重要です。また、公判前整理手続や訴訟指揮に関する対応のパターンについて、基本を押さえておくことが重要です。
そして、「証拠→事実→評価→結論」という流れを、論理矛盾なく再現する能力が問われます。裁判官の思考様式を踏まえ、「この証拠をどう解釈し、どこで疑問を持つか」といった視点の練習が必要です。
刑事弁護
刑事弁護は、身柄拘束からの解放に関する手続の種類と、各手続の実体的な要件の理解、そして証拠とともにどのようなポイントを起案の中で取り上げて評価するかという基本的な型が必要です。
また、証拠構造を念頭に置きつつ、事案の全体像から、特に無罪弁護において証拠と矛盾ない主張のストーリーを立論して最終弁論を起算することがポイントになります。
検察
検察は、起訴状における公訴事実記載の型と、客観証拠から供述証拠を検討する手順、そして各証拠ごとの位置づけや重みの評価ポイントを示すことが重要です。
二回試験の「地雷」ポイント5選
最後に、二回試験で「不可」になるリスクが高い地雷ポイントを、5つご紹介していきます。
原被告を逆にしてしまう(民弁) 危険度:★★★★
民事弁護では、訴状や準備書面の形式に則って答案を書く必要がありますが、原告と被告の立場を逆にしてしまうという初歩的なミスは、形式面で致命的な減点対象になる可能性があります。
※形式面だけで、書いてある内容は逆転していない場合であれば、善意に斟酌してもらえる可能性はあります。記載内容自体が立場逆転している場合だと、危険度が高いです。
たとえ法的な構成や論点の整理が適切であっても、当事者の記載が誤っていると、答案全体の信頼性が著しく損なわれ、「依頼者の立場に立った弁護活動ができない」と評価されかねません。
これは、特に時間に追われる本試験中に生じやすいミスであり、答案作成前に事案の読み込みと立場の整理をルーティン化することが予防策となります。
訴訟物の選択ミス(民裁) 危険度:★★★★
民事裁判科目では、訴訟物の選択が最初の重要判断になります。ここでミスをすると、後続の主張立証の論点展開が全てずれてしまい、答案の価値が実質的にゼロになりかねません。
なぜなら、設問が訴訟物を起点に設計されていて、訴訟物が想定されている回答筋とずれると、要件事実の構成などすべてがずれてしまう可能性があるためです。
たとえば、単なる金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権を保証契約に基づく保証債務履行請求権とした場合、事案の内容や設問の中で出てくる論点が全て抜け落ちたり、その後の法的構成や証拠の意味付けが全く異なってしまうため、評価がC以下に落ち込むこともあります。
二回試験では、「不可」になるリスクが高いです。
※あり得る訴訟物の選択であれば、善意に斟酌してもらえる余地は考えられますが、設問の配点がすべて落ちるようなミスになると、点数のつけようがなくなってしまうリスクがあります。
したがって、設問文から依頼者の要望や請求内容を正確に読み取り、訴訟物と要件事実を結びつけて答案を構成する習慣を日頃から鍛えておくことが不可欠です。
証拠検討が主観→客観(刑裁、検察) 危険度:★★★
刑事裁判や検察官の科目では、証拠に基づく事実認定が核心となりますが、「被告人の供述など主観的な証拠から出発して、その後に客観証拠をあてはめる」という構造は危険です。
作法は、常に客観証拠から供述証拠を検討する流れであり、証拠の重みや信用性の評価を通じて論理的に事実を認定する必要があります。
供述証拠先行型の起案は、仮に事案の筋をいち早く把握するため思考過程としては考えられますが、書面起案としての理解が不足しているとみなされる可能性があり、評価の伸び悩みに直結します。
証拠一覧から客観的な証拠・事実を抽出する訓練を、実務修習段階から意識的に行いましょう。
無罪弁護の事案を情状弁護にしてしまう(刑弁) 危険度:★★★★★
刑事弁護において最も危険なミスは、「無罪主張すべき事案を、情状弁護で処理してしまう」ことです。これは弁護人としての判断能力そのものを疑われる重大なミスです。
二回試験では、弁護人がどのような観点から弁護方針を立て、それをどのように構成したかが評価対象となります。
たとえば、被疑者がアリバイを主張しているにもかかわらず、「罪を認めたうえでの寛大な処分」を求めるような答案を書いた場合、依頼者の利益を理解していない、または軽視しているとみなされかねません。
そのため、答案作成前に事案の性質(無罪主張型か、量刑軽減型か)を正確に判断し、それに応じたストーリー構成を行う力が不可欠です。
特定答案(共通) 危険度:★★★
司法試験でもある、受験者が誰か特定できてしまう「特定答案」は、二回試験においても一定リスクがあるので、注意が必要です。
二回試験の起案では、例えば、1行おきに起案をする指示などがありますが、これを無視してしまった場合などが特定答案にあたる可能性があります。
※部分的にではなく、全体的に書いてしまった場合などが、特にリスクがあります。
まとめ
二回試験は、単なる法律知識の理解度を測る試験ではありません。実務家としての資質、法的思考の再現力、そして形式的な正確性を兼ね備えているかを評価する試験です。
本試験においては、「何を問われているか」を素早く把握し、それに正確に応じた答案を、整った構成と簡潔な文章で作成する能力が求められます。
修習中から以下の3点を意識して取り組むことで、合格の可能性は格段に高まります。
- 過年度のA答案を繰り返し読み、自分の答案との違いを比較すること
- 実務修習・集合修習での起案やフィードバックを活用すること
- 教官のコメントや講評から評価軸を抽象化すること
そして何より、「地雷」を踏まないようにするための基本的な確認作業や答案構成練習を欠かさず行うことが、合格のカギとなります。