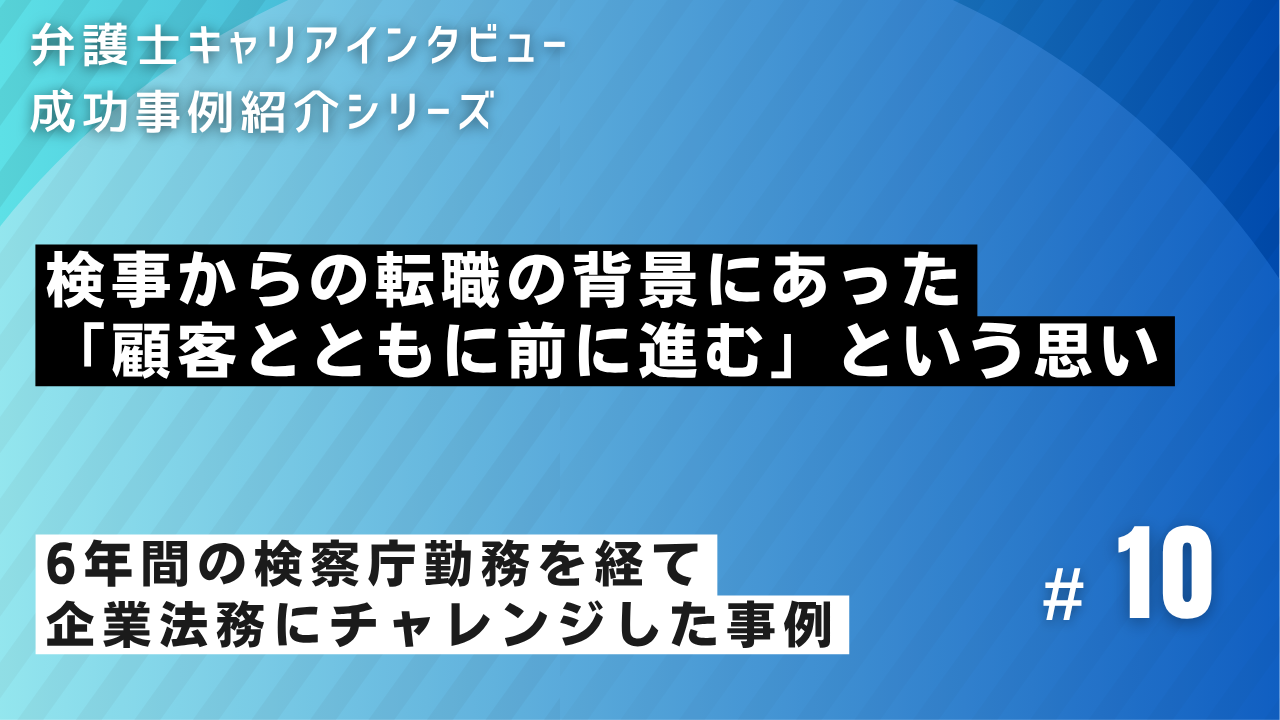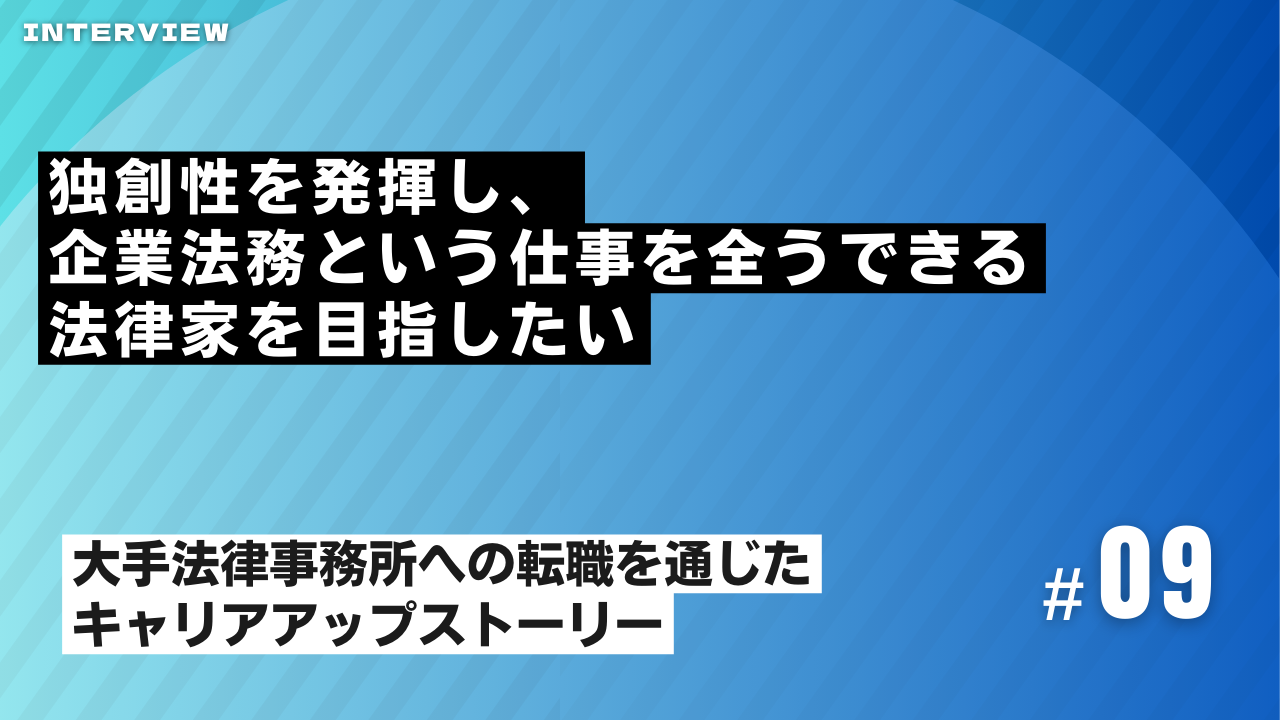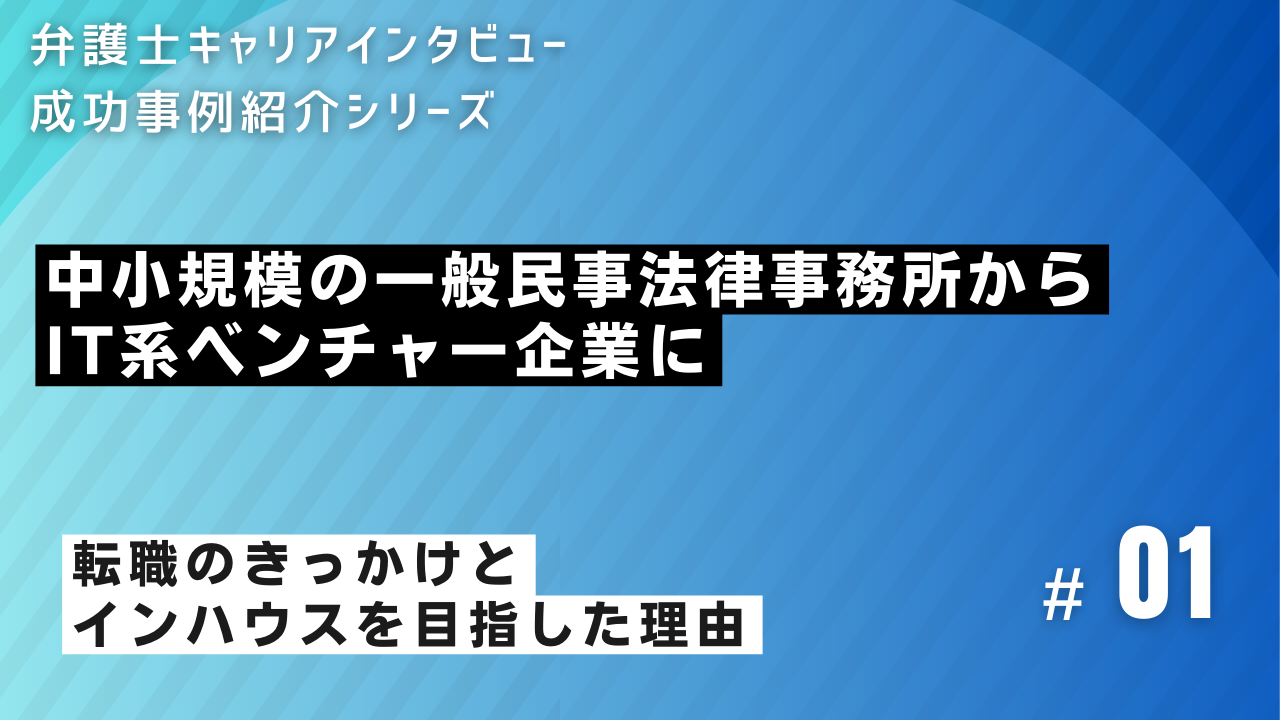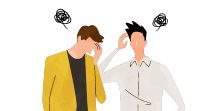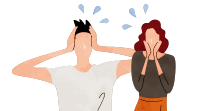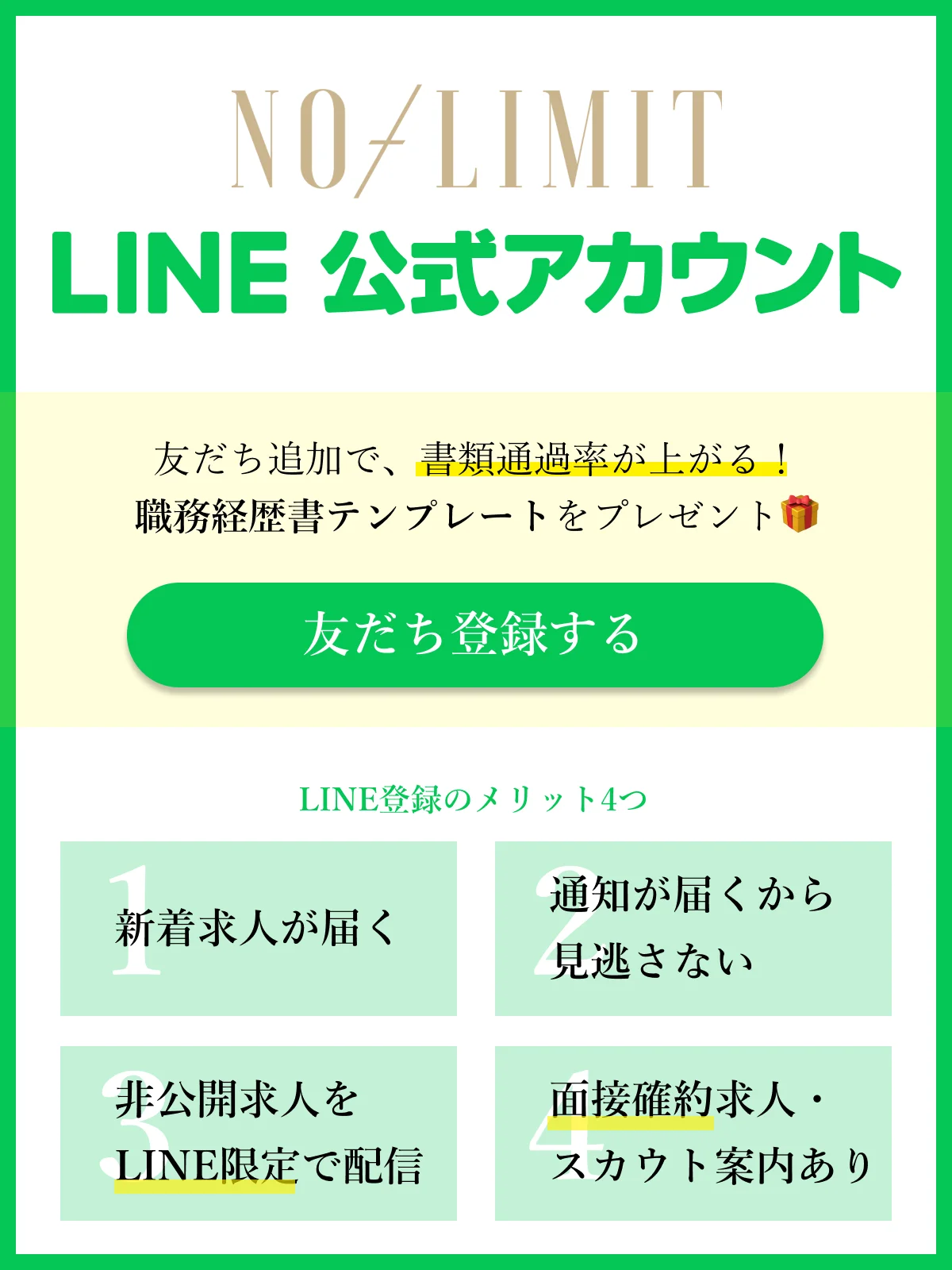弁護士登録からわずか10日でスタートアップに出向。
同期も前例もいない環境で、法務未経験の新人弁護士がどのように壁を乗り越えたのか。
若手弁護士のキャリアに一石を投じるリアルな奮闘記、前編です。
弁護士になって10日、志願のベンチャー出向
ロースクール生時代に見た弁護士の世界観への”違和感”
私は、大学に入学した時から弁護士を目指して勉強を始めました。
弁護士になろうと思ったのは、暴力を否定し、悲惨さをなくしたいという思いからです。
幼少期に泣き虫で引っ込み思案なのに、理不尽なことには負けたくない性格だったためか、よく同級生から暴力を振るわれたり、泣かされたりしていたのを覚えています。
しかし、喧嘩が強かったわけではなく、暴力で人を傷つけたり自分が傷つけられるのも嫌だったことから、報復したり対抗することはしなかったし、できませんでした。
それでも、勇気が出ない自分でも、自分の力でどうにか打ち勝てるようになりたい、、、そんな時に見出したのが、言論や知略で戦うことであり、「法律」というツールでした。
そんな原体験から、法律を駆使して様々な法律相談や訴訟対応、刑事弁護など、法律を駆使して困っている人を救う弁護士の仕事は、自分が目指すべき生き方だと思い至ったのです。
実際、法律の勉強を進めていく中で、法律の世界の楽しさと奥深さに没頭しました。
そこから、弁護士や司法の世界に立ち入っていく中で、実は法律の理想と限界の狭間にこそ解決すべき課題があるのではないかと思い始めました。
「2割司法」という言葉もありますが、既存の司法システムで解決できない課題が少なくないことも事実です。
また、当時の私は、弁護士の業務領域が限定的に語られていることに、少しもったいなさを感じていました。
法律家が身に着けるリーガルマインドも、ステークホルダーを整理することや、解決すべき課題の特定、仮説を定立してあてはめて結論を出す、結論の妥当性を欠くなら修正して検証していく、などに抽象化すれば「司法」という領域だけでなく、よりあらゆるビジネスの領域に根付いてサービスを創出する思考フレームとして転用していけるのではないかと考えるようになりました。
さらに、AI、Web3、IoT、デジタルツインなど、テクノロジーの進化によって社会の構造が進展していく中で、法整備が追いついていない新領域が次々と出現していく変化のど真ん中にこそ、リーガルの視点が求められていると考えていたのです。
ひいては、アナログな司法システムも根本的に変わっていくのではないか、そうなったときにリーガルサービスというものの価値がどのように社会から求められるのかを考えるようになりました。
このように掘り下げていったときに、自分がやりたいことが果たして今まで自分が思い描いていた「弁護士」なのかと違和感を感じ、何かもっと別のアプローチで「法律をどう使うか」を考えるべきではないかと考えるようになったのです。
ビジネスパーソンとしてリーガルサービスを再構築したい
それまで法律の勉強に多くの時間を割いてきましたが、完全にビジネスサイドのポジションでリーガルサービスを俯瞰したい、ビジネスを学びたいと思い、司法試験を受験した直後、就活と同時に速攻でベンチャー企業でのインターンに応募しました。
数ある中から、法律メディアや法務人材紹介エージェント事業を手掛けるASIROさんにお引き合いをいただくことができました。
マーケターとして、特にWebマーケティングを中心に広告運用やSEO、SNSマーケに関する業務に携わりました。
6か月のインターン期間の中で、「弁護士であること」だけでは間違いなく生き残れないこと、従来の弁護士のキャリアとは異なる分野や弁護士がやらないことに取り組むこと、そして前例のないことにチャレンジする重要性を学びました。
肩書きは一つの専門性に過ぎず、本質的には、既存の枠組みや領域から離れ、自分にしかできないフィールドにフォーカスする戦略が重要であると考えるようになったのです。
そこで、単にリーガルパーソンとしてリーガルサービスを提供する立場になるのではなく、ビジネスパーソンとしての軸足でリーガルサービスのあり方を問い直すことを考えました。
企業活動の最前線に入り込み、リスクを適切にコントロールしつつ、事業を前に進める法務。
そのような存在を目指したいと考えたのです。そしてその思いは、「インハウスロイヤー」や「スタートアップ法務」への関心へとつながっていきました。
司法修習前後「2回」の就活を経て出向へ
インターン期間中、私が考えていた様々な課題感や、やりたいことを軸に就職活動をしていましたが、なかなか内定をいただくことができませんでした。
そんな中で、私の大学時代の先輩が所属する名古屋市の旭合同法律事務所にお声掛けをいただき、ちょうど修習直前のタイミングで内定となりました。
街弁の事務所で、私自身が取り組みたいビジネスサイドの法務は、メインの分野ではありませんでした。
しかし、「あなたの思い描く挑戦やキャリアに思う存分取り組んでほしいし、それを支援したい。」との所長の言葉から、入所を決めました。
その後、修習期間に入り、法律家としての専門性を軸にしつつどのようにして前例のないことに取り組むかを考えていたとき、「1年目で、しかも入所とほぼ同時に出向するのはどうか」と思い至りました。
その理由は大きく2つありました。
1つは、単に「普通誰もそんなことしないだろう」という発想です。
2つ目は、ビジネスパーソンとしての軸でリーガルサービスをあり方を問い直し新しいリーガルサービスを再構築するという目的に立ち返り、ビジネスサイドに一歩目から飛び込むべきだと考えたためです。
そこで、ドキドキしながら、私は、所長と副所長に相談しました。
そもそも入所してすぐに企業出向するなど、内定先の事務所からすればほぼ採用の意味がなくなってしまうため、即却下されてしまうのではないか、生意気すぎて内定を取り消されてしまうことにならないかと。
しかし、なんと思いの外「ぜひやってみなさい」と快諾。背中を押していただきました。
ただし、出向先を手配できるわけではないので、自分の力で切り拓けるのであれば、とのことでした。
私はすでに決心をしていたので、もちろん自分の力で出向先を確保しようと思いました。
それが「2度目の就活」です。
30社〜40社ほど、法務の募集に応募する中で、門前払いもしくは面接の段階に至っても「前例がなく難しい」「受入体制が作れない」「基本的に自走力が必要になるが、それが担保されるかが不透明」といった理由で通りませんでした。
それもそのはず、私が条件としていたのが
- 入所予定先への在籍を前提にすること(在籍出向)
- 法務機能・組織が発展途上のベンチャー企業であること
- 弁護士として個人受任もできること
の3つがあったためです。
そもそも①と②を両立することは困難で、さらにインハウスの働き方でも決して多くない③の条件も付加されているという、今考えればミスマッチ要素しかなく無謀すぎると思います。
そんな中で、私を引き入れて下さったのが、株式会社キッズラインでした。
キッズラインは、「日本にベビーシッターの文化を」「家事代行を当たり前に」をミッションとして、個人事業主のシッター・家事代行事業者と、保護者・ユーザーをマッチングするサービス等を展開し、まさに先進的な領域で社会課題の解決に挑む会社で、志向と合致しました。
そして、代表の経沢香保子さんは女性として最年少で東証マザーズへの上場を果たした著名な起業家、かつ法務コンプライアンスを管掌している別所直哉さんはヤフー株式会社(当時)の法務のトップを経て、現在ロビィングコンサルティング会社を経営され数々の法改正にも携わったルールメイキングのエキスパートであることから、得られる経験や学びは計り知れないと思い、入社をすることを決めました。
そして、入社は弁護士登録をしてから「10日後」と決めました。
通常の新人弁護士のキャリアは、まずは事務所内で案件の進め方や弁護士としての基礎を学ぶ時期です。
ベンチャー企業のインハウスで、必ずしも新人弁護士の収入には及ばないかもしれない、しかし、私は「今すぐ行くべきだ」と本気で思っていました。
法務の現場で実践的に学べることに加え、事業と法務が一体となって動く現場を肌で感じられること、「弁護士」になる前にその環境に飛び込むことこそが、私にとっての最初の「挑戦」の場だったのです。
こうして、司法修習後に弁護士登録をしたのち、わずか10日でベンチャー企業に出向し、インハウスロイヤーとしてのキャリアを歩み始めることになりました。
いきなりインハウスに、しかも出向することへの不安
確たる決意と覚悟をもって踏み出した弁護士としてのスタートでしたが、不安だらけでした。
相談できる同期などはいない
まだ一人で案件を持ったこともなければ、企業の法務部門がどう動いているのかすら知らない状態でした。
そんな私にとって、最も大きな不安の一つは、「相談できる同期がいない」という状況でした。
通常であれば、同じタイミングで事務所に入所した同期たちと日々の学びを共有したり、「これってどうやって対応するの?」とざっくばらんに聞き合ったりすることができます。
しかし、私は出向先に単身で入り、同じような立場の若手弁護士もいなければ、その場で相談できる先輩弁護士がいるわけでもありませんでした。
「これってどうしたらいいんだろう…」「自分の役割で対応してよいのか…?」そんな迷いを感じても、気軽に話せる相手がいないことに、初期はとても苦労しました。
上長には「弁護士」として直接のロールモデルがいない
出向先には法務機能がすでに存在していたものの、そこには弁護士資格を持つメンバーはいませんでした。
つまり、法的な専門知識の相談や、訴訟対応を想定したリスク感覚のすり合わせができる“先輩弁護士”がいないという状況でした。
たとえば、契約書レビューを一つ取っても、単にリスクを指摘するだけでは意味がありません。
事業の現実を踏まえ、「この程度であればリスクを取ってもよいのか」「どこまでが交渉余地なのか」といった判断が求められます。
しかし当時の私は、そうした判断の基準を自分一人で持ちきれず、誰かに背中を押してほしいと感じる場面も多くありました。
社内には頼れるビジネスの先輩はいても、「弁護士」としてのメンタリングをしてくれる存在はいない。
そのギャップに何度も不安を感じました。
そんな中、一番のメンターとなったのが別所さんでした。
法律の専門知識も弁護士以上で、企業法務の第一銭での多大な経験からのアドバイスやフィードバックを通じて、ビジネスのバランス感覚を前提にリーガルリスクを最適にコントロールするための基礎を徹底的に浸透させていくことができました。
ファーストキャリアとしてあまりに博打な要素しかない
一般的な弁護士のキャリアは、最初の1〜2年で基礎的な業務を身につけ、先輩弁護士の指導を受けながらスキルを磨いていくという段階を経ます。
しかし私の場合、その「助走期間」がまったくありませんでした。
目の前にあるのは、スピード感のある事業と、目まぐるしく変化するプロジェクト、そして誰も教えてくれない法律問題の山。
もちろん、出向元の事務所には定期的に報告をし、必要があればサポートも受けられる体制はありました。
しかし、現場での判断はすべて自分に委ねられており、トラブルがあっても、最初の対応はまず自分が担うことになります。
「弁護士としての自分は、これで合っているのか?」
「この判断が、将来的に大きなリスクにつながったらどうしよう?」
そうしたプレッシャーは常に付きまとっていました。
キャリアの入口として、インハウスしかもベンチャーというフィールドに出ることは、客観的に見れば極めてリスクの高い選択だったと思います。
それでも私がこの道を選んだのは、「リスクの中にしか、得られない学びがある」と信じていたからです。
もちろん、その選択の重みを痛感する瞬間は多々ありましたが、今振り返ると、あの時に「安全な道」ではなく「挑戦の道」を選んだことが、後のキャリア形成にとって大きな意味を持つことになったと感じています。
入社3か月での3つの壁
ビジネスパーソンとしての壁
出向して最初の3か月で、私がまず痛感したのは「ビジネスパーソン」としての未熟さでした。
弁護士としてのスキル以前に、社会人経験自体が未熟だった私にとって、「メールの書き方」から「Slackでの報連相」まで、すべてが初体験でした。
そうかといって、大手企業のように充実した研修があるわけではなく、とにかくOJTで、場数を踏んで多くのフィードバックを受けることがすべてでした。
たとえば、初めて担当した契約書レビューで、私が相手方の不備を詳細に指摘したところ、「もう少し事業サイドに寄り添った交渉のアドバイスをくれないか」と社内のメンバーに指摘されたことがありました。
法的には正しいことを言っているつもりでも、事業を推進していくことの目的やバランスを失念すると、社内外の信頼を損ねる可能性があることを学びました。
また、会議での発言の仕方にも苦労しました。話のテンポが速く、略語や業界用語も飛び交う中で、内容を理解しながら適切なタイミングで発言するのは至難の業でした。
多くの人とのコミュニケーションやすり合わせ、キーマンを見抜いて社内のコンセンサスを得ることなども1つ1つを勉強していく必要がありました。
「弁護士だから」ではなく、「一人の職員として」評価される厳しさに直面したのは、この頃でした。
法律知識に頼るだけでは通用しない。「社会人1年目」としての基礎を固める必要性を痛感した3か月でした。
弁護士ではなく企業内の「法務パーソン」としての壁
次にぶつかったのは、「弁護士」としての自負と、「法務パーソン」としての役割とのギャップでした。
出向前の私は、「弁護士である自分」が専門家として社内の信頼を得ることを当然視していました。
ところが実際には、社内のメンバーにとって「弁護士資格の有無」はほとんど重要ではなかったのです。
それよりも求められていたのは、「現場が必要とするタイミングで、必要な情報をわかりやすく届けてくれる人かどうか」という実務家としての信頼でした。
「法律的にはNGですが、事業的にはどうしましょう?」
「この施策、どの程度までならリスクを取れますか?」
そういった問いに対して、「原則的には~」と答えるだけでは全く足りません。
社内で求められているのは、“答え”ではなく“方針を決めるための選択肢”であり、時に“ビジネス上の決断を後押しする言葉”でした。
これは、法的な正しさを最優先にしていた自分にとって、大きな価値観の転換でした。
出向初期は、法務の存在意義を「リスクを潰す人」として捉えられてしまうことが多く、どうすれば信頼される「推進者」になれるのかを日々悩んでいました。
「正しいことを言っているのに、なぜ納得してもらえないのか」と感じた経験は、今でもよく覚えています。
キャリアイメージとのギャップの壁
そして、もう一つの大きな壁は、「描いていたキャリアとのギャップ」でした。
ロースクール時代から、自分は“ビジネスに強い弁護士”を目指していると思っていました。
しかし、実際にビジネスの現場に飛び込んでみると、理想としていた「活躍する姿」とは程遠い自分がそこにいました。
M&Aやファイナンスの案件など企業法務の花形のようなものに関わるのではなく、温度感が高いクレームへの対応、契約書のほか公的な書類について「てにをは」など体裁レベルの不備のチェック、リサーチペーパーのまとめなどが中心でした。
どちらかというと守りの法務が中心で、「事業の推進に役立っているのか」「足を引っ張っていないか」と不安になる日々が続きました。
また、周囲の同期弁護士たちが事務所内で基礎を固め、大型の訴訟などの案件を数多く経験しながら順調に成長していく姿を見ると、自分だけが“道を外れてしまった”ような感覚にも陥りました。
一般的なキャリアパスと違いすぎる選択をしたことに対する、迷いや焦りが芽生えたのもこの時期です。
ただ、そのときに自分を支えたのは、「この不安もすべて、キャリアの糧になる」という信念でした。
当時の自分には、目立つような成果や大きく目に見えて分かる案件の解決実績のようなものもありませんでしたが、「この場所でしか得られない経験がある」と信じていました。
そして、後になってわかったのは、まさにこの“壁の連続”こそが、他では得られない実践知を育ててくれていた、ということです。
担当していた主な業務
ジェネコ
出向して最初に任された業務の一つが、いわゆる「ジェネコ」、つまりジェネラルコーポレート領域の対応でした。
具体的には、法務相談対応を中心として、社内規程の整備と運用、会議体の運営、登記対応、株式に関する文書のチェックなど、コーポレート・ガバナンスの基礎を支える業務です。
会議体の運営や手続的な業務は、とにかくミスがないことが求められます。議事録1つとっても、一言一句の正確性に神経を払う必要があります。
そして、法務相談対応が、基本的かつ最も日常的な業務です。法務相談では、ファクトチェックの重要性を学びました。レビューや判断に必要な情報について、基本的にはデータベース上で管理されていることから、可能な限り自分自身で収集して確かめにいくことを徹底しました。
また、相談者の社員から順序立てて必要な情報を聞きお互いに案件のポイントを整理するように心がけていました。
また、プロジェクト全体の中で占める位置づけや期限がある中で、すべての論点について100%の回答をすることは不可能です。
そのため、複雑な論点がある場合は、リスクが顕在化した場合の影響度が最も高いものから優先順位をつけ、一般的な相場で対応するものと、特に深掘りをして検証すべき論点に対する回答に精度を持たせるようにしていました。
様々な種類の相談がある中で、法的に正確な見解を求めているものだけでなく、数ある選択肢から最善のリスク判断を提示すべきもの、時にはセオリー通りに進めては不可能であることを前提に突破可能なアプローチとロジックを組み立てることも求められます。
いずれも、1つ1つの案件のゴール・目的を見失わないこと、そして事業判断としてどのような解が求められるのかという視座が必要です。
契約法務
契約法務は、業務委託契約や秘密保持契約(NDA)はもちろん、SaaSやサブスクリプションモデルに関連する利用規約、資本提携に伴う投資契約など、多岐にわたる契約に携わりました。
契約法務は、スピードと柔軟性が重視されます。
そのため、「完璧な契約を目指すよりも、事業の進行を止めない範囲で、リスクの解消と受容のバランスを最適化する」という思考が求められました。
とはいえ、新人弁護士だった私は「どのようなリスクを排除し、どこまでが許容できるリスクなのか」の判断がつかず、とにかく最初のころは契約書の“細部”にばかり目が向いてしまっていました。
「重要なことは、問題がないことの保証ではなく、“問題が起きそうなところを見抜き、どのようなリスクがどのように起こりうるのか、リスクの影響度や性質を正しく伝えて、受容できるのか排除すべきなのかを提示すること。事業サイドが交渉で行き詰まっている際に適切な代替案も提示することです。」
ある日、上長の別所さんからそう言われたとき、契約レビューの本質を突かれたような気がしました。
以降は、ただリスクを列挙するのではなく、「対応可能な修正案を提示する」「事業部の判断を促す選択肢を添える」といった“前に進めるための法務”を意識するようになりました。
トラブル対応
CtoCのマッチングサービスのため、利用者同士の法的トラブルへの対応も、任されるようになっていきました。
たとえば、顧客からのクレーム対応や、代理人弁護士から会社側に対して行ってくる交渉の対応などです。
これらの案件では、毅然と「法的にはこうすべきです」と対応することも重要である反面、カスタマーサポートやビジネスとしての落とし所の付け方など、非常に繊細な対応が求められました。
たとえば、あるクレーム案件では、対応を間違えればSNSで炎上するリスクがありました。
事業部門からは迅速な判断を求められる一方、法的には曖昧な論点も多く、当時の私は非常に悩みました。
最終的には、関連資料を洗い出し、類似事例を分析したうえで、社内向けに「選択肢とそのリスク、想定される結果」を整理して提示しました。
その時に「現場と一緒に考えてくれる法務」として感謝されたことが、大きな自信につながりました。
省庁渉外や事務局対応
キッズラインの事業は、政策課題と直結していること、先進的な事業領域で法律も整備途上にあること、そして子どもの生命や心身の安全確保のため行政との連携が不可欠な業界に属しています。
そのため、所管省庁との渉外や、業界団体との事務局業務も担当することになりました。
保育の現場で重大な怪我や事故が発生した場合の報告対応、法令やガイドラインの解釈確認、行政からの文書照会への回答など、通常の企業法務とは一味違う「政策的な法務」の現場にも携わります。
あるプロジェクトでは、消費者庁に特定商取引法上の規制の適用範囲外であることの回答を得るために、施策の座組を詳細に検証し、事業サイドと綿密にロジックを組み立てながら必要な回答を得る準備を入念に行いました。
その上で、事前照会を行った結果、意図した回答を引き出すことができました。
行政対応には“公式見解”としての重みがあるからこそ、一言一句のニュアンスが非常に重要です。
弁護士としての論理性だけではなく、社内外に通じる「言葉の設計力」が求められる業務であり、自分の視野が一段と広がったように感じました。
新人としての悩みや失敗
前編の最後に、私の弁護士1年目の悩みや失敗について、3つお話したいと思います。
コミュニケーションや調整の仕方
出向して間もない頃、最も苦労したのは「社内でのコミュニケーションと調整」でした。
法律事務所のように、案件ベースで明確に役割分担がされているわけではなく、社内ではプロジェクトごとに流動的に関係者が決まり、意思決定のルートも日によって変わることがありました。
私が法務として懸念点を伝えたつもりでも、関係者に十分共有されていなかったり、逆に「そんな話は聞いていない」と言われてしまうこともありました。
また、調整ごとの連絡手段もさまざまで、SlackでDMを送るのか、チャンネルでオープンにするのか、タスク管理の一元化だけで足りるのか、ミーティングで口頭で伝えるのか……その“使い分け”ができていなかった時期は、情報が錯綜し、対応が後手に回ることがありました。
こうした苦い経験を通じて、「伝えるべき相手を正確に見極めること」「相手の時間を奪わずに、必要な情報を過不足なく伝える技術」が重要であることを学びました。
今では、相手の職種や忙しさに応じて伝え方を変えることを意識していますが、当時はとにかく場数を踏みながら試行錯誤の連続でした。
法務としての発言の重みと責任
法務担当として会議に出席していると、「それって、違法じゃないですか?」「この文言ってリスクありますよね?」といった確認が突然振られることがあります。
最初の頃は、自信がなくても反射的に答えてしまったり、逆に慎重になりすぎて場を止めてしまったりと、バランスが非常に難しかったです。
弁護士としての立場から、曖昧なことは言えないというプレッシャーがある一方で、事業サイドは「即答」を求めてきます。
このギャップをどう埋めるかは、私にとって大きな課題でした。
あるとき、私がある規制の解釈について、事業サイドが急いでいた案件でもあったことから、仮説ベースではありましたが1,2のソースがあることを前提に「大丈夫だと思います」と回答をしたことがありました。
しかし、当局確認をする前であったことから、明確な裏付けがあったわけではありませんでした。
そこで、すぐに顧問先法律事務所や当局への念押しの確認を行い、仮説の裏付けができたのですが、あのときの焦りと反省は今でも鮮明に覚えています。
それ以来、私は「法務の見解として言うこと」「個人の仮説として話すこと」を明確に区別し、わからないことはその場で保留にする勇気を持つようになりました。
「すぐに答えること」よりも、「確実に守るべき一線を見極めること」が、法務における信頼につながるのだと実感しました。
ヒアリング
事業部門からの相談や契約の背景事情をヒアリングする場面でも、最初は苦戦しました。
聞くべきことをうまく引き出せなかったり、専門用語を遠慮して聞き返せなかったりと、コミュニケーションの基本ができていなかったのです。
そうした経験を通じて、私は「ヒアリングは事前準備が9割」だという考えに至りました。
契約書の内容だけでなく、関連するSlackのやり取りや、社内Wikiの情報、これまでの経緯をできるだけ読み込んだうえで、「何を知りたいのか」を明確にしてから話を聞くようにしました。
ヒアリング力は、契約の意図を正確に汲み取り、的確なレビューやアドバイスを行うための土台です。
今でもまだ学びの途中ですが、当時の失敗がその重要性を教えてくれました。
意図の汲み取り方と伝え方
弁護士としての「伝える力」には自信があるつもりでしたが、企業の中ではそれだけでは足りませんでした。
法的に正しいことを伝えても、相手の業務や立場を無視していれば、全く届かないことがあるのです。
たとえば、あるプロダクトのリリース時期が迫っている状況で、私が「この契約は再交渉が必要だと思います」と伝えたとき、「それは法務として言っているの?それとも、ビジネス的にも再交渉が必要という判断なの?」と詰められたことがありました。
私は法的リスクの観点で発言していたつもりでしたが、それが伝わっていなかったのです。
このとき、相手が何を聞きたいのかを理解し、その前提で「何を、どう伝えるか」を考え抜くことの重要性を思い知らされました。
それ以降は、発言の際には前提と立場を明示するようになりました。
たとえば、「これは法務の観点ではリスクがあると考えますが、事業側でリスクを許容するならこの条件で進めることも可能です」といった形で、“判断材料”としての情報提供に徹するようにしました。
様々な交渉での主導権の握り方
新人のうちは、外部とのやり取りでも「弁護士」という立場に遠慮してしまうことがありました。
とりわけ、契約交渉の場面では、自分の意見をどう出せばよいのか分からず、相手のペースに呑まれてしまうことがありました。
社内でも「法務に同席してほしい」と声がかかる一方で、実際に交渉の場では発言のタイミングを掴めず、何もできなかったこともありました。
「ただ座っているだけの法務」となってしまった反省が、いくつもあります。
転機となったのは、ある取引先との契約交渉で、事前に想定質問と回答方針を自分でまとめ、社内の事業責任者と一緒に準備をした場面です。
その交渉では、相手の主張を受けつつも、こちらの譲れないラインを明確に伝えることができ、最終的に納得感のある着地を得ることができました。
交渉で主導権を握るというのは、声を大にして反論することではありません。
適切で入念な準備と冷静な対話によって、相手の立場とこちらのリスクを両立させるための「筋道」を示すことだと、今では感じています。
前編のまとめ
弁護士登録からわずか10日で飛び込んだベンチャー企業のインハウスの現場は、想像していた以上に厳しく、そして予想以上に学びに満ちた環境でした。
出向の初期は、社内での立ち位置すら定まらず、自分の存在価値に自信が持てない日々が続きました。
「弁護士」としての専門性を発揮しようとしても、実務の流れや社内事情を理解していなければ、机上の正論に終わってしまいます。
一方で、「新人」としての自分には、わからないことを素直に聞く勇気も必要でした。
この3か月間で直面したのは、法律知識だけでは乗り越えられない多くの“壁”でした。
ビジネスの流れに乗る力、社内外の関係者との調整力、情報を咀嚼して伝える力、そして何よりも「自分で考えて動く覚悟」が求められました。
正直なところ、失敗や後悔の連続でした。「もっと上手くできたのではないか」と思う場面も数えきれません。
それでも、ゼロから積み上げていく過程で、「法務として信頼される存在になるために必要なこと」が少しずつ見えてきた気がします。
この“濃密すぎる”初期フェーズを経て、私はようやく「自分はこの会社の中で、何を提供できるのか」という問いに向き合えるようになっていきました。
そして出向から半年、1年と経つ中で、私はさらに大きな役割を担うことになります。
法務チームを率いる立場として、事業の意思決定に深く関与し、自らチームを育て、社内の法務機能を拡張していく——。
後編では、こうした「リーダーとしての成長の過程」と、出向3年目を迎えた今だからこそ見えてきた「ベンチャー法務の魅力と現実」についてお伝えしていきます。
ベンチャー法務に興味がある方、若手弁護士としてキャリアに迷っている方、そして「弁護士」という枠を超えて社会に関わる方法を模索している方にとって、少しでもヒントになるような経験を共有できればと思います。
弁護士の求人紹介・転職相談はこちら