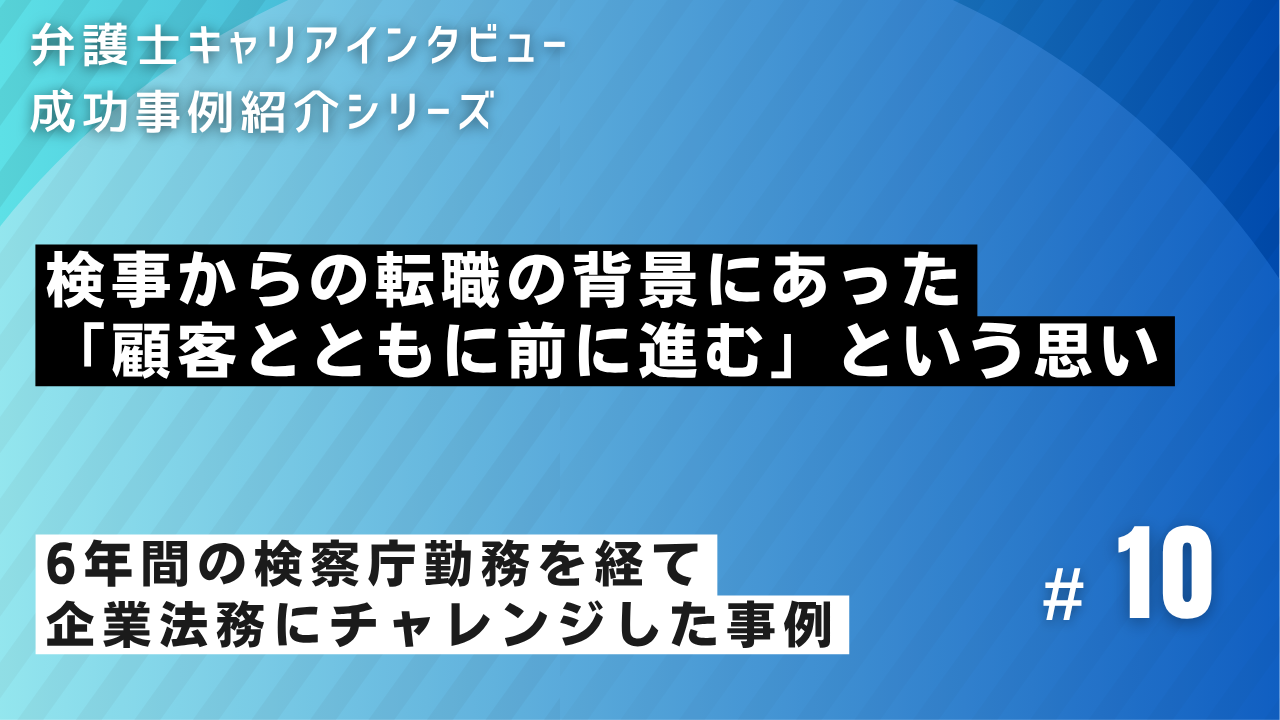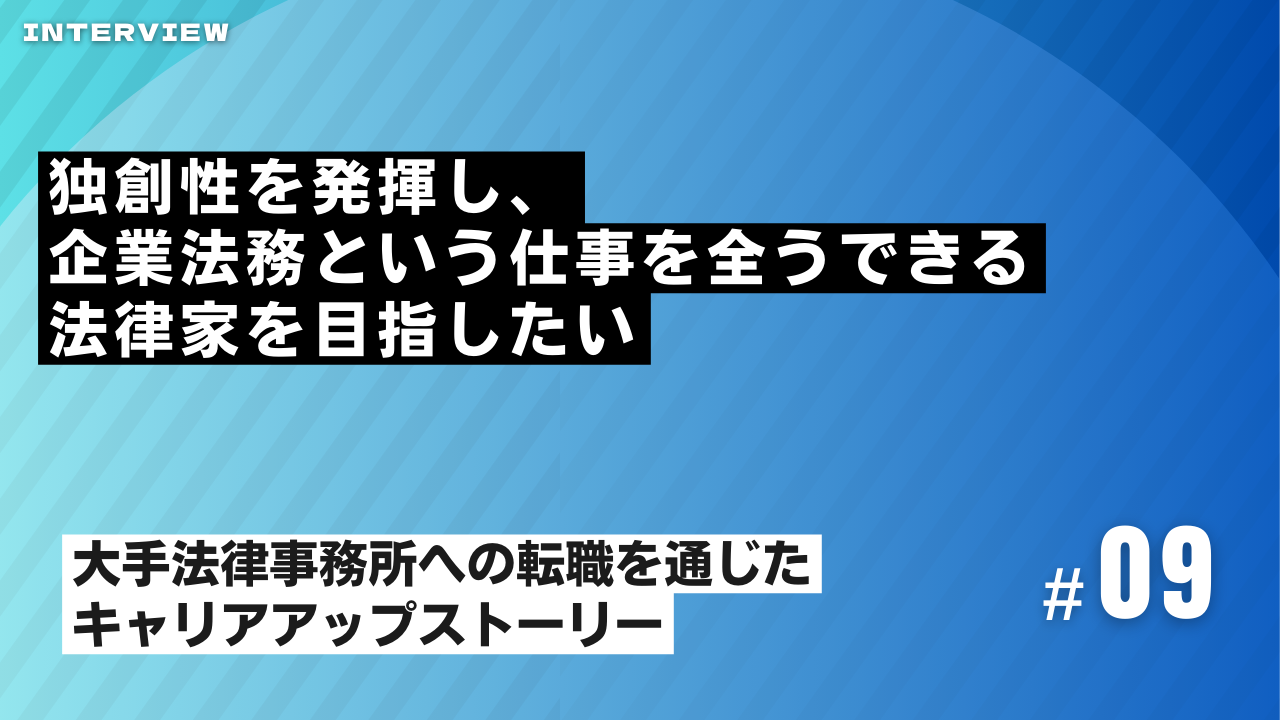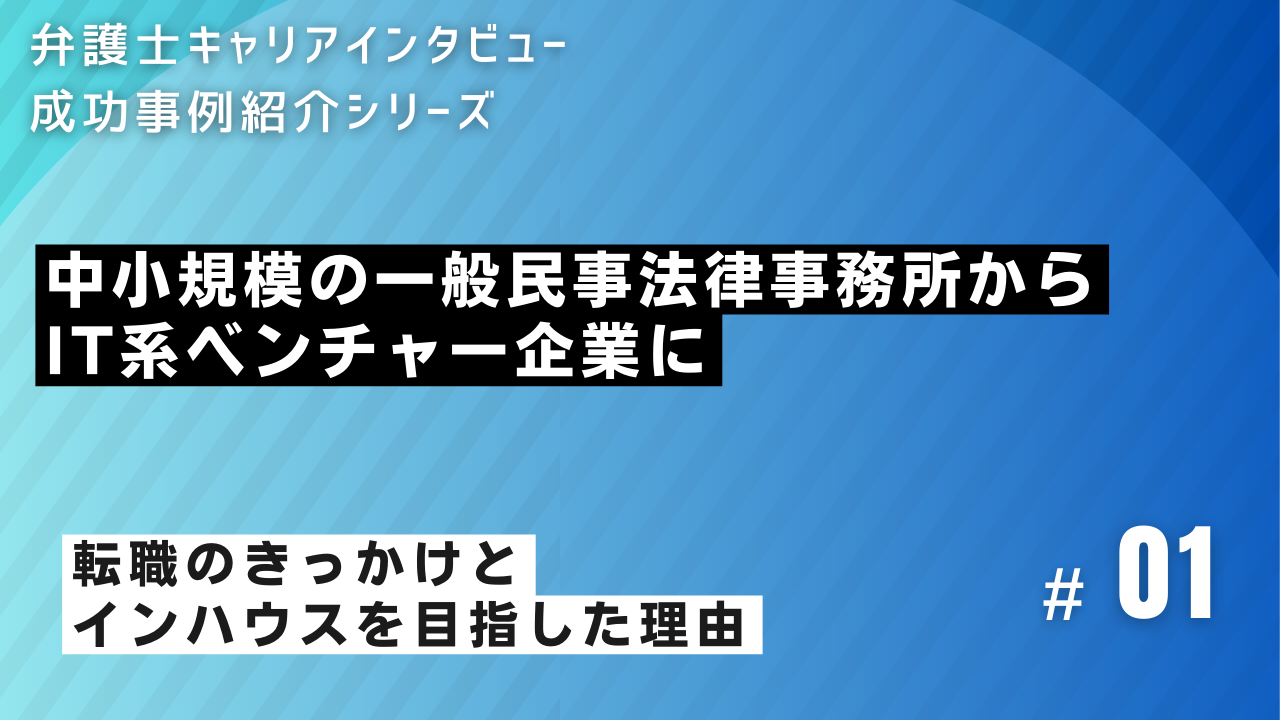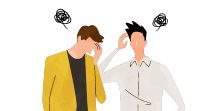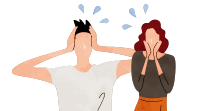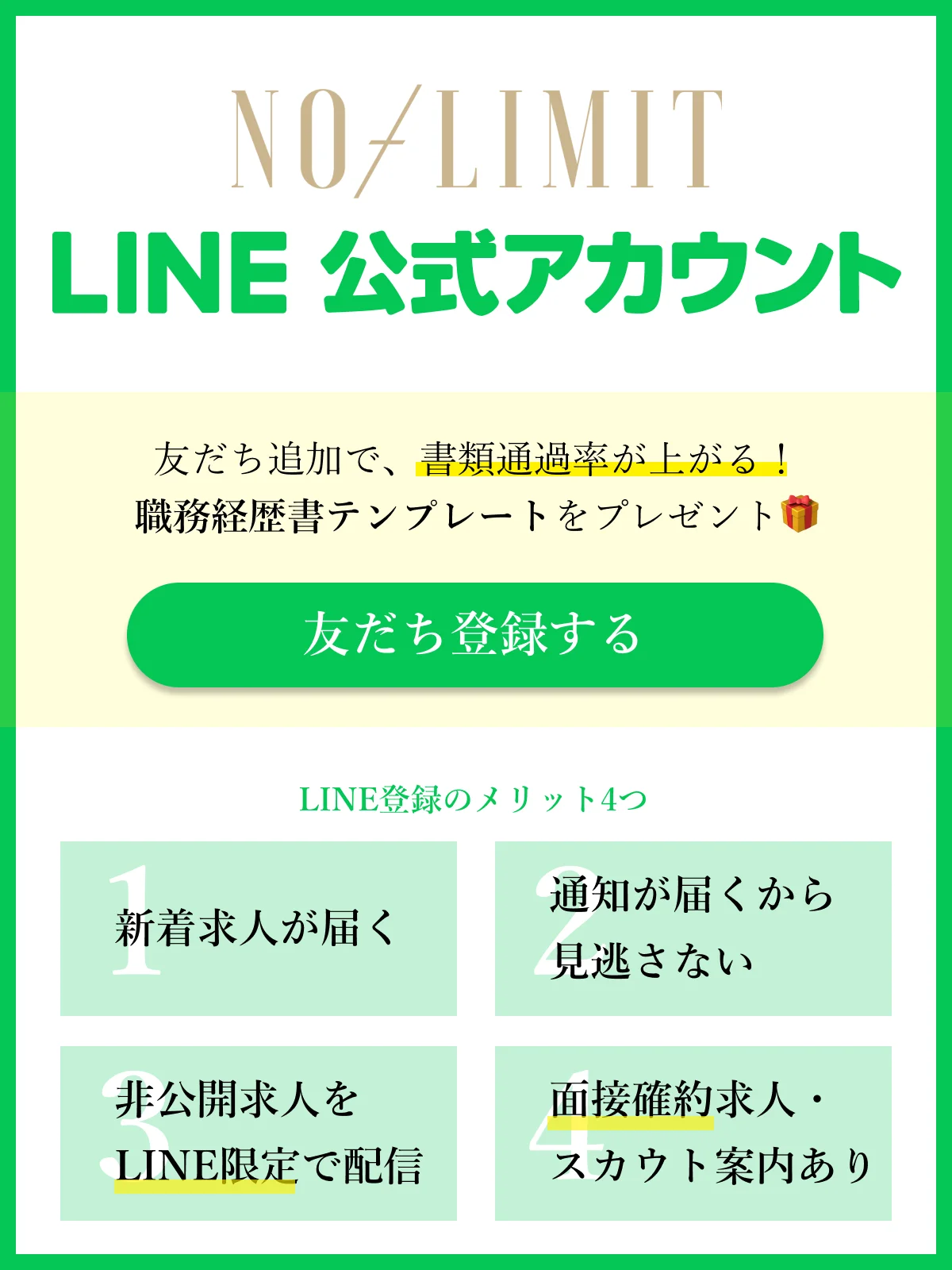「弁護士は忙しくて休みなんてないんじゃないか」というイメージをお持ちの方は多いかもしれません。
実際、法律事務所で働く弁護士は担当案件のスケジュールに追われ、休日どころか深夜や早朝に仕事をするケースも珍しくありません。
しかし、全員がそういった“常に仕事漬け”というわけではなく、勤務先や働き方によってはしっかりと休日を確保し、プライベートを充実させることも可能です。
近年では、働き方改革や法曹人口の増加などもあり、弁護士のワークライフバランスに対する関心が高まっています。
本記事では、「弁護士の休日はいつなのか?」という基本的な疑問から、所属形態や働き方による休日の違い、さらには具体的な休日の過ごし方や休日を確保するための工夫を解説します。
実際に弁護士として10年程度のキャリアを持ち、プライベートの時間もしっかり楽しんできた筆者の経験も交えつつ、弁護士のリアルな休日事情を幅広くお伝えします。
弁護士の休日はいつになる?
弁護士にとって「休日」とは、文字通り仕事をせずに“休む日”を指します。
しかし、一般的な会社員とは異なり、明確に「土日祝日が休み」というルールがあるわけではありません。
ここでは、弁護士がどのようにして休日を設定しているのか、またはどのような形で“休日”と呼べる時間を確保しているのかを見ていきましょう。
土日や祝日休みという概念はない
弁護士には「土日祝日が定休日」という厳密な制度がありません。
もちろん、多くの法律事務所が土日祝日を基本的に“閉所”としている場合もありますが、それはあくまでも「事務所として対応しない時間帯を設ける」という運用に近く、弁護士自身が必ずしも休めるとは限りません。
たとえば、訴訟案件の準備やクライアントへの回答が切迫している場合には、土日でも資料作りやリサーチ、文書作成に追われることがあります。
また、緊急性の高い刑事案件や企業の不祥事対応などでは、祝日や深夜に連絡がくることも珍しくありません。
つまり、世間一般でいう「土日祝日は休み」という働き方とは、ややかけ離れているのが実情です。
平日でも休める!
一方で、「平日はずっと仕事で、土日祝日も働いている」というわけではありません。
むしろ、弁護士が平日を休みにすることは意外に珍しくありません。
案件の山場が終わり、裁判期日やクライアントとの打ち合わせが入っていない平日を使って、あえて休むケースがあるのです。
特に、裁判所は基本的に平日の昼間しか期日が開かれませんし、多くのクライアントも平日の日中で打ち合わせを希望します。
逆にいうと、そのスケジュールさえ調整できれば、平日を“オフ”として活用することも十分可能です。
これは他業界のシフト勤務やフレックス勤務にも通じるものがあり、混雑が少ない平日に旅行やショッピングを楽しむ弁護士もいます。
所属先や勤務形態などによっても異なる
弁護士の休日は、実は所属形態や勤務スタイルによって大きく異なります。
弁護士の多くは法律事務所に所属していますが、その中でも「勤務弁護士」「パートナー弁護士」など役職的な違いがありますし、最近増えている「インハウスローヤー(企業内弁護士)」の場合は企業の休日スケジュールが適用されるケースもあります。
また、独立開業している弁護士であれば、自分の裁量で休日を決めやすい反面、案件を受けすぎると全く休めないという事態にもなりかねません。
それらの点については、次の章で詳しく解説します。
弁護士の求人紹介・転職相談はこちら
所属形態や働き方などによる弁護士の休日の違い
一口に「弁護士」といっても、さまざまな所属形態や働き方があります。
法律事務所でも、大規模事務所から数名程度の小規模事務所まで幅広く、また企業や官公庁でのインハウスローヤーという道も一般的になってきました。
こうした違いが、休日の取り方や過ごし方にも反映されます。
法律事務所(勤務弁護士)
勤務弁護士とは、いわば「サラリーマン弁護士」のような位置づけです。
事務所との業務委託契約(※)に基づき、働くパターンです。休日の取りやすさなどは、事務所の方針にも左右されます。
※一部の事務所では雇用契約の形態もある
多くの場合、裁判所が土日休みであることに合わせて、事務所の基本的な休日も土日であることが多いですが、担当案件が立て込んでいるときや顧客対応が必要なときには、土日でも仕事をすることがあります。
また、大手事務所ではチーム制で仕事を回すため、完全休暇を確保しやすい反面、期日に近い時期などは業務が集中し激務になりがちです。
勤務弁護士は、上層部から案件を割り振られることも多く、詳細なリサーチや書面のドラフト・修正作業の往復で、土日も起案などの作業に追われることもあり自身ではコントロールしきれない部分があります。
一方で、きちんとした福利厚生や研修制度がある事務所、組織化され案件管理やタスクの割り振りやスケジュールの組み立てが細やかに調整しているような事務所であれば、休暇の申請もしやすく、結果的に休日を確保しやすい場合もあります。
法律事務所(パートナー弁護士)
パートナー弁護士は、事務所の経営層や共同経営者としての立場を持つ弁護士です。
案件を取ってきて収益を上げる、事務所の運営を担うなど、経営的な視点も求められます。
休日は自己裁量で決めやすい一方で、事務所全体の経営や若手の指導、営業活動など、業務範囲が広くなります。また、顧客との重要な関係構築や対外的な活動が多く、結果的に休日のスケジュールも埋まりやすいです。
パートナー弁護士は一見、「上の立場だから自由に休める」ようにも見えますが、実際は事務所を回すためにプライベートの時間を犠牲にせざるを得ない状況も多々あります。
もちろん、顧客の接待などは、半ばプライベートの延長であることや、趣味の一貫のような側面もあります。
いずれにしても、自分の裁量と責任が大きい分、休日をどう活かすかが大きなテーマとなります。
インハウスローヤー(企業内と公務員)
インハウスローヤーは、一般企業に所属し、その企業の法律問題やコンプライアンス対応を担う弁護士です。
また、公務員として官公庁の法務部門で働く弁護士も増えてきています。
この場合、勤務先のカレンダーがそのまま適用されることが多く、土日祝日や年末年始などは一律に休みとして扱われるケースが一般的です。
働き方については、法律事務所ほど自由度はないかもしれませんが、会社員に近いワークライフバランスを実現しやすいメリットがあります。
そのため、若手弁護士やワークライフバランスを重視する弁護士の間では、インハウスローヤーへの転身が増加傾向です。
一方で、有給消化などは会社の状況によることや、業務量を調整した分だけ自由に取りたいだけ休みがとれるというわけではありません。
一般的な企業の管理職の方が休みにくい場合もあるように、法務のマネジメントレイヤーであれば、休暇を十分に取り切れるわけでもないという点は否めないでしょう。
それでも、福利厚生が充実している会社では、年間休日の設定が充実している場合もあり、プライベートとのバランスの取りやすさは期待できるでしょう。
独立開業
独立開業弁護士は、自身で事務所を立ち上げ、経営者としての側面を持ちます。
案件獲得から経理、マーケティングまでをすべて行う必要があり、休日の設定も完全に自己裁量です。
一方で、案件数をコントロールして自分のペースで仕事をするスタイルを確立できれば、理想的な働き方を実現できるでしょう。
たとえば、個人案件を中心に受けながら月数件の受任にとどめ、その分休日に趣味や家族との時間を充実させる弁護士もいます。
その他
近年は、フリーランス的な働き方や複数の事務所と業務委託契約を結ぶ形など、従来の枠組みにとらわれない働き方も増えてきています。
これらの場合は、業務範囲や報酬形態などが多様化する一方、休日をどう設定するかも自由度が増します。
また、弁護士だけでなく、「弁護士・司法書士・行政書士・税理士」など複数の資格を持ち、それぞれの業務を行っている人もいます。
そのような場合、単純な「休日」だけではなく、資格ごとの繁忙期の違いを考慮しながらスケジュール管理をする必要があるでしょう。
弁護士の求人紹介・転職相談はこちら
弁護士の休日の過ごし方パターン3選
ここからは、実際の弁護士がどのように休日を過ごしているか、その代表的なパターンを3つに分けて紹介します。
もちろん人それぞれのスタイルがありますが、筆者自身や周囲の弁護士のケースを参考にしながら解説していきます。
趣味や外出
最もポピュラーな休日の過ごし方は、趣味に打ち込んだり外出を楽しんだりするパターンです。
たとえば、ゴルフやテニス、ジムでのトレーニングなどアクティブな趣味を持つ弁護士は多く、平日のデスクワーク中心の生活をリフレッシュする意味でも積極的に体を動かします。
弁護士業務は精神的に負荷が高いため、休日にどうストレスを解消するかは重要です。
好きな場所に出かけたり、趣味に集中して気分転換を図ることで、翌週以降の業務効率が上がるという好循環が期待できます。
クライアントとの接待や会食(趣味としても)
弁護士の仕事には、顧客開拓や関係構築のためのコミュニケーションが欠かせません。
特に、企業法務を扱う弁護士やパートナー弁護士は、クライアントや取引先との会食やゴルフなどが休日の過ごし方として挙げられます。
一見“仕事”のようにも見えますが、当人たちにとっては趣味の延長や交友の一環として楽しんでいるケースもあります。
休日にオフ感覚でクライアントと交流を深めることで、仕事にも好影響を及ぼすことがあるため、あえて「会食やゴルフを休日に入れる」弁護士も多くいます。
筆者自身も、仕事とプライベートの境界がない感覚を感じる時間も多くありますが、まさにこのような時間です。
仕事をする
最後のパターンは、「休日でも仕事をする」というもの。
これは弁護士あるあるですが、案件が詰まっているときや重要な裁判期日が迫っているときには、休日にまとまった時間を確保して書面作成やリサーチ、打ち合わせを行うことがあります。
もちろん、休日は本来休むべき時間ですが、弁護士特有の“いつでも連絡が来る可能性がある”という性質上、完全オフにするのが難しいのも事実です。
ここでは、「休日に仕事をするか、しないか」は本人の裁量や案件状況によって変わってきます。
弁護士はどうやって休日を確保している?
「弁護士は休日が少ない」といわれる一方で、しっかりと休みを取り、趣味や家族との時間を満喫している弁護士も確かに存在します。
では、いったいどうやって休日を確保しているのでしょうか。ここでは、代表的な方法や考え方を紹介します。
案件処理の状況や受任のコントロール
弁護士の休日は、受任している案件の数とタイミングに大きく左右されます。
たとえば、独立開業弁護士であれば、受任する案件の量をある程度調整することで、ある時期を“休み”と決めてまとめてオフを取ることも可能です。
特に忙しい時期には休日も返上で働き、ピークが過ぎたらまとめて休暇を取るというメリハリをつける弁護士も多く、“結果的に年に1回は海外旅行に長期滞在できる”というケースも珍しくありません。
打ち合わせなどのスケジュール調整
クライアントとの打ち合わせや裁判期日、会議などは、弁護士がコントロールできる部分もあれば、裁判所やクライアントの都合に合わせる部分もあります。
とはいえ、ある程度先回りしてスケジュールを立てることで、休日を確保する努力が可能です。
今やオンライン会議やチャットツールなどを活用すれば、物理的に事務所にいなくてもクライアントと連絡を取り合えます。
これにより、場所や時間にとらわれない働き方を実現し、休日の調整も行いやすくなっています。
取扱っている事案の内容や期日間隔
弁護士が扱う案件には、民事訴訟、刑事事件、企業法務、離婚・相続などの家事事件、債務整理、行政事件など多種多様です。
事案ごとに期日の進み方や必要となる準備の内容が異なり、それによって休日の確保のしやすさも変わってきます。
このように、扱う案件の種類によって休日の概念が変わることも弁護士業務の特徴の1つです。
刑事事件をメインにしている弁護士は、土日や夜間の警察対応が必要になることも多い一方で、企業法務中心の弁護士は平日昼間に打ち合わせが集中し、休日はオフになりやすいなど、分野ごとの違いを意識すると良いでしょう。
インハウスローヤーなら土日祝日休みも
前述のとおり、インハウスローヤー(企業内弁護士)であれば、企業の就業規則に則って土日祝日が休みとなるケースが多いです。
もちろん、緊急案件が発生すると休日出勤を要請されることもありますが、法律事務所に比べると突発的な対応は比較的少ないといえます。
ただし、インハウスローヤーは企業活動の最前線で働くため、国際取引の対応や海外子会社のトラブルなどがあると、時差に合わせて深夜や休日も動く必要があるケースもあります。
必ずしも“定時勤務”だけでは済まないものの、法律事務所と比べると休日の予測がつきやすいのがメリットです。
スキマ時間の活用や集中的な業務時間の確保など
弁護士業務は、細切れの時間が多いのも特徴です。電話相談やメール対応、面談などが日中に散発的に入り、書面作成や調査はその合間に行わざるを得ないことも多いでしょう。
この細切れ時間を上手に使いこなすかどうかで、休日の余裕が生まれるかが変わってきます。
「業務効率化」の手段を講じていくことで、自然と休日を確保できるようになります。
逆に、ダラダラと平日夜間まで事務所に残っていると、休日を思うように使えなくなる傾向もあるため、オンとオフをはっきり切り替える姿勢が重要です。
弁護士の求人紹介・転職相談はこちら
ある弁護士の休日
ここでは、筆者自身の経験を踏まえつつ、弁護士の休日スケジュールの一例を示します。
弁護士の休日がどのように流れるのか、具体的なイメージを持っていただくための参考にしてください。
午前中
- ゆっくり起床:平日の業務時間は朝早く出社し、夜遅くまで続くこともあるため、休日は身体を休めるために少し遅めに起きることが多いです。
- ジョギングやジム通い:運動不足を解消し、リフレッシュするために朝からランニングをしたり、フィットネスクラブへ行く弁護士は少なくありません。
- 家族との時間:小さいお子さんがいる弁護士の場合は、家族で朝食を食べたり、子どもを公園に連れて行ったりするなど、普段なかなか取れないコミュニケーションの時間を大切にします。
ランチ
- 外食で気分転換:平日は忙しくてコンビニ弁当や事務所近くの定食屋で済ませがちなので、休日は少し遠くまで足を伸ばして美味しいランチを楽しむ場合があります。
- 仲間や友人との食事:他の弁護士や企業法務の仲間など、同業者や職種が近い人と情報交換することも。
- 接待を兼ねる場合も:前述したように、休日にクライアントと食事をするケースもあり、仕事とプライベートが混在することが少なくありません。
午後
- 趣味の時間:映画鑑賞や美術館巡り、スポーツ観戦など、趣味を存分に楽しむ弁護士もいます。最近はテレワーク環境が普及したこともあり、オフィスに行かずとも最低限のメールチェックはスマホでも可能なので、外出中でも業務への対応は柔軟に行えるのが強みです。
- 書面作成やリサーチ:どうしても週明けの期日やクライアントへの提出物が迫っている場合は、午後の数時間を仕事に充てることもあります。集中して数時間取り組めば、平日何日分もの作業がはかどるケースもあります。
夕方から夜
- 友人や同僚弁護士との会食・飲み会:弁護士同士で仕事の悩みを共有したり、情報交換をしたりすることは頻繁にあります。日中は家庭サービスをして、夜に同業者と会ってストレス発散をするという弁護士も多いです。
- 家族と外食・自宅でゆったり:子どものいる弁護士の場合、夜は家族団欒の時間に充て、週末にしか見られないテレビ番組を一緒に見たり、ホームパーティ的に料理を楽しむことも。
- 早めに就寝:平日の疲れをとるために、休日は無理をせず早めに寝るという健康志向の弁護士も増えています。
まとめ
「弁護士の休日はいつなのか?」という疑問に対し、その答えは「一概には言えないが、実は自由度が高い部分もある」というのが実情です。
土日祝日は一般企業のようにカレンダー通りには休めないことも多いですが、一方で平日にオフを取れることもあり、自身の裁量でスケジュールを組みやすいメリットがあります。
また、法律事務所の勤務弁護士やパートナー弁護士、インハウスローヤー、独立開業など、所属形態や働き方によって休日の概念は大きく変わります。
さらに、クライアントの状況や案件の種類によっては、休日でも対応を迫られることもあるため、いかに効率的に業務をこなし、オフを確保するかが重要です。
- 弁護士の休日は「土日祝日が休み」という固定概念には当てはまらない
- 平日に休む自由度がある一方、案件の状況次第では土日祝日でも仕事
- 所属形態(勤務弁護士、パートナー弁護士、インハウスローヤー、独立開業など)で休日の取り方や過ごし方は大きく異なる
- 趣味を楽しむ、クライアントと会食する、休日でも仕事をするなど、過ごし方は千差万別
- 案件のコントロールやスケジュール管理、スタッフとの協力などを通じて休日を確保している
弁護士と聞くと「いつも忙しくて休む暇がない」という印象を持つかもしれませんが、実際にはワークライフバランスに配慮しながらキャリアを積み重ねることが十分可能です。
特に近年は、インハウスローヤーや時短勤務など多彩な選択肢が増え、法曹界全体の働き方が多様化しています。
これから法曹を目指す方は、「弁護士になったら本当に休めるのか」と不安に思うかもしれませんが、自分の志向や得意分野、ライフスタイルに合った所属先・業務分野を選ぶことで、ある程度コントロールの効く働き方を実現することも可能です。
また、すでに弁護士として働いている方であれば、案件の取捨選択やスケジュール管理を工夫し、休日を充実させるヒントとして本記事を活かしていただければ幸いです。
弁護士の求人紹介・転職相談はこちら