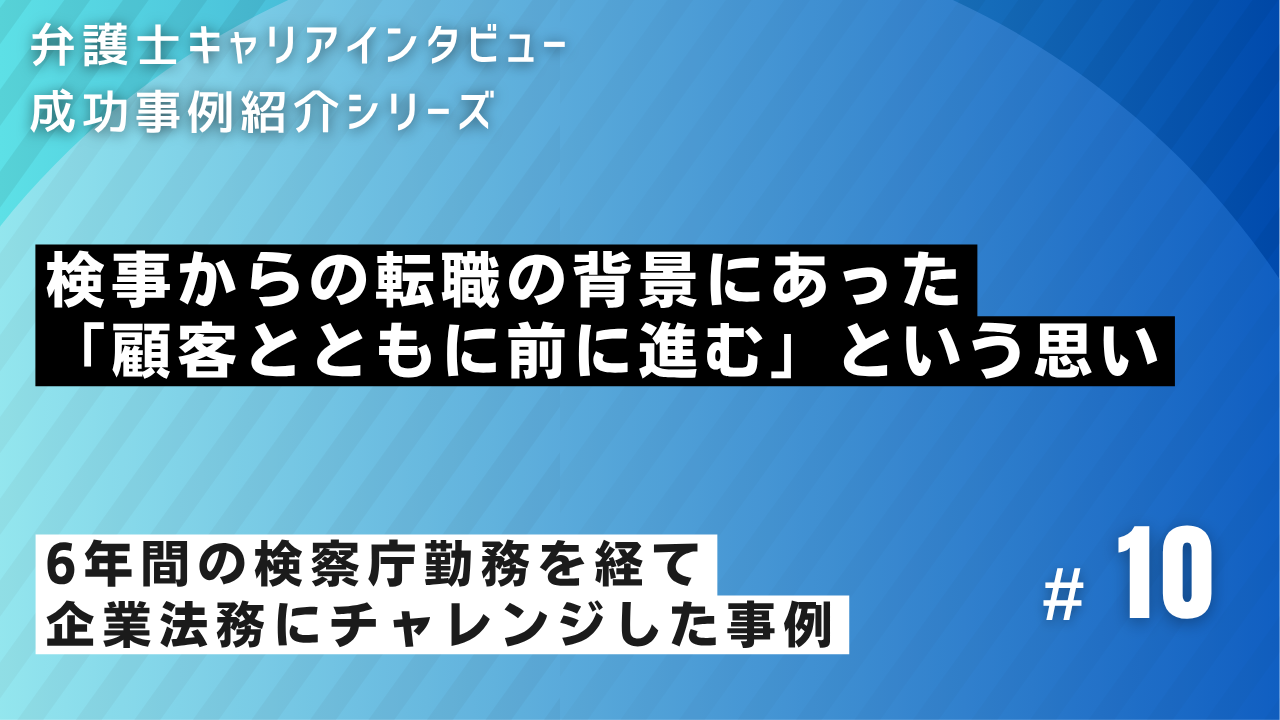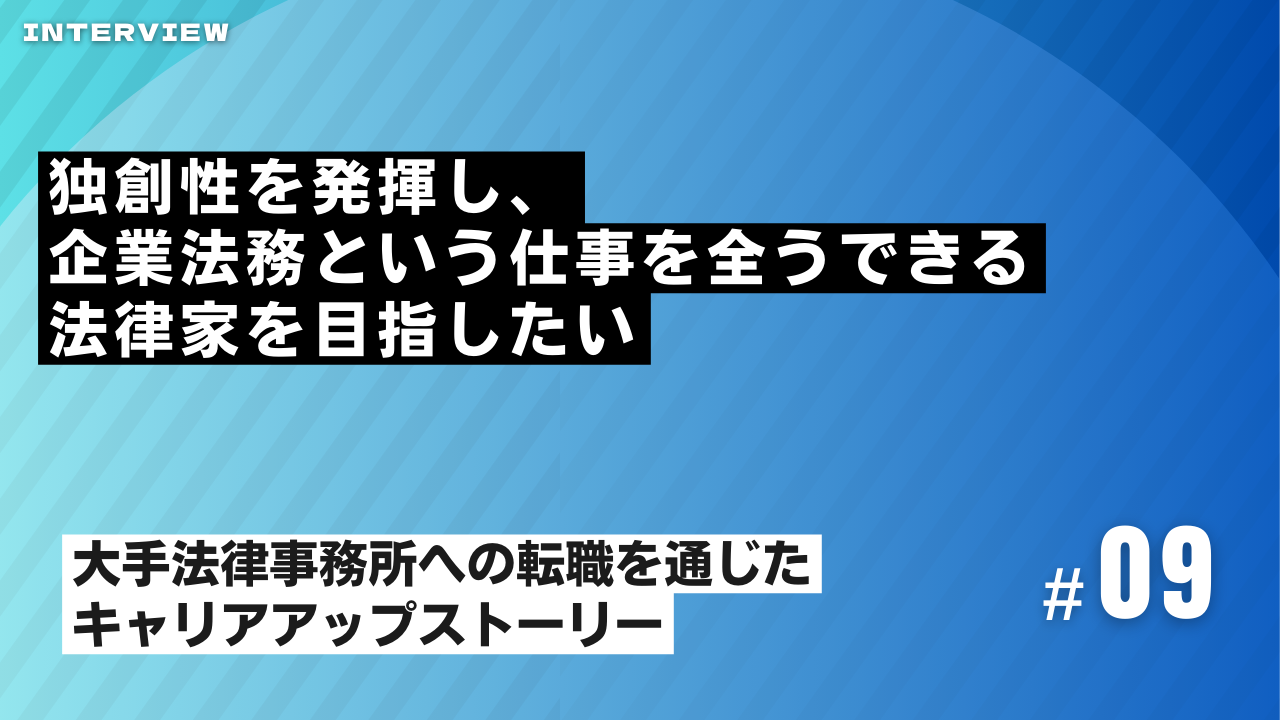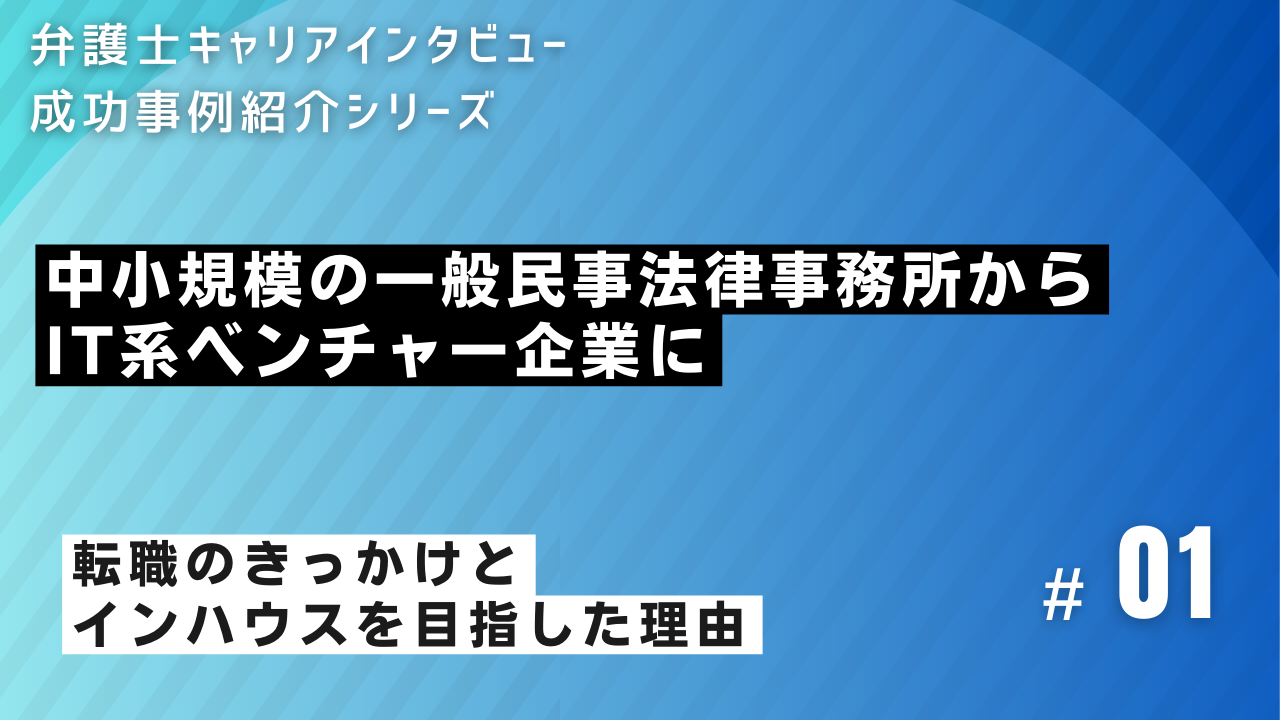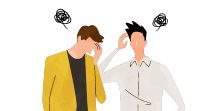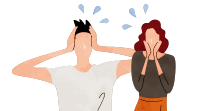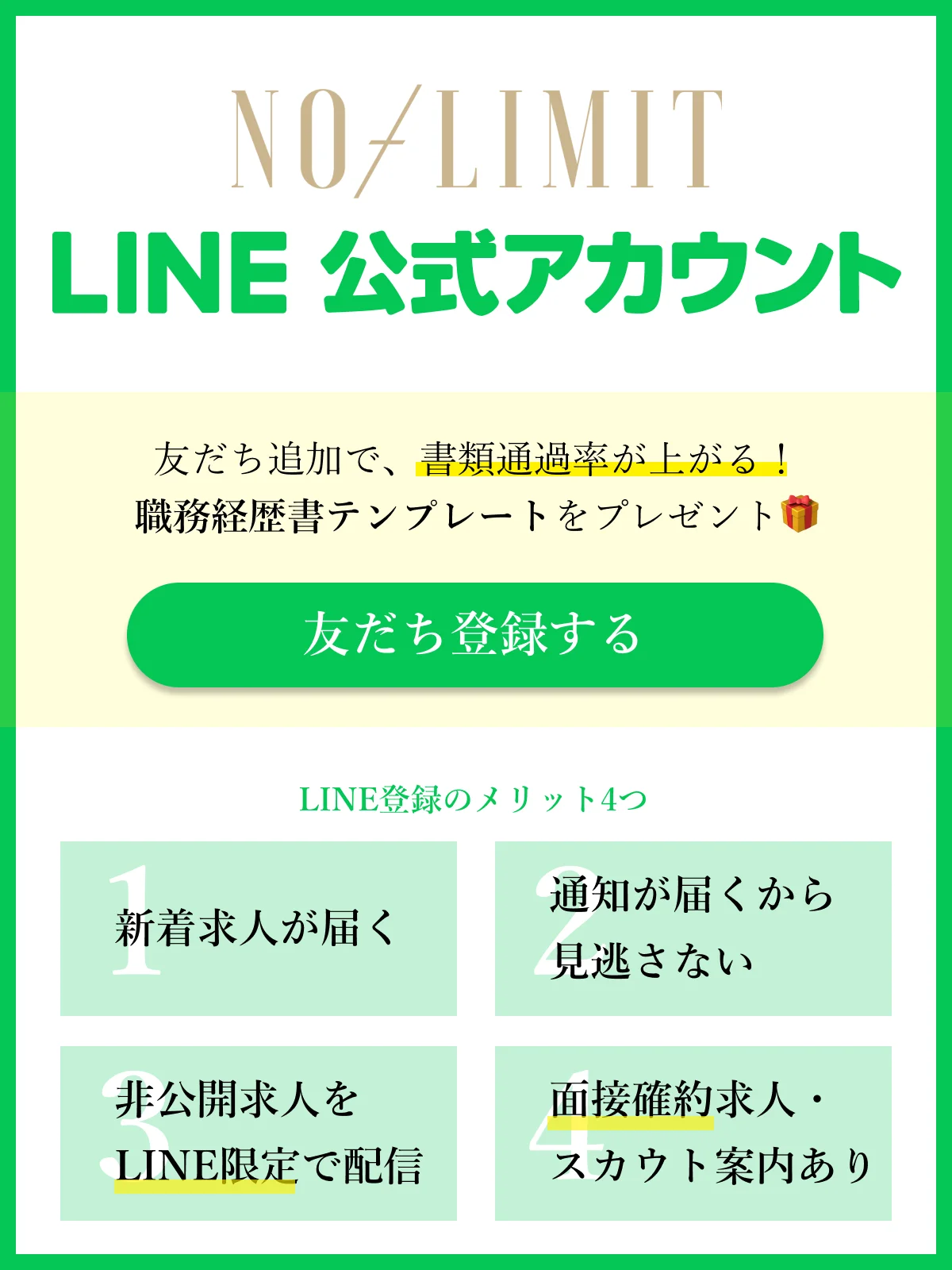日本内外の企業がグローバルに事業を展開する中、法務人材もボーダレスな活躍の場として国際法務が注目されています。
外資系の企業、コンサルティングファーム、弁護士有資格者であれば法律事務所も含めて、国際法務に携わる場は様々です。
国際法務に関する業務内容や種類、求められるスキルや国際法務に強い人材の獲得ポイントを解説します。
目次
国際法務とは何か?グローバルビジネスで求められる専門性
グローバル化が進展する現代において、企業の活動範囲は国内にとどまりません。
製品やサービスが海外市場で流通し、多国籍の企業同士が協業するケースも当たり前になってきました。
そこで必要とされるのが、「国際法務」です。
国際法務とは、単純に「英語を使って法律的なやりとりをすること」だけを指すわけではなく、複数の国や地域にまたがるビジネスを円滑かつ合法的に進めるために必要となる法的支援やリスク管理を指します。
国際法務の専門家が担う役割は多岐にわたります。
たとえば、海外で製品やサービスを提供する際に必要な契約書の作成やリーガルチェック、国際取引のリスク評価、現地の法制度への対応、さらには国際的な訴訟・仲裁に至るまで、その範囲は非常に幅広いものです。
また、近年ではIT技術の発達に伴い、オンライン上で取引や契約を行う「越境EC」や「クラウドサービスの国際利用」など、新たなビジネスモデルが次々と生まれています。
こうしたビジネスモデルは国境を超えて行われるため、データ保護法やサイバーセキュリティ規制などに対して多国籍での対応が必要です。
国際法務は、もはや一部の専門家だけが担う領域ではなく多くの企業が必須のリソースとして確保すべき分野になっています。
国際法務案件の種類
国際法務において取り扱う案件の種類は、どのようなものがあるでしょうか。ここでは6つ解説していきます。
英文等の外国語での契約書対応及び契約交渉
国際法務の代表的な業務のひとつが、外国語による契約書対応や契約交渉です。
グローバル企業の取引先が海外にある場合、英語やその他現地言語で作成された契約書を精読し、必要に応じて修正案を提示して交渉を行う必要があります。
契約書の内容に法的リスクが潜んでいないかをチェックし、クライアントが不利にならないように文言を調整するなど、綿密なコミュニケーションが求められます。
また、実際の契約交渉の場面では、相手国のビジネス慣習や契約文化を理解して交渉を進めることが重要です。
契約交渉は単に「法的知識と英語力」があればいいというものではなく、取引相手の拠点とする国の文化的背景や商慣習を踏まえて、Win-Winの関係を構築できるような調整力やコミュニケーション能力が求められます。
クロスボーダーM&A
クロスボーダーM&Aとは、海外の企業を買収したり、逆に海外から日本企業が買収を仕掛けたりする際に発生する法務案件です。
具体的には、デューデリジェンス(対象企業の法務・財務・税務状況の調査)や、買収契約のドラフト・レビュー、株主間契約や業務提携の条件交渉といったさまざまな業務が発生します。
デューデリジェンスの際には、現地の専門法令の知識も必要となりますし、財務や税務面も含めた横断的な分析・検討が求められます。
さらにM&Aが成立して終わりではなく、その後のPMI(Post Merger Integration)――統合後の経営体制や社内ルール、コンプライアンス体制の構築を円滑に進める際にも国際法務の視点が欠かせません。
異なる法制度やビジネス文化を背景に持つ企業同士が一体化するためには、各国の法令、労務・税務の規制を理解しつつ、新しい組織のルールを設計する必要があります。
国際仲裁・訴訟対応
海外の取引先とトラブルが発生した場合、通常の国内訴訟とは異なるプロセスを踏むことが多々あります。
これには、国際仲裁機関を利用した仲裁手続きや、海外の裁判所での訴訟が想定されます。
これらは手続き自体が国内とは大きく異なり、英語を中心とした資料作成やプレゼンテーションが必要です。
また、管轄の問題や適用される法制度に関する検討が必要になるため、国際法務の知識と経験がないと十分に対応できません。
国際仲裁条項を契約書に盛り込むことの是非や、紛争が起きた場合に備えた事前のリスクマネジメント体制の構築など、予防的な法的戦略も求められるのが国際法務の特徴です。
現地法令の調査と規制対応
海外進出する企業は、進出先での事業許認可や現地労務規制など、さまざまなルールに対応しなければなりません。
こうした対応を怠ると、罰則を受けたり、事業継続が困難になるリスクもあります。
そこで国際法務の専門家は、現地の法律事務所やコンサルタントと連携しつつ、最新の法令情報をキャッチアップし、クライアント企業の事業が円滑に進むようアドバイスを行う役割を担います。
また、国や地域によって大きく異なる労働法や雇用ルール、消費者保護などの規制にも注意が必要です。
こうしたローカルルールを踏まえた事業運営ができるかどうかが、海外事業の成否に直結するケースも少なくありません。
GDPR等の国際的なルールへの対応
EU一般データ保護規則(GDPR)の施行以降、各国・地域で個人情報保護やプライバシーに関する規制が強化され続けています。
日本においても個人情報保護法の改正が相次いで行われ、海外とのデータのやり取りについて厳格なルールが求められる状況です。
このように、グローバルに共通化が進むルール(データ保護、競争法、賄賂禁止法など)にいち早く対応しないと、企業は高額な制裁金や信用失墜のリスクにさらされる可能性があります。
国際法務の担当者やチームは、これらのルール動向を常にチェックし、契約や内部統制、システム構築の観点から会社のコンプライアンスを支えることが期待されるでしょう。
税務やファイナンス
クロスボーダーの取引を行う上では、国際税務の視点も重要です。
移転価格税制やPE(恒久的施設)の問題、源泉徴収税の扱いなど、国ごとに異なるタックスルールを理解しなければなりません。
さらにファイナンスの領域でも、海外で資金調達を行う場合の金融規制や、為替管理法規制などを把握しておく必要があります。
これらの問題は、国際法務の枠を超えて財務・会計部門との連携が不可欠です。
しかし、国際法務に携わる人材としても、最低限の税務やファイナンスの仕組みを理解していると、より実効性の高い法務アドバイスができるようになるでしょう。
国際法務と国内法務との比較ポイント3つ
続いて、国際法務と国内法務ではどこが大きく違うのかについてみていきましょう。
ここでは、基本的なリーガルコミュニケーションやドキュメントマナー、海外法令や国際規格に関する知識、法的交渉の慣習やルールに関する知見の3つのポイントを解説していきます。
基本的なリーガルコミュニケーションやドキュメントマナー
国内法務であれば、日本語を使って法的コミュニケーションを行い、日本法を前提とした契約書や社内規程を作成するのが主流です。
一方、国際法務では、英語やその他現地言語で契約書を作成するのが基本となります。
リーガルドキュメントの形式・マナーや記述の慣習が異なるため、単純に「日本語の契約書を英語に直す」だけでは十分でないケースも多いのです。
例えば、英語の契約書であれば「Whereas, …」で始まる前文(Recitals)の書き方や、定義(Definition)の配置、細かい句読点ひとつですら法的な意味が大きく変わる場合があります。
また、一般的な法令に属する事項でも、すべて契約書内に盛り込むことが必要であり、契約書に記載がないことは考慮されない慣習もあります。
こうした背景を理解してコミュニケーションを行うためには、一定の語学力に加え、海外の法文化に関する素養が必要となります。
海外法令や国際規格への知識
国内法務は日本法を中心に扱い、関連する判例やガイドラインなども日本語で入手できます。
一方、国際法務では、複数の国の法令や国際条約、国際規格に関する知識が求められます。
たとえば、WTOルールやEU規制(GDPRやCompetition Lawなど)を踏まえた取引条件の調整が必要な場合や、米国の制裁規則(OFAC規制)に抵触しないかといった検討が日常的に発生します。
また、同じ国の法制度でも、州や自治体によって規制が異なるケースもあるため、現地の法律事務所と密接に連携しながら対応方針を決めることが一般的です。
法的交渉の慣習やルールの知見
法的交渉のプロセスや態度、契約書のチェックポイントなどは、国や地域によって大きく異なります。
たとえば米国企業との契約交渉では、初期段階から厳格な責任条項や損害賠償条項の範囲を定義したがるケースが多い一方、ヨーロッパ企業の場合はGDPR対応を重視し、データ保護の条項を手厚くすることが一般的です。
このように、交渉対象がどの国の企業なのか、どのような法的背景を持つのかによって、ポイントが変わってきます。
国内法務と比較して、国際法務ではこうした「異文化・異法域」への適応力が大きく試されると言えるでしょう。
国際法務が求められる3つの背景
ここまで様々な国際法務の種類や、国内法務との違いについて解説してきました。
では、国際法務が求められる理由や背景はどのような点にあるでしょうか。ここでは3つに絞って解説していきます。
競争環境のグローバル化
日本国内の市場だけをターゲットにしていた従来のビジネスモデルでは、世界的な大企業やベンチャー企業との競争に打ち勝つことが難しくなっています。
IT企業を中心に海外展開を視野に入れた事業設計が当たり前となり、海外の大手企業が日本市場に進出するケースも増加傾向です。
このようなグローバル競争の中で、法務部門のグローバル対応力が企業の競争力を大きく左右しています。
越境的・国際的な法令やルールの拡大
EUや米国を中心に、国際的な規制ルールが次々と整備・強化されています。
GDPRによるデータ保護規制やFCPA(米国海外腐敗行為防止法)などが代表例で、海外事業を展開する企業はこれらへの対応が不可欠です。
こうした規制は、企業活動の自由度を制約する反面、透明性を高めて企業の社会的信用を守るための大きな要素でもあります。
対応を誤れば大きなペナルティが科されるだけでなく、企業イメージの失墜にもつながりかねません。
国際的な企業間紛争の増加
海外企業同士の取引が増えるにつれ、契約上のトラブルや知的財産権の侵害、独占禁止法関連の問題など、国際的な企業間紛争が増加しています。
紛争が起こってから法務担当者が動くのではなく、事前にリスクを特定し、紛争を避けるための予防法務を実践できる体制が不可欠です。
紛争が避けられない場合も、国際仲裁・国際訴訟に対応できるスペシャリストが社内外に存在しているかどうかで、企業のダメージを最小限に抑えられるかが変わってきます。
国際法務に関する最新トピック
国際法務に関してどのような点が注目されているか、最新のトピックを4つご紹介していきます。
海外M&AとPMI(Post Merger Integration)実務での法務課題
従来から盛んに行われてきたクロスボーダーM&Aは今後も増加が見込まれています。
その中でも特に注目されるのが、買収後のPMIにおける法務課題です。
企業統合の際には、労務制度の統合、契約書の再編、コンプライアンス方針の標準化などが必要になり、国や地域ごとに異なるルールをうまく繋ぎ合わせる必要があります。
今後はM&Aのスピードや複雑化が増す中で、PMI段階で生じる法務課題を迅速かつ的確に対応できる人材が求められるでしょう。
AI関連の法規制や訴訟への対応
AI(チャットボットや画像生成ツールなど)の急速な普及とともに、新たな法的課題が生まれています。
AIが自動で生成するコンテンツの著作権問題、AIの出力結果が誤情報を含む場合の責任問題、個人情報の取り扱いなど、世界各国で規制や指針の整備が進められている段階です。
国際法務の観点からも、AIを利用したサービスの海外提供に関する利用規約の整備、データの取扱いに関する規定の検討などが今後さらに需要を増していくと考えられます。
ESG関連の規制対応
環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字をとったESGは、企業経営の重要な指標として注目を集めています。
特にEUを中心に、ESG関連の開示規制が強化され、企業は気候変動対策や人権リスク管理などの取り組みを求められるようになりました。
こうした規制対応には、環境法や人権法、サプライチェーン管理に精通した国際法務の視点が必要です。
経済安全保障
近年、先進国を中心に経済安全保障の観点から、海外投資や輸出管理が厳格化される動きが強まっています。
国家の安全保障上の理由から、特定国への技術移転や輸出が制限されるケースが増えているのです。
企業にとってはサプライチェーンの見直しや、新たな許認可制度への対応が必要になり、国際法務の役割が大きくなっています。
国際法務人材に求められるスキルと要件
国際法務に携わるためには、どのようなスキルや要件が必要なのでしょうか。
以下ではポイントを3つに分けて紹介します。
語学力だけではない!スキルセットの最新傾向
国際法務というと「英語力が最優先」と考えられがちですが、近年では語学力以外のスキルが重視される傾向にあります。
もちろん英語やその他外国語でのコミュニケーションは必須ですが、それだけでは差別化が難しくなってきているのです。
たとえば、国際的な契約書のドラフティングや法令リサーチを行うには、リーガルライティングの技術が必要になりますし、契約交渉には異文化理解力や交渉力が欠かせません。
さらに、デジタル化が進む中で、オンラインツールやAIを活用して効率的に業務を進めるITリテラシーを備えていると大きなアドバンテージになります。
法的知識とビジネス感覚
国際法務に求められる専門知識は、日本法に限りません。
主要取引国の商法や民法、国際仲裁法、投資関連法令など、多岐にわたります。とはいえすべての国の法律を網羅的に知ることは現実的ではありません。
そこで基本的な英米法の考え方を理解し、必要に応じて現地の専門家と連携できるフットワークが重要になります。
また、法的な判断に加えて、ビジネスの視点で最適解を提示する能力が必要です。
クロスボーダー取引の際には、会社の利益最大化とコンプライアンス遵守のバランスをどう図るかが重要になります。
机上の法理だけではなく、事業や市場の状況、相手国の商習慣を考慮したうえで的確なアドバイスができる法務人材が求められるでしょう。
ソフトスキルの強化
法務の仕事というと、どうしても書面やリサーチといった「固い」イメージが先行しがちですが、国際法務ではコミュニケーション能力や交渉力、チームワークといったソフトスキルが非常に重要です。
特に以下の要素は意識して磨く必要があります。
- 異文化コミュニケーション力:違う言語、異なる文化背景を持つ人々とのスムーズなやり取り
- プロジェクトマネジメント力:海外子会社や外部の弁護士、コンサルタントなど、多様なステークホルダーを取りまとめる能力
- 問題解決力:想定外の法律問題や規制変更があった際に、迅速に情報を集めて解決策を検討する柔軟性
国際法務分野でのキャリアパス
では、国際法務に携わりたい人材はどのようなキャリアを描くのでしょうか。ここでは代表的なルートを3つご紹介します。
国際法務に関するキャリアの種類
国際法務に関わるキャリアには、様々な種類があります。特に弁護士資格がある場合には、法律事務所を含めて主に3つ挙げられるでしょう。
- 企業内法務(インハウスロイヤー):メーカー、商社、IT企業、金融機関などの法務部に所属し、海外案件をメインに担当する。
- 法律事務所(弁護士):クロスボーダー案件に強みを持つ国際系法律事務所や外資系事務所で活躍。
- コンサルティング・ファーム:ビジネスコンサルタントとして国際取引のスキーム作りやコンプライアンス対応をサポートする。
それぞれ求められる知識やスキル、日常業務の内容は異なりますが、いずれも海外案件を扱うことでキャリアに深みが増し、高い市場価値を得られるメリットがあります。
国内法務からのキャリア形成の仕方
はじめは国内案件をメインに経験を積み、徐々に海外関連のプロジェクトに参加することで国際法務の経験値を高めるケースが多いです。
具体的には、次のようなステップが考えられます。
- 国内での法務基礎を固める:契約書レビュー、社内規程整備、労務対応、コンプライアンス教育など、基本的な法務スキルを習得。
- 語学力の強化:TOEICや英検などで目標スコアを目指すだけでなく、海外ドラマや英語文献を活用して実践的な表現を身につける。
- 海外関連案件への参画:社内で海外子会社にまつわる契約や、外国人取引先とのプロジェクトがあれば積極的に手を挙げる。
海外での実務経験の積み方
より本格的に国際法務へ進むには、海外での実務経験が大きな武器になります。
たとえば、海外赴任や海外大学でのLL.M.取得、海外ロースクールへの留学などが代表的な方法です。
現地の法体系や言語、文化を肌で感じることで、国際案件に対応できる即戦力としてアピールできます。
また、国内にいながらでも、海外の法令データベースやオンラインセミナーを活用して知見を広げることが可能です。
国際法務求人の市場動向と年収・待遇
国際法務に関する人材の市場や年収、待遇はどのような内容かみていきましょう。
求人数・ニーズの拡大傾向
グローバル化の加速とともに、国際法務人材のニーズは拡大傾向にあります。
特にアジアや欧米に積極進出する日系企業や、逆に日本市場を攻める外資系企業など、多方面から求人が増えています。
また、スタートアップやベンチャー企業でも「グローバルな事業展開を視野に入れているので、最初から国際法務担当を置きたい」というニーズが高まっています。
平均年収・待遇水準
国際法務案件を扱う企業や法律事務所では、年収水準が国内法務より高めに設定されるケースが多いです。
これは、語学力や専門知識など、ハードルの高いスキルセットを求められるためです。
加えて、海外案件を通じて得られる収益やリスク管理の重要性が大きいことから、企業としても優秀な人材を確保するために高めの報酬を用意する傾向があります。
一般的には、企業内法務であっても年収800万円~1,500万円程度の幅で提示されることが多く、外資系法律事務所や国際法律事務所ではさらに高額になるケースも。
ただし、年収は企業規模や業界、個人の経験・スキルによって大きく変動します。
国際法務の担当者になるための転職にはエージェントの活用がおすすめ!
国際法務ポジションへの転職を検討している場合、専門の転職エージェントを活用するのが効果的です。
国際案件を扱う求人は非公開であることも多く、自力でリサーチしにくい側面があります。
転職エージェントを活用するメリット
- 非公開求人の紹介:インターネット上には出ない特別なポジションを紹介してもらえる
- 応募書類のブラッシュアップ:英文レジュメやエントリーシートなどをプロの目線でチェック
- 面接対策・条件交渉サポート:面接でよくある質問の傾向や、採用企業との年収交渉などをサポート
- キャリアアドバイス:国際法務でのキャリアパスやスキルアップの方法など、個別に相談できる
転職エージェント選びのポイント
- 国際法務案件の取扱実績:どの程度の実績があるか、担当コンサルタントに海外案件への知見はあるか
- 専門分野に精通したコンサルタントの存在:法律関連のバックグラウンドを持つコンサルタントや、外資系企業とのパイプを持つスタッフがいるか
- コミュニケーションの丁寧さ:転職希望者の希望をじっくりヒアリングし、適した求人を提案してくれるか
No-Limit弁護士の特長
まず、弁護士業界に精通したアドバイザーによるサポートが受けられる点です。
No-Limit弁護士は、弁護士業界に特化した求人案件を扱っていることから、法務人材として求められる人材要件を言語化し、資質などを精密に判断することができます。
また、ハイクラスの求人案件も多数取り扱っています。その中で、国際法務に関わるものもあり、就職や転職の成功事例も積み重ねています。
法務人材の中長期的なキャリア形成にも精通したアドバイスを提供することができます。
N0-Limit弁護士では、様々なフェーズやキャリアパスによる就職や転職の支援実績があり、キャリア形成においても様々なパターンから中長期的なキャリアを見据えたアドバイスを強みにしています。
まとめ
国際法務は、グローバルビジネスが前提となる現代の企業活動において非常に重要なポジションです。
英文契約書のレビューやクロスボーダーM&A、国際仲裁、現地法令への対応など、多岐にわたる専門業務を通じて企業のリスクを減らし、成長をサポートします。
近年では、AIやESG、経済安全保障などの新たな法的課題が次々に登場し、国際法務人材に求められるスキルや知見も高度化しているのが現状です。
国際法務へのキャリアパスは、企業内法務や法律事務所、コンサルティングファームなど多様であり、それぞれの場所で活躍のチャンスがあります。
語学力だけでなく、海外の法制度や文化、ビジネス感覚、ソフトスキルなど総合的な能力が必要とされるため、国内法務での実務経験をベースにステップアップしていく人も多くいます。
また、国際法務の求人需要は拡大傾向にあり、年収・待遇も比較的高い水準で推移しています。転職を検討する際は、国際法務の求人を豊富に取り扱うエージェントを活用することで、キャリア選択の幅を広げられます。「No-Limit弁護士」のように専門知識と実務経験を兼ね備えたコンサルタントが在籍しているエージェントを頼りにするのは、最短距離で国際法務のキャリアを切り開くコツと言えるでしょう。
今後もグローバル化と技術革新はさらに進み、企業や社会が直面する法的課題は一層複雑化すると考えられます。
こうした大きな変化の中でも、国際法務の力を活かして企業の成長に貢献できる人材は、間違いなくビジネス界で重要な存在として評価され続けるでしょう。
もし国際法務へのキャリアアップを目指すなら、早めに情報を収集し、適切な学習や実務経験の積み方を計画すると同時に、頼れるエージェントを活用してぜひ夢を実現させてください。